目次
人事評価における不服申し立ての現状
不服申し立ての制度とは?
人事評価は企業にとって重要な業務のひとつですが、評価結果に納得できない従業員からの不服申し立ても少なくありません。
多くの企業では、不服申し立てを受け付けるための制度を設けています。
これには、正式な異議申し立ての手続きや再評価の機会を提供する仕組みが含まれます。
たとえば、評価結果を受けた従業員が一定期間内に人事部に申し立てを行い、必要に応じて上司や第三者委員会による再評価を受ける制度が一般的です。
しかし、不服申し立ては人事評価への不満から起こるものであり、放っておくと社員の反感や職場環境の悪化を招くことになります。
人事評価への不服の背景
従業員が人事評価に不満を持つ背景には、いくつかの要因があります。例えば、評価基準が不明確であったり、評価者によって判断がばらついたりすることなどです。また、評価のフィードバックが十分に行われず、従業員が納得感を持てないケースもあります。
「なぜ自分の評価がこの結果になったのか?」という疑問を持つ従業員が増えると、企業全体のモチベーション低下にもつながるため、注意が必要です。
不服申し立てにおける企業側のリスク
企業における不当な評価のケース分析
企業においては、意図せず不当な評価を行ってしまうケースがあります。
例えば、評価者の主観が強く反映された結果、特定の従業員が不利な評価を受けることがあります。
また、評価の根拠が不十分で、具体的な業務成果よりも「印象」や「好き嫌い」で評価が決まるケースも問題です。これが積み重なると、従業員の不満が爆発し、企業の信頼性が失われてしまいます。
企業が被る不服申し立ての影響
不服申し立てが増えると、企業にはさまざまな影響が及びます。
まず、対応にかかる時間とコストが膨らむことが挙げられます。他にも従業員の士気が低下し、最悪の場合、訴訟や労働紛争に発展することもあります。
こうした事態を防ぐためには、評価制度の透明性を高め、不満が生じにくい環境を整えることが必要です。
不服申し立てされない評価制度を作るには?
評価基準を改善する
評価基準を明確にし、公正な評価が行われるようにすることが重要です。業績評価だけでなく、スキルや行動に関する基準も明示し、客観的な指標を増やしましょう。こうすることで、従業員の納得感を高めることができます。
また、スキルマップを活用することで、従業員の能力を可視化し、評価に活かすことができます。スキルマップを用いれば、従業員ごとの得意分野や習得が必要なスキルを明確に把握でき、それに基づいた公平な評価を行えます。これにより従業員は、「成長の過程が評価に反映されている」と感じることができ、従業員のやる気の向上に繋がります。
曖昧な基準を排除する
「頑張っている」「期待に応えた」といった抽象的な評価ではなく、具体的な数値や事例を用いた評価基準を設定することが不可欠です。例えば、「売上目標の達成率」や「プロジェクト完了率」など、客観的なデータに基づいた評価を行うと、公平性を確保できます。
従業員の成長を促す施策をとる
評価が単なる査定ではなく、従業員の成長を支援する仕組みとして機能するようにすることも重要です。具体的には、定期的なフィードバックの機会を設けたり、スキル向上のための研修を充実させたりすることで、評価に対する納得感を高めることができます。
ほかにも、定期的にスキルマップを振り返らせることで、従業員が自身に足りないスキルを認識し、努力する計画を立てられます。
制度改正に向けた人事部の役割
不満を抱える社員のサポート
評価結果に不満を持つ従業員と面談を行い、納得できる説明を行うことで、不服申し立てを未然に防ぐことができます。評価に対する不満がどこから生じているのかを把握し、制度の改善につなげることも重要です。
評価改善のためのフィードバックを行う
評価者と従業員の間で、定期的なフィードバックの場を設けることが効果的です。
評価結果が一方的に伝えられるのではなく、双方向のコミュニケーションを重視することで、不満の解消につながります。
従業員との信頼関係構築
透明性のある評価制度を維持するためには、従業員との信頼関係が不可欠です。日頃から従業員と密にコミュニケーションをとり、従業員の生の声を集めましょう。従業員の意見を反映した制度設計を行うことが、長期的な信頼構築につながります。
人事評価制度の透明性と公正性を確保するには?
目標による評価を導入する
公平な査定を実現するためには、従業員が設定した目標をどの程度達成したかを明確に評価することが重要です。
例えば、「売上目標の達成率」「プロジェクト完了の時間内達成率」など、具体的な数値を用いた指標を活用することで、評価に対する納得感を高めることができます。
評価制度を周知させる
仮に透明性と公正性を兼ね備えた評価制度が作られても、現場の従業員が知らなければ、絵に描いた餅になってしまい意味がありません。
評価制度が作られたら、従業員に説明して十分に理解してもらうことが必要です。効果的に評価制度を理解してもらうには、説明会やガイドライン等で従業員に説明するのが望ましいでしょう。新入社員や昇進した評価者向けに定期的な研修を実施することで、誤解やトラブルを防ぐことができます。
HRvisで実現する納得のいく人事評価をサポート
「公平な評価が重要と言われても、人が関わるからどうしても甘辛が生まれる……。」
「評価される従業員に気を使いすぎて、適切な評価ができていない……。」
ここまで記事を読んで、こんなお悩みをお持ちではありませんか?
そんな時は、人事評価システム「HRvis」を活用しましょう!
HRvisを活用することで、スキルマップを用いて従業員の能力を可視化し、納得できる人事評価を実現できます。スキルマップでは、過去のデータと比較しながら従業員の成長やパフォーマンスを数値化します。これによって、各従業員の強みや成長すべきポイントが明確になり、公平な評価が可能になります。これにより、従業員が納得しやすい評価制度になり、不満の発生を防ぐことができます
さらに、HRvisのAI評価機能を活用すれば、事実ベースの評価をサポートできるため、上司の評価の甘辛による不公平感をなくすことができます。AIが客観的なデータを基に評価のたたき台を作成することで、評価者ごとのバイアスを軽減し、従業員が納得できる評価を行うことができます。
HRvisを導入し、より透明性の高い人事評価制度を実現しませんか?
ロイヤル総合研究所 コンサルティング部
人事コンサルタント 飯塚友恵

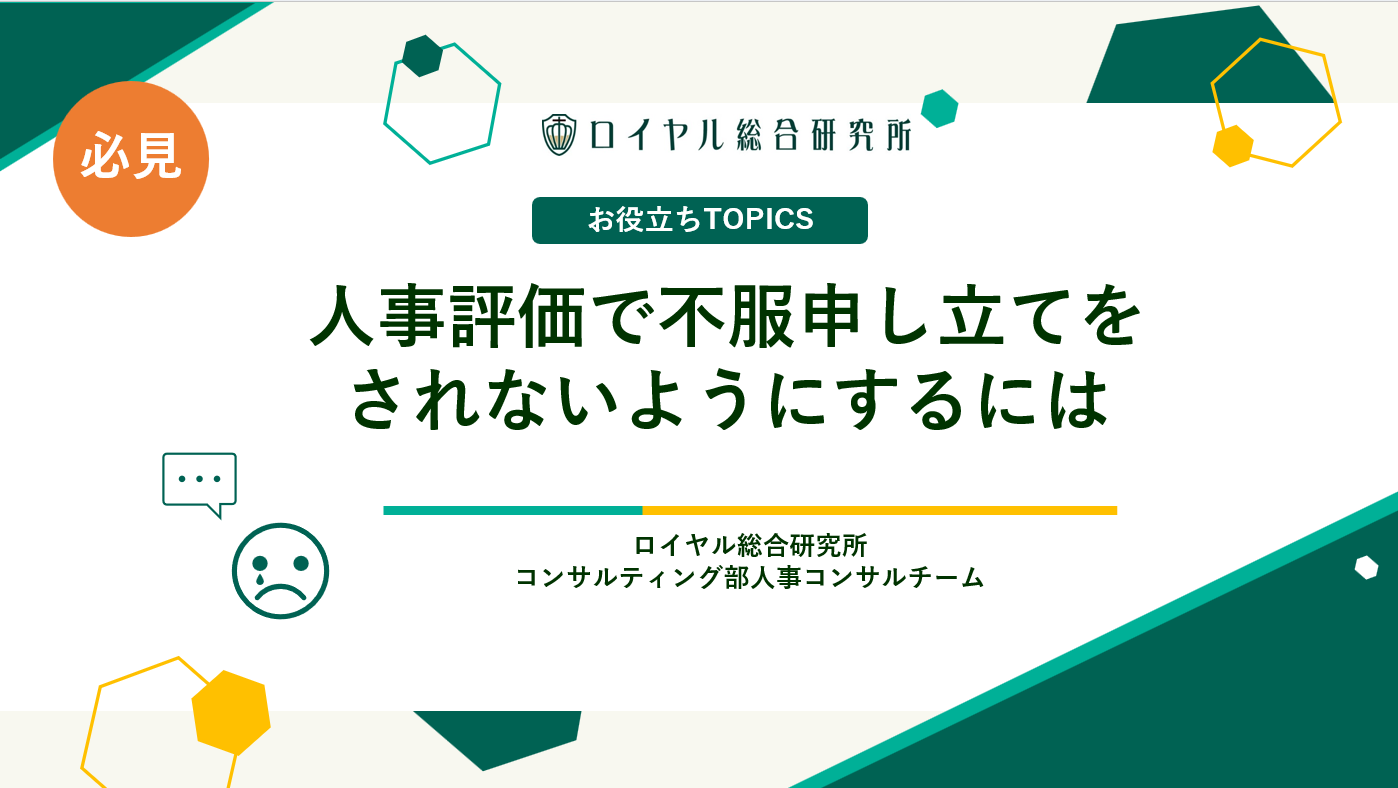
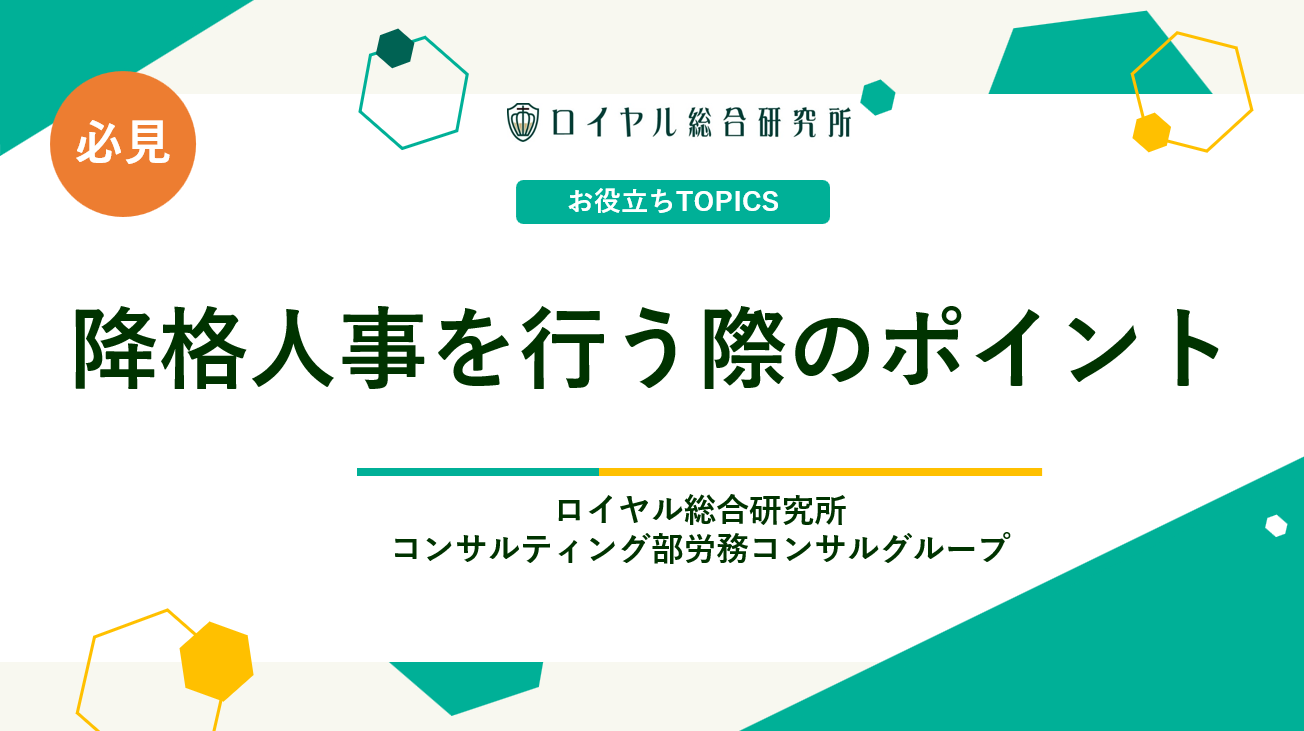
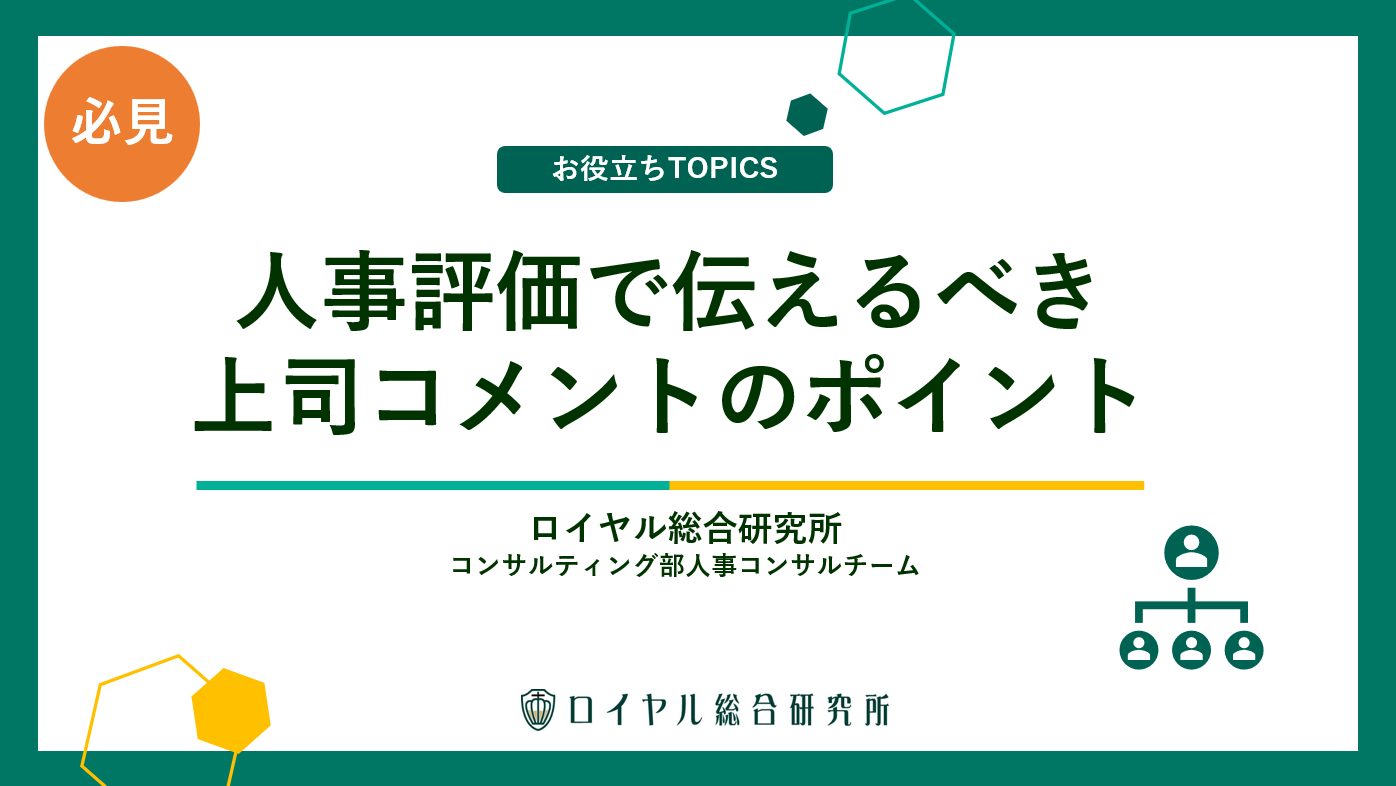
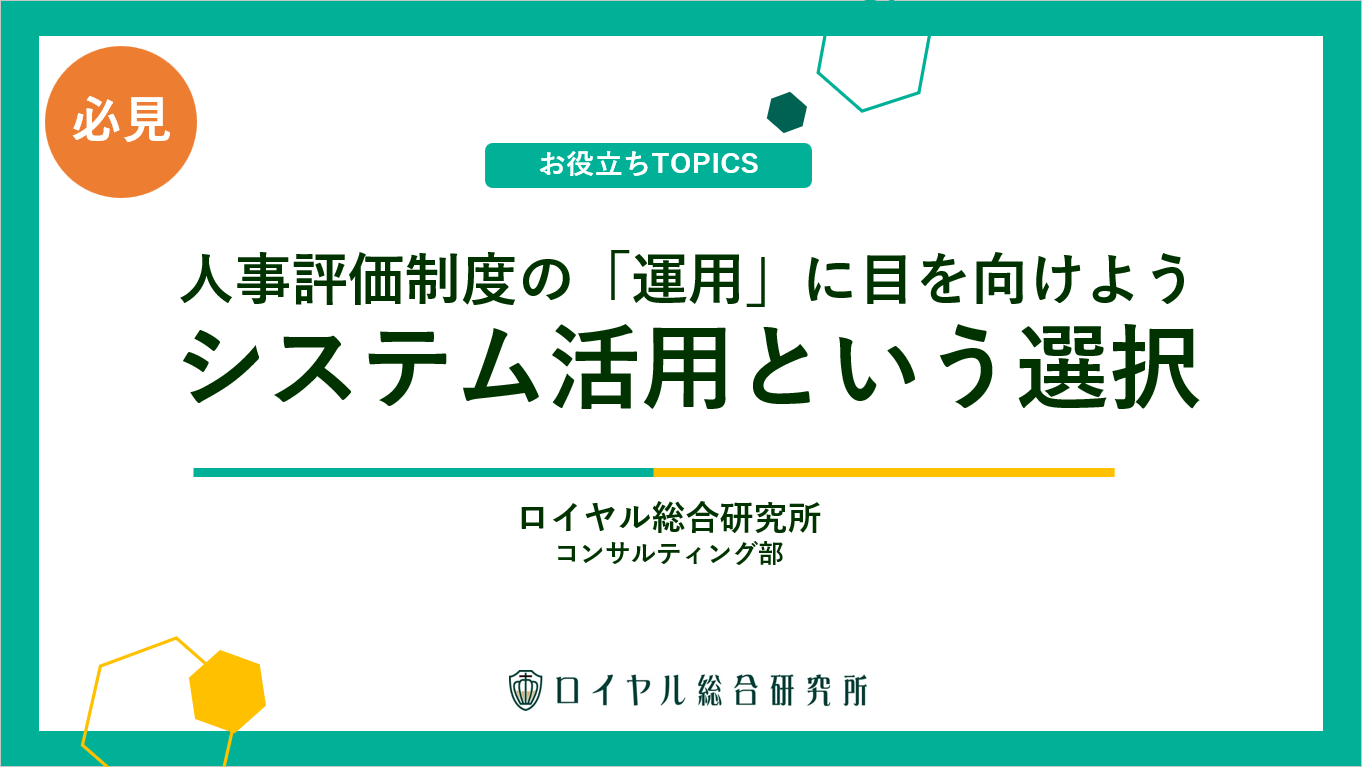
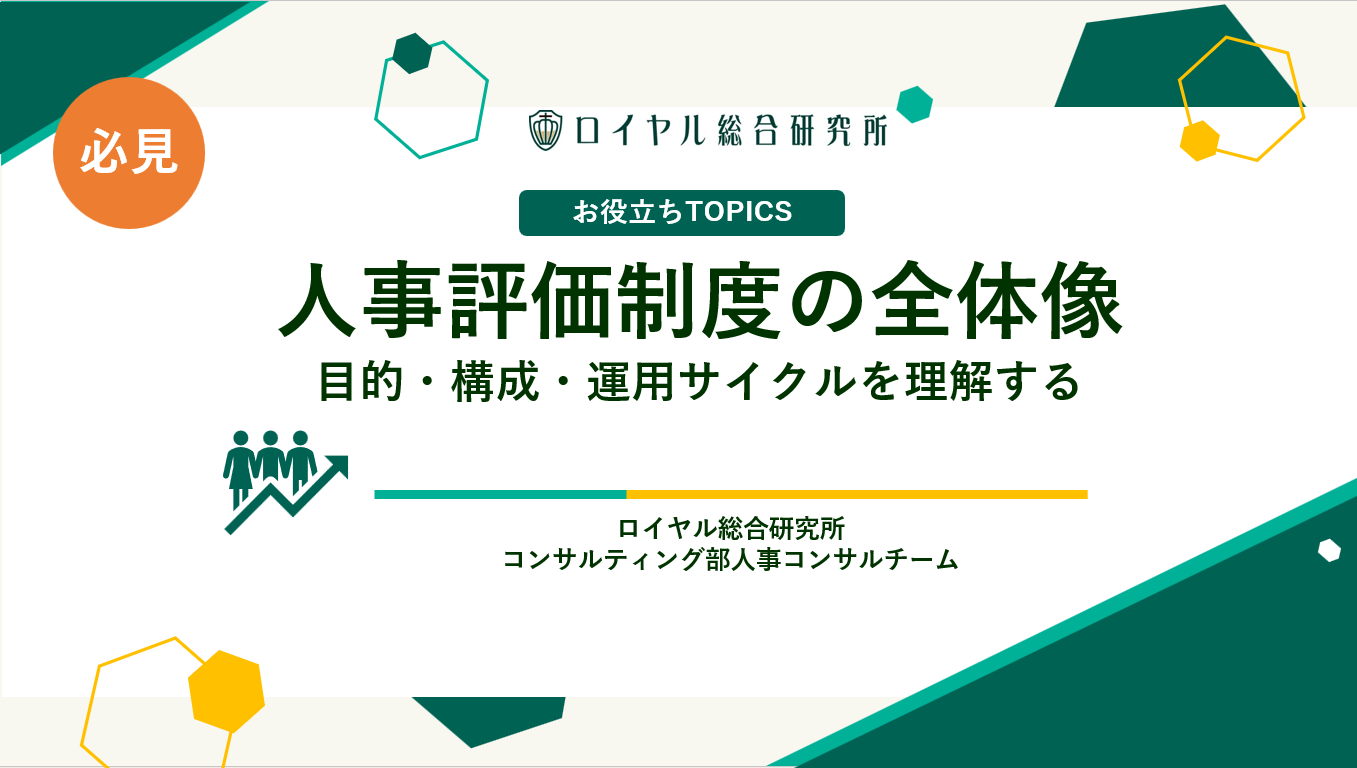
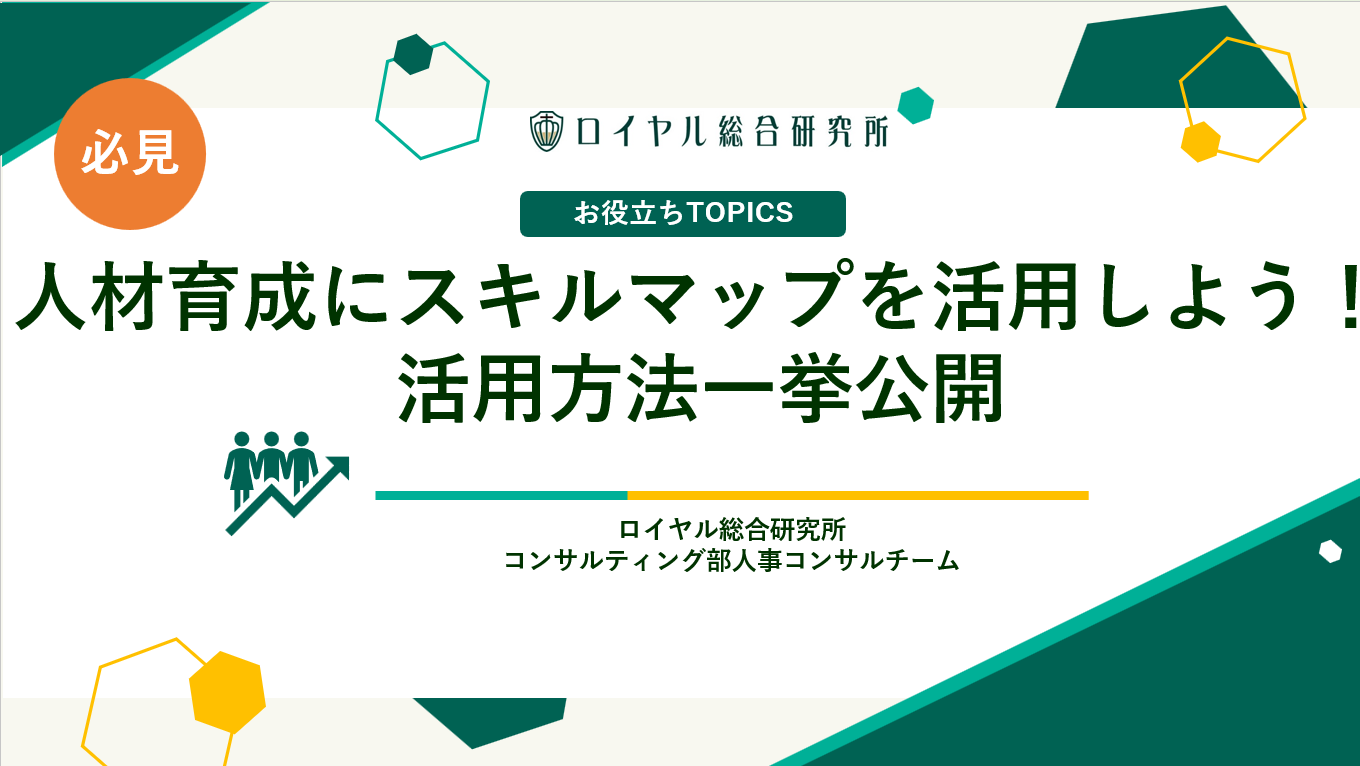
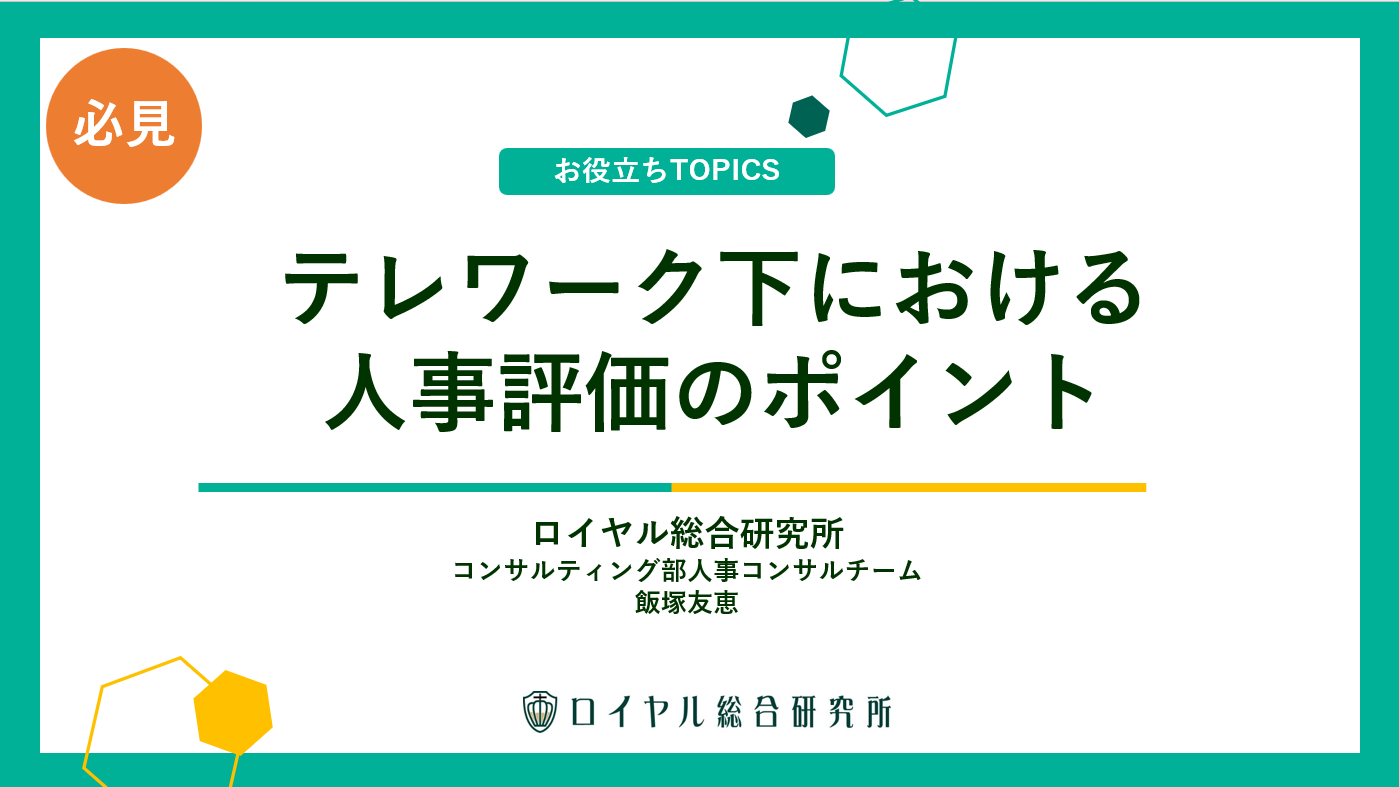
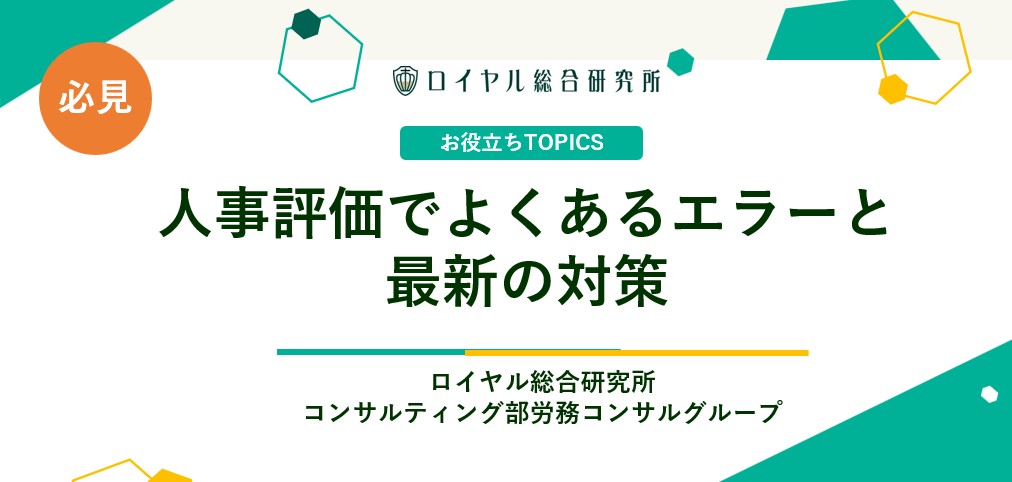
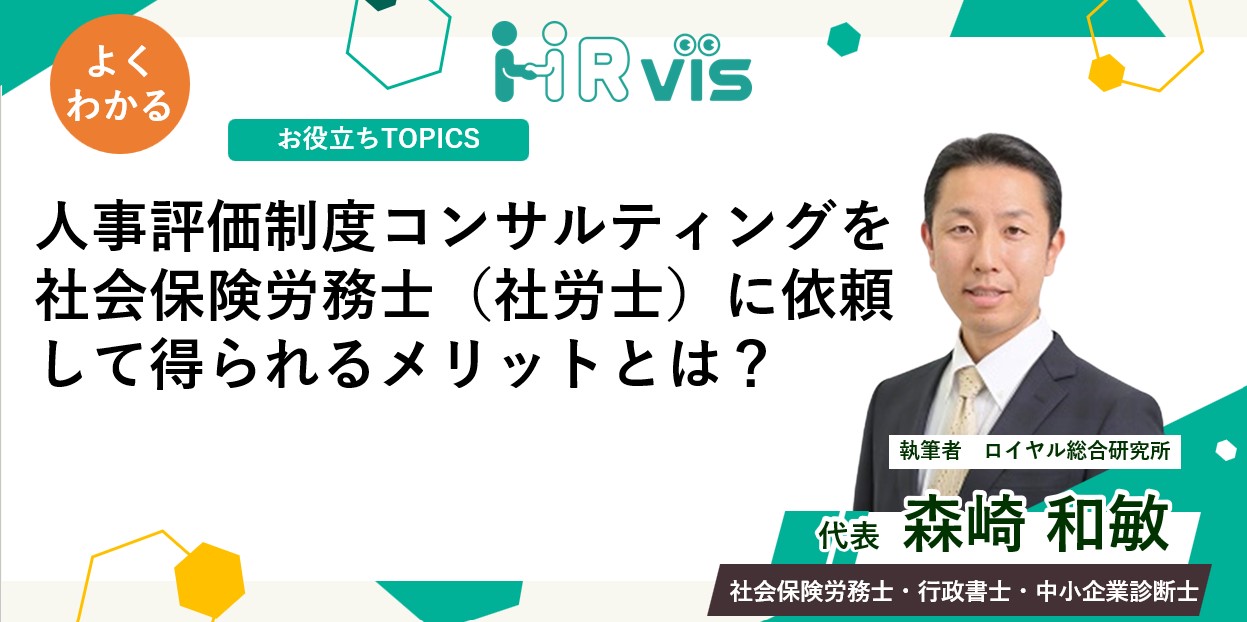
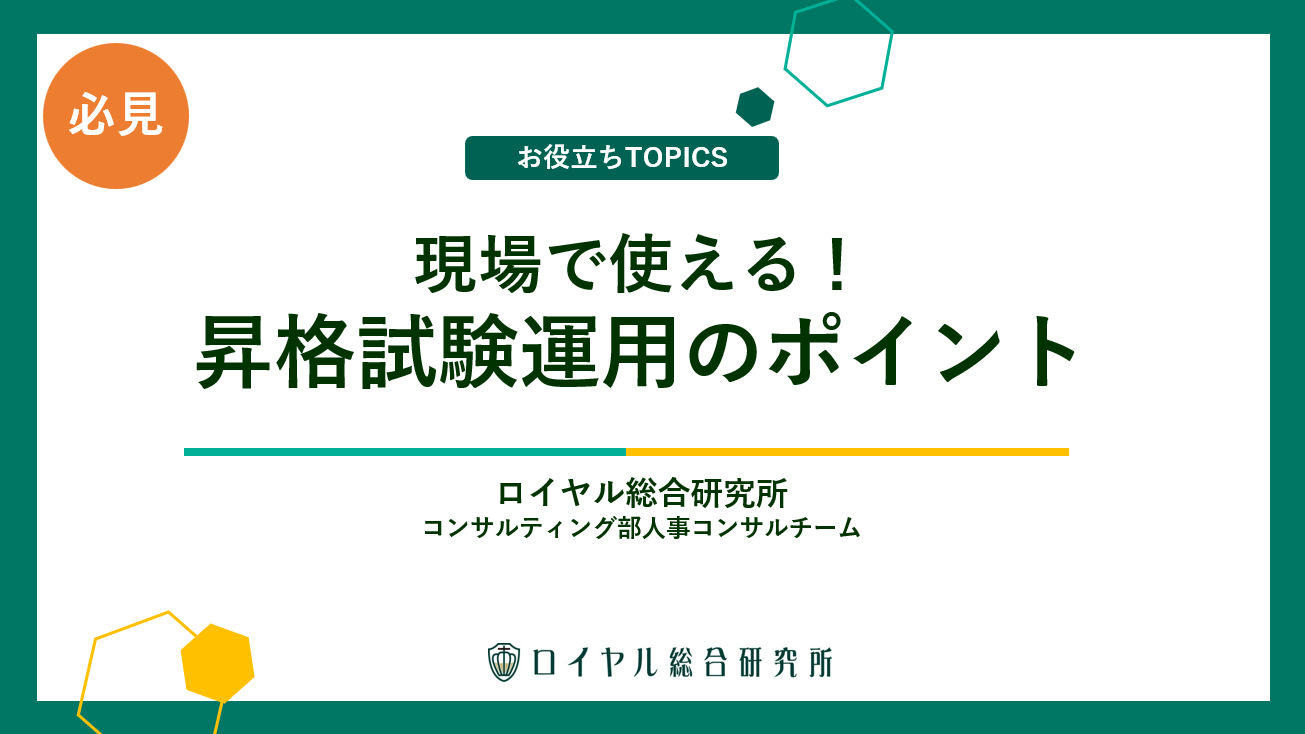
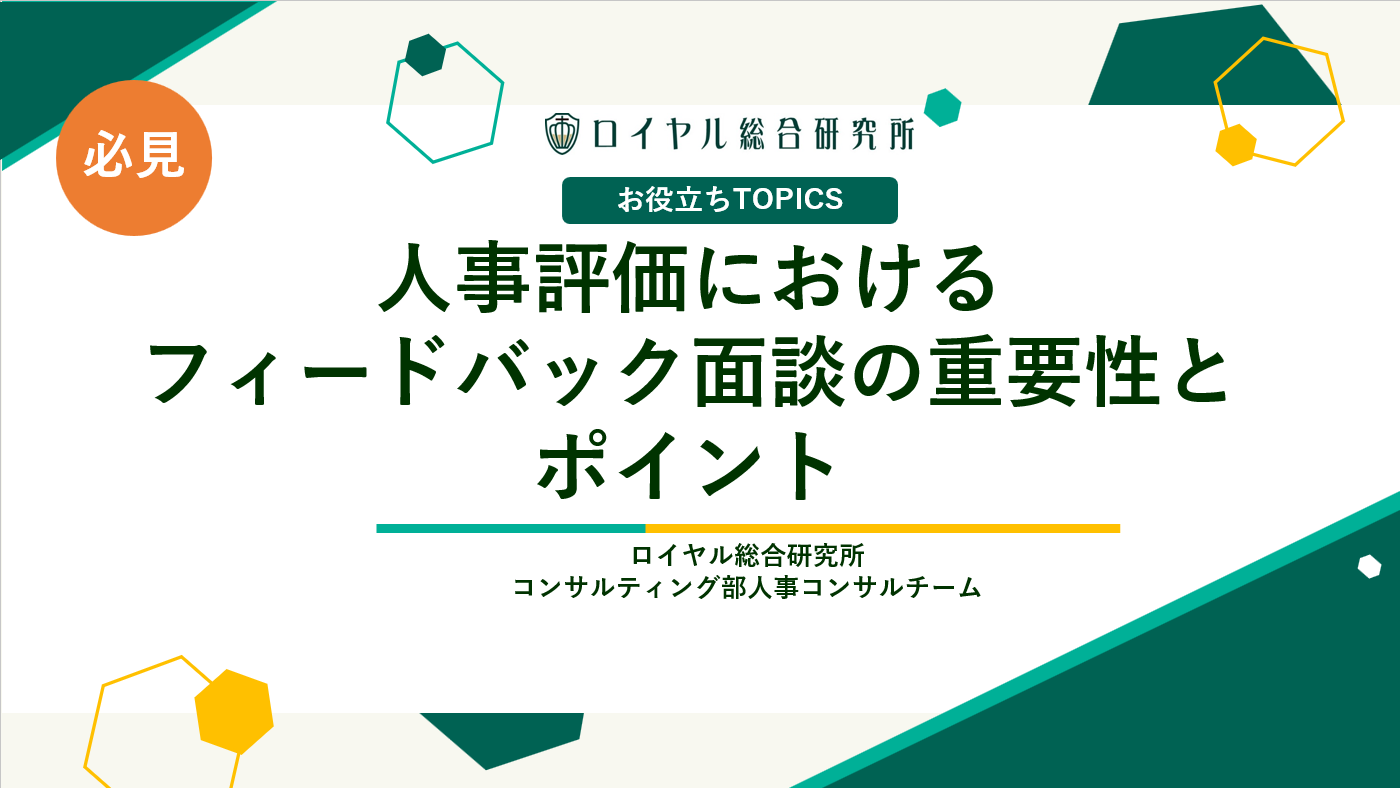



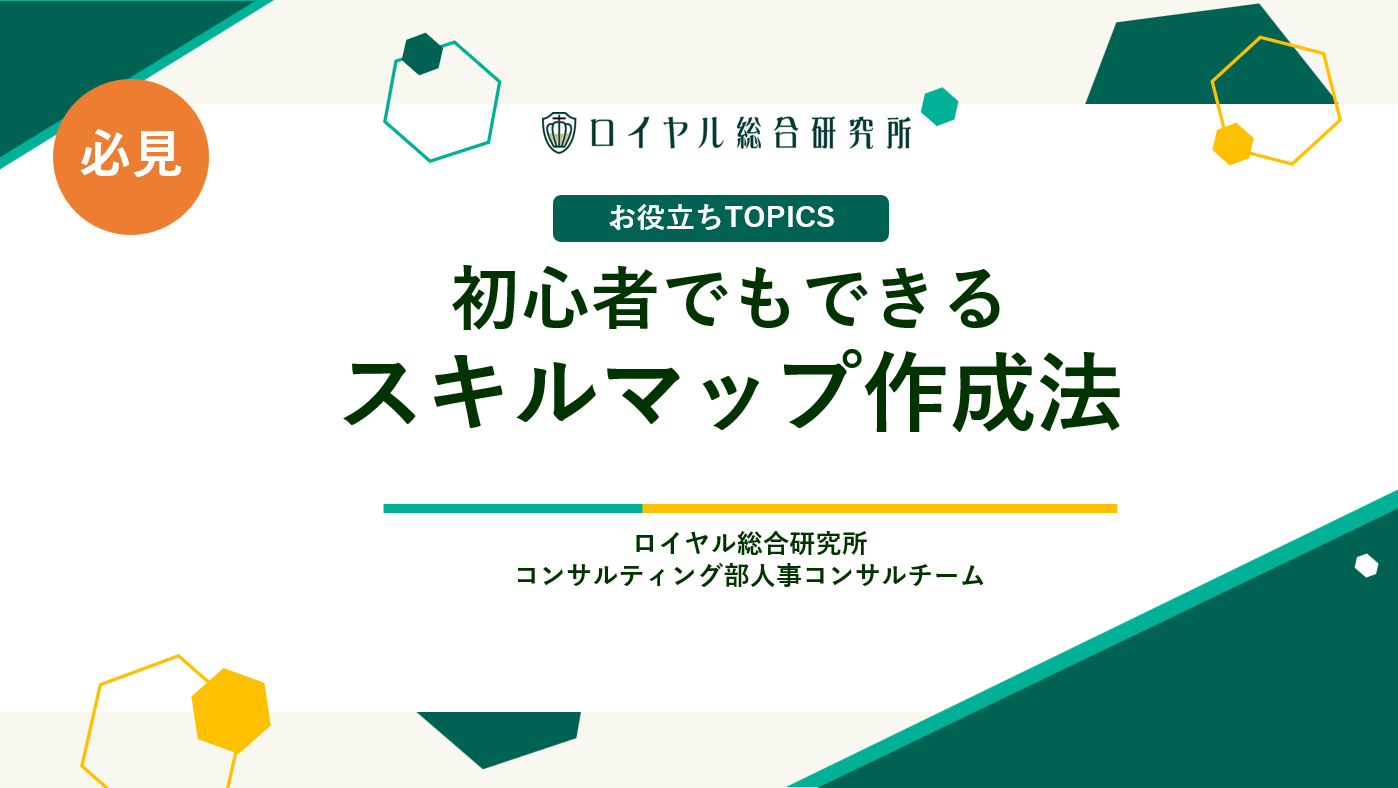
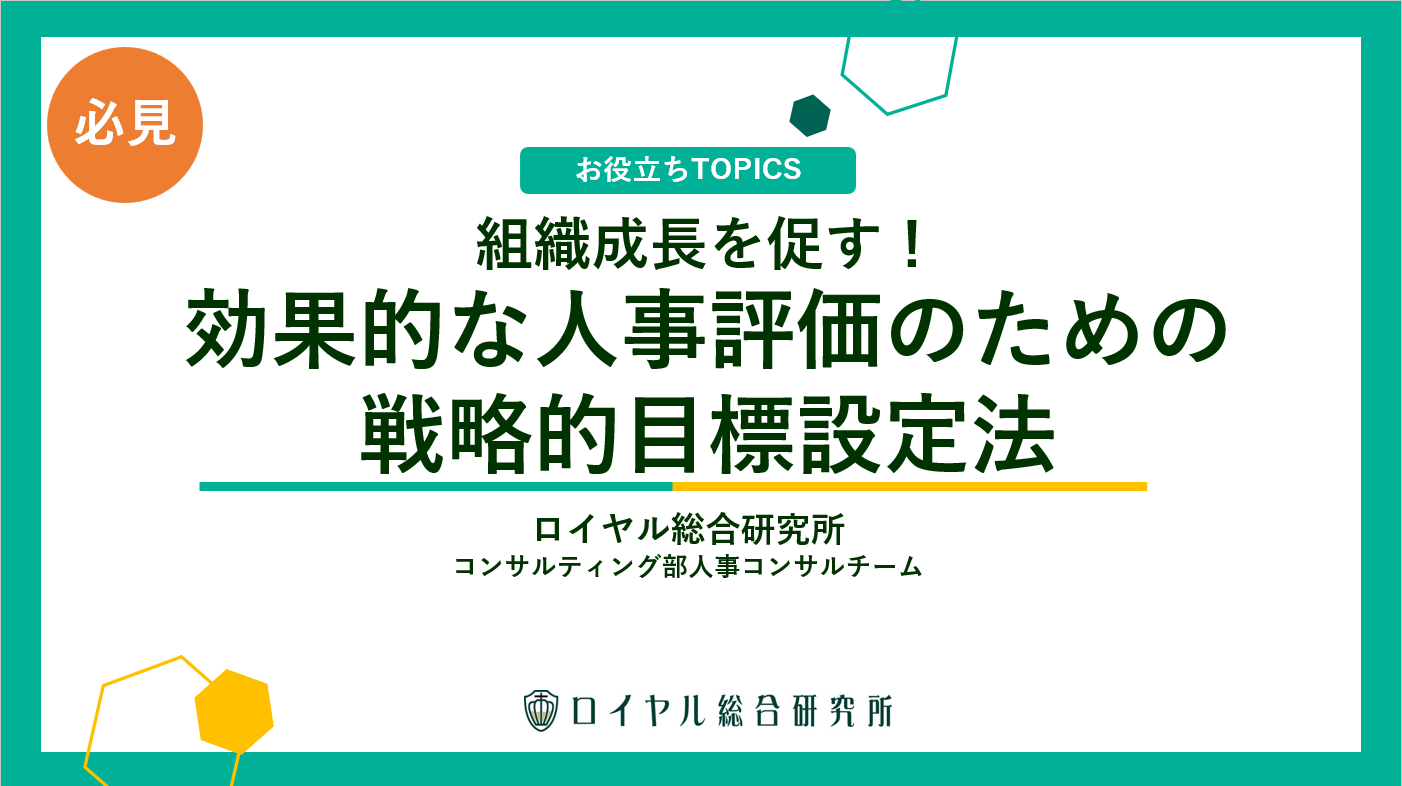
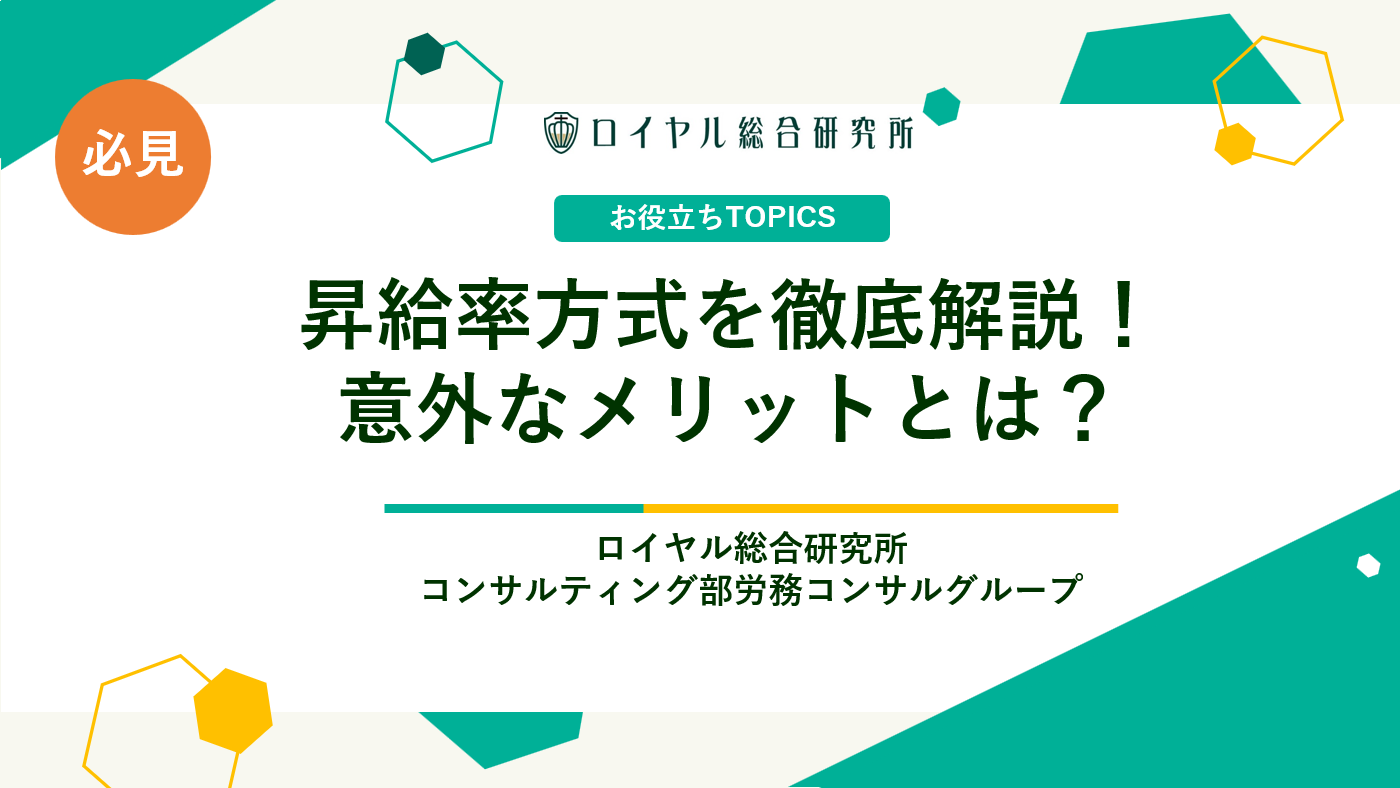


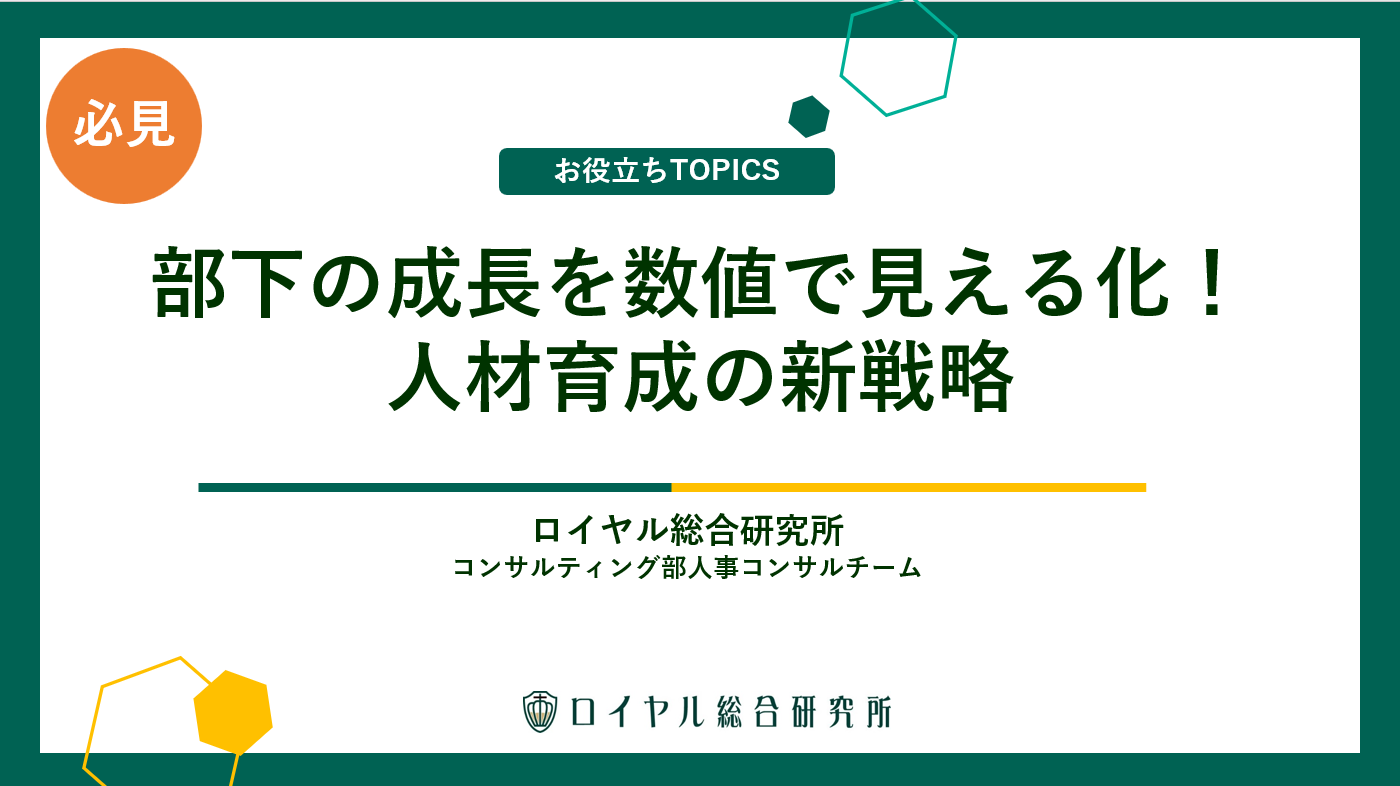
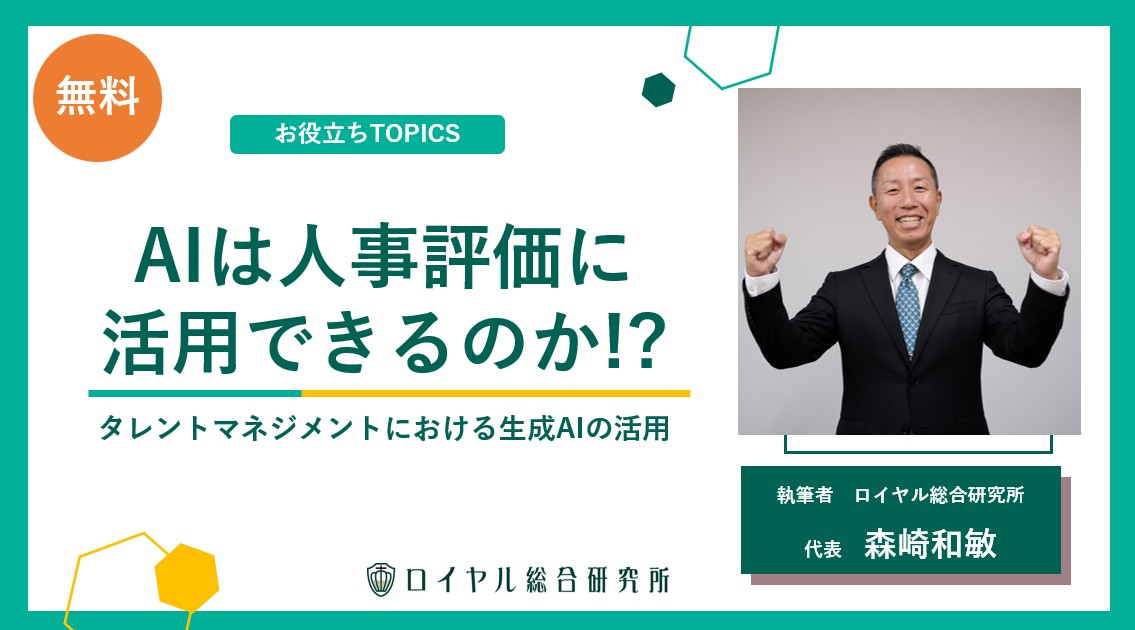

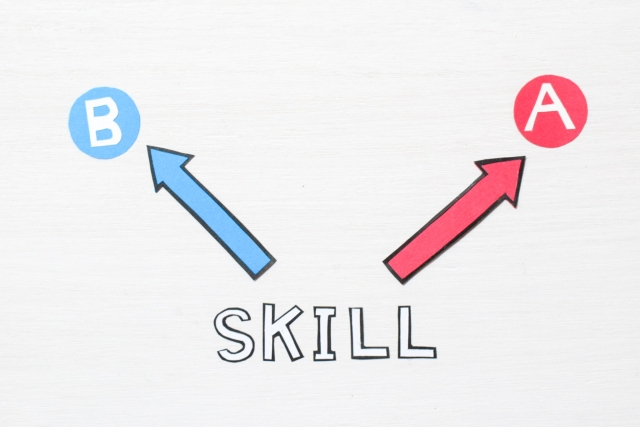


 ページトップに戻る
ページトップに戻る