目次
「一度決めた制度は変えてはいけない」は間違い
人事評価制度は、社員のやる気アップに効く仕組みですが、逆に、社員のやる気を低下させてしまう場合があります。注意が必要です。
やる気を低下させないための注意
事例でお話ししましょう。
H社で人事評価制度導入後、第1回目の評価を行なったときのできごとです。新しい人事評価制度ができて、若手中心のH社の社員は「将来の社内での目標や自分自身の成長ビジョンが持てる」と、意気揚々として評価に取り組んでくれました。
ところが、評価結果を集約してみると、非常に悪い。「SS・S・A・B・C・D・E」で分類すると、「SS」「S」「A」評価は存在せず、「B」評価の社員が約20%、「C」評価が約50%、「D」評価が約30%という結果になってしまいました。
しかし、制度のルールに基づいて導き出された評価結果なので、これを調整することはかえってよくないだろうと判断。そのまま本人に結果を伝えると、不満がいっきに噴出したのです。
「こんなに頑張っているのに会社は評価してくれない」
「モチベーションを上げるための人事評価制度のはずなのに、これでは、モチベーションが下がる一方だ」
「上司は減点方式の評価で、まったくよいところを見てくれない」等々⋯⋯⋯⋯。
結局、評価結果を一段階甘めにスライド(B評価の社員をA評価に、C評価の社員をB評価に)させ、なんとか反発を収拾できました。しかし、社員はこの評価を行なったことによって会社や人事評価制度に対して不信感を持ってしまい、その後の対応にもかなり苦慮しました。
このような反発が起こらないよう、事前に対処するためにはどうしたらよいのでしょうか?
ルールを破る
それは、制度のルールを破ればよいのです。どういうことかというと、社員に結果をそのままフィードバックすると不満が出るのがわかりきっているならば出ないように評価結果を調整すればよいのです。
H社の例で言うと、不満が出た後に行なった、評価の甘辛調整を面談前に実施しておくのです。
頭の固い総務系の担当者に任せていると、とんでもない事態を招くことになりかねせん。経営者の判断で、ルールに反してでも、臨機応変な対応を積極的行なわなければならないこともあるのです。
ルールを守ることと、社員のやる気、どちらを優先させますか?
「うまく運用できないから導入しないほうがよい」は間違い
こんなことをおっしゃる経営者もたまにいらっしゃいます。
「今回構築した人事評価制度は〇〇の部分がうまくいかないので、制度としてダメなんじゃないか、やはり導入はやめたほうがよいのではないか」
うまくいかなくて当たり前
しかし、一度評価制度や賃金制度を運用してみて、うまくいかない場合もご安心ください。「人事評価制度」はうまくいかない部分が出てきて当然なのです。
これまでの多くの書籍やコンサルタントは、こうやればうまくいく、こういう考え方で、この通りに運用しなければならない、公平な評価をするためにはここがポイントです、などと教え、ルール通りに運用することを強制します。
不具合の出ない人事評価制度はない
これまでは、誰も運用段階で不具合が出た場合、どのように対処したらよいのかを教えてきませんでした。しかし、現実には不具合は必ず出るので、その対処と仕組みの改善が必要です。これに対処できない中小企業が人事評価制度をうまく運用できていないのです。
まずは簡単に導入できる人事評価システムを取り入れてみましょう
「人事評価制度の必要性はわかっているが、0からシステムを構築するのは難しい」
「人事評価制度を作りたいが、何からやったらいいかわからない」
こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ「HRvis」の導入をご検討ください!
「HRvis」は、人事のプロである社会保険労務士と、システムのプロが共同開発した、クラウド型タレントマネジメント人事評価システムです。当社の人事制度コンサルティング実績に基づき、よく使われる人事制度が初期設定されているため、すぐに使用できます。
また、評価シートに入力する項目や目標をテンプレート化できるため、毎回同じ項目を入力する必要はありません。人事制度のマスタで制度をアレンジすることも簡単にできます。
人材評価の方法についてお悩みの方は、ぜひHRvis の導入をご検討ください!
ロイヤル総合研究所
人事コンサルティングチーム




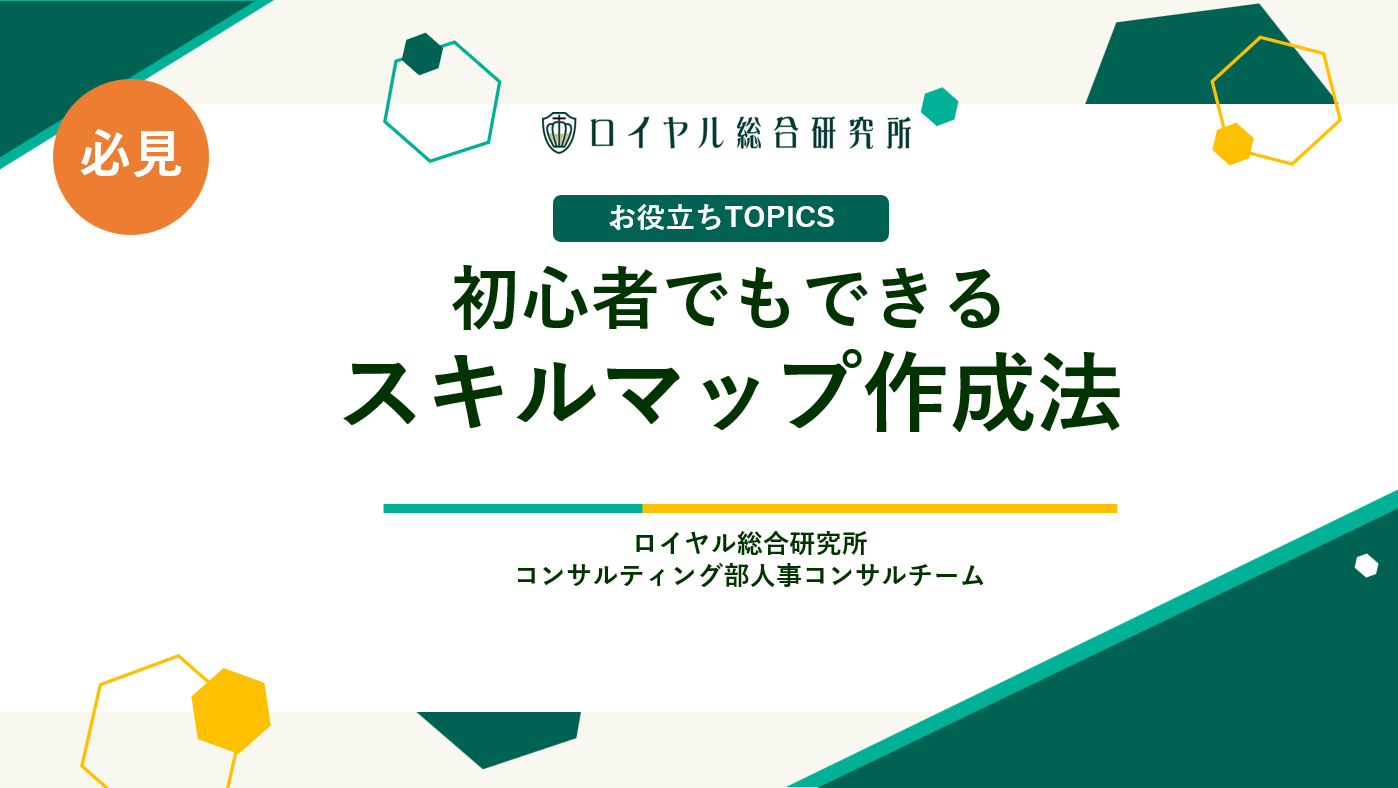
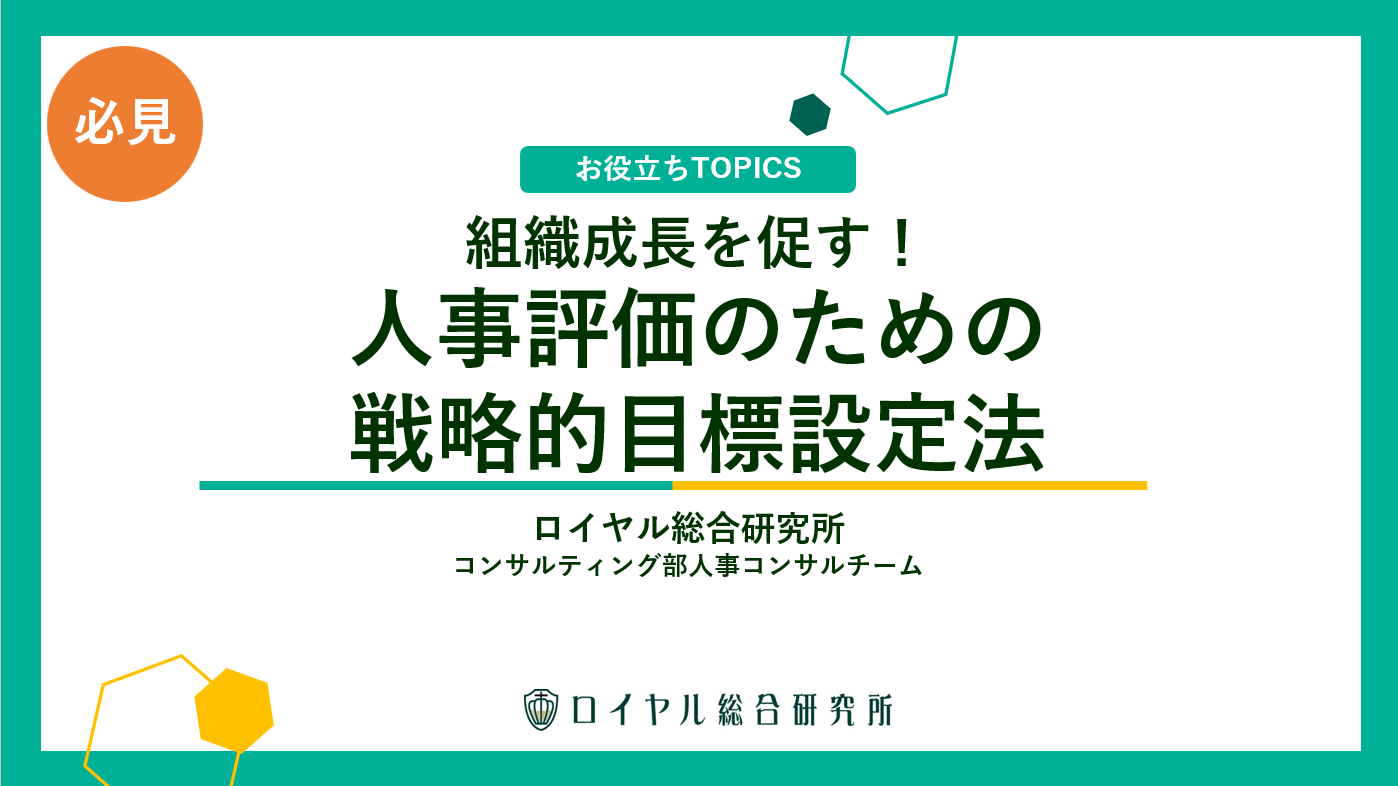
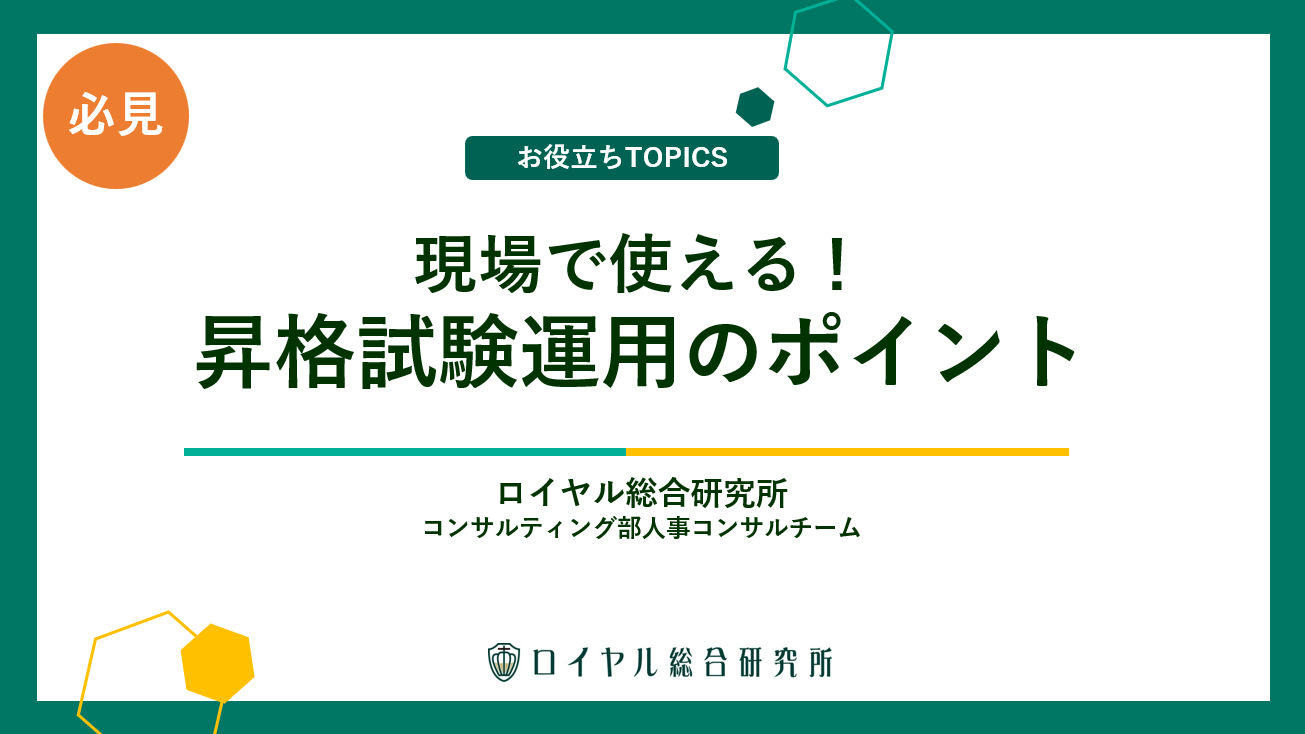
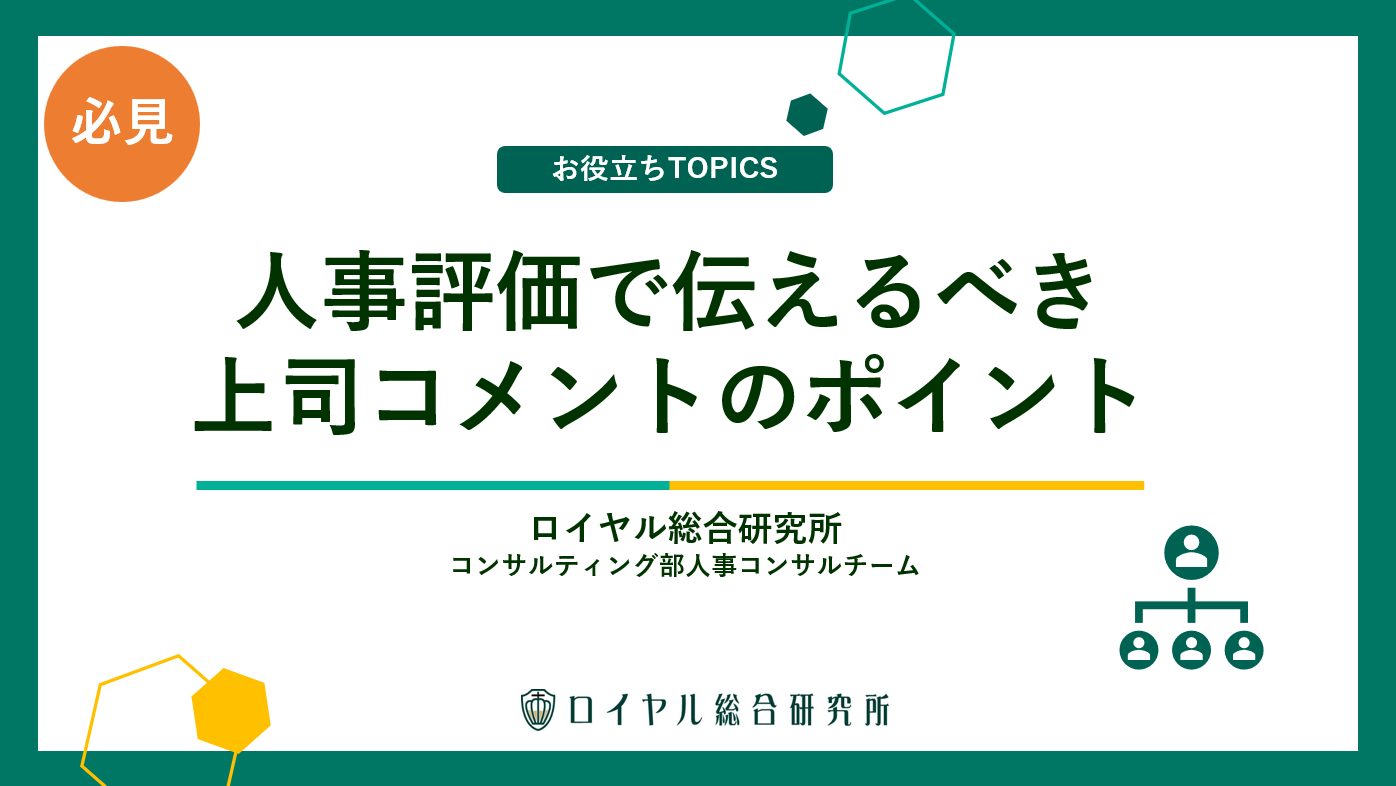
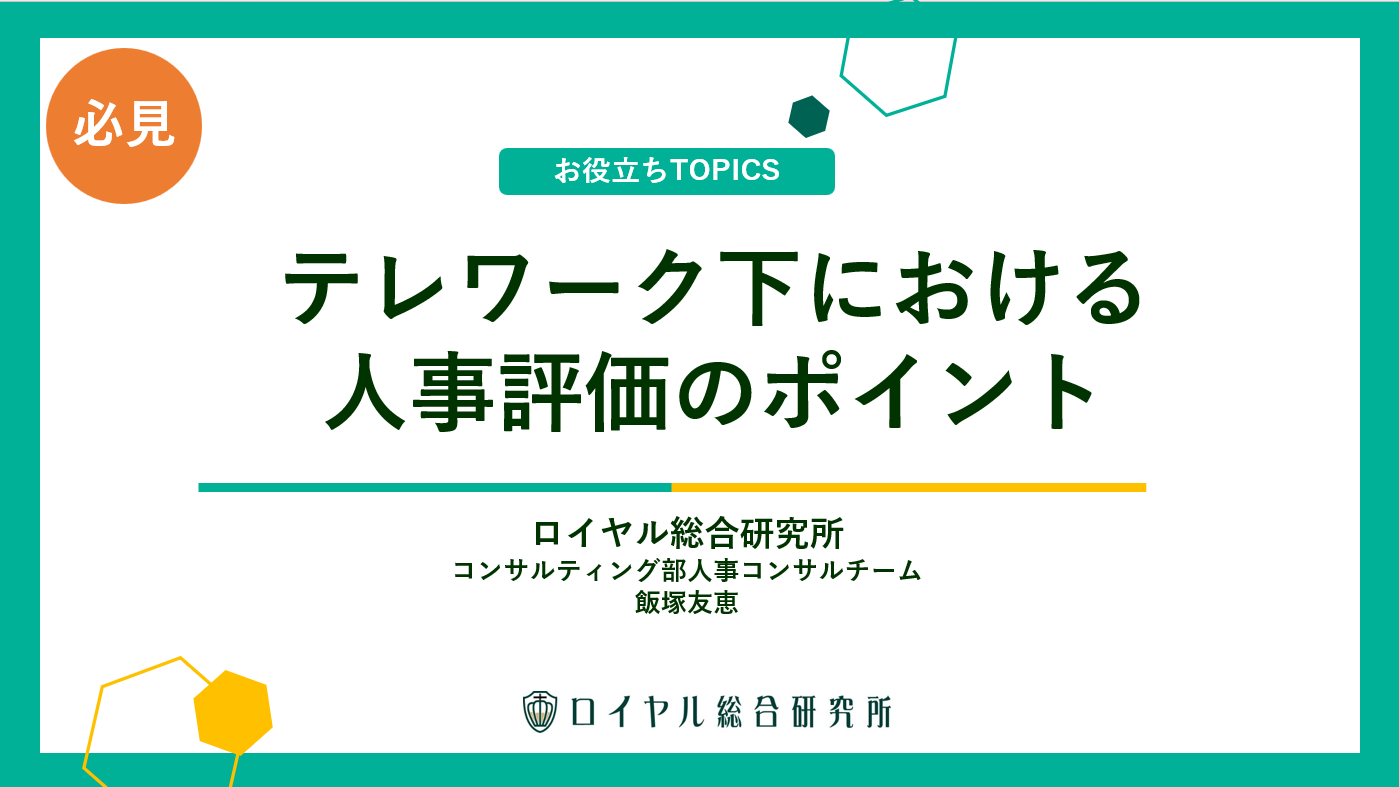
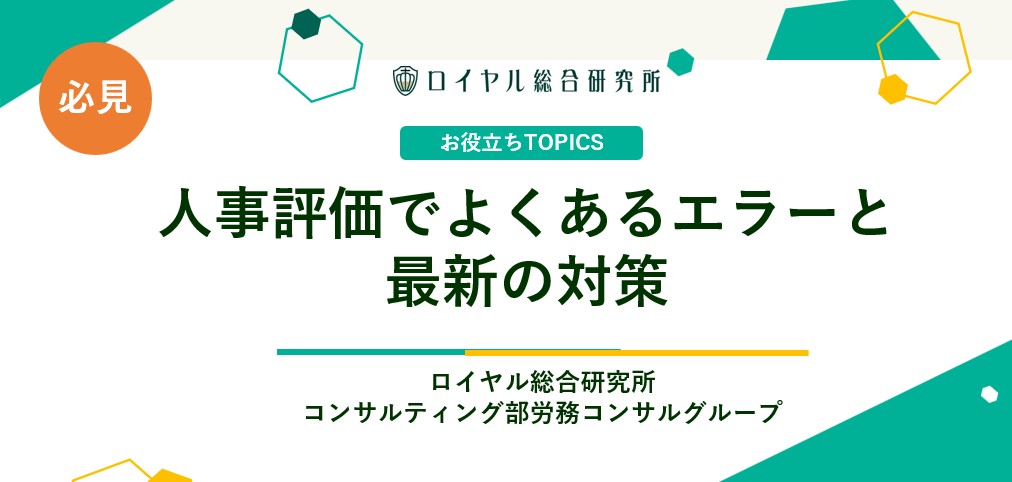
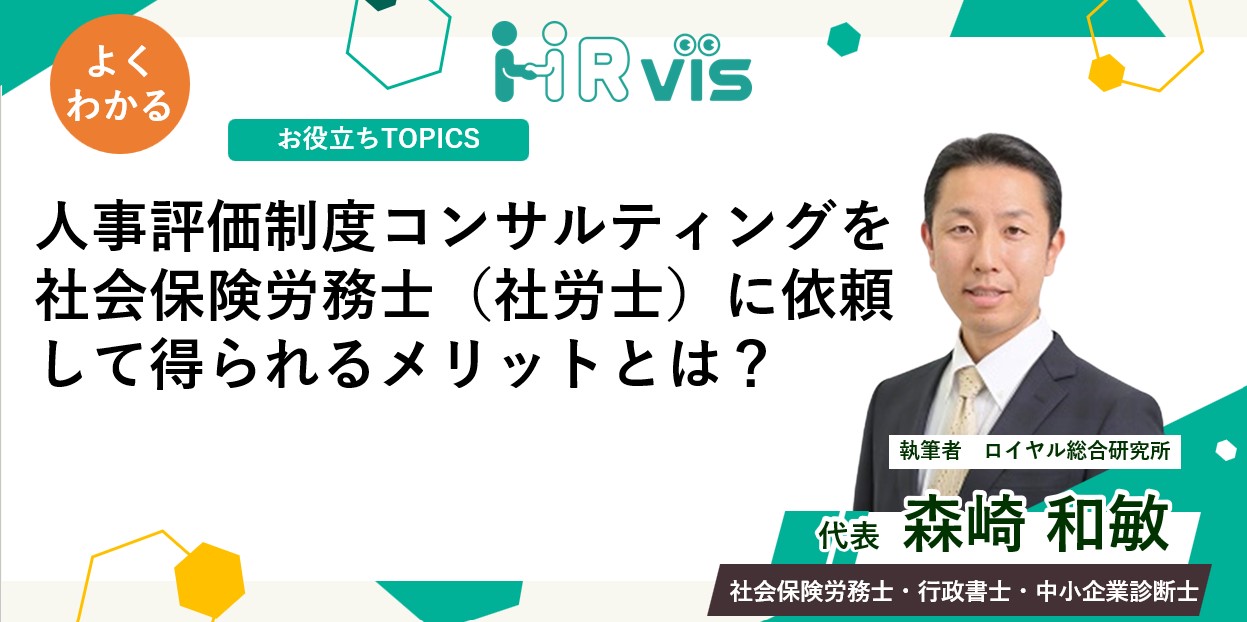
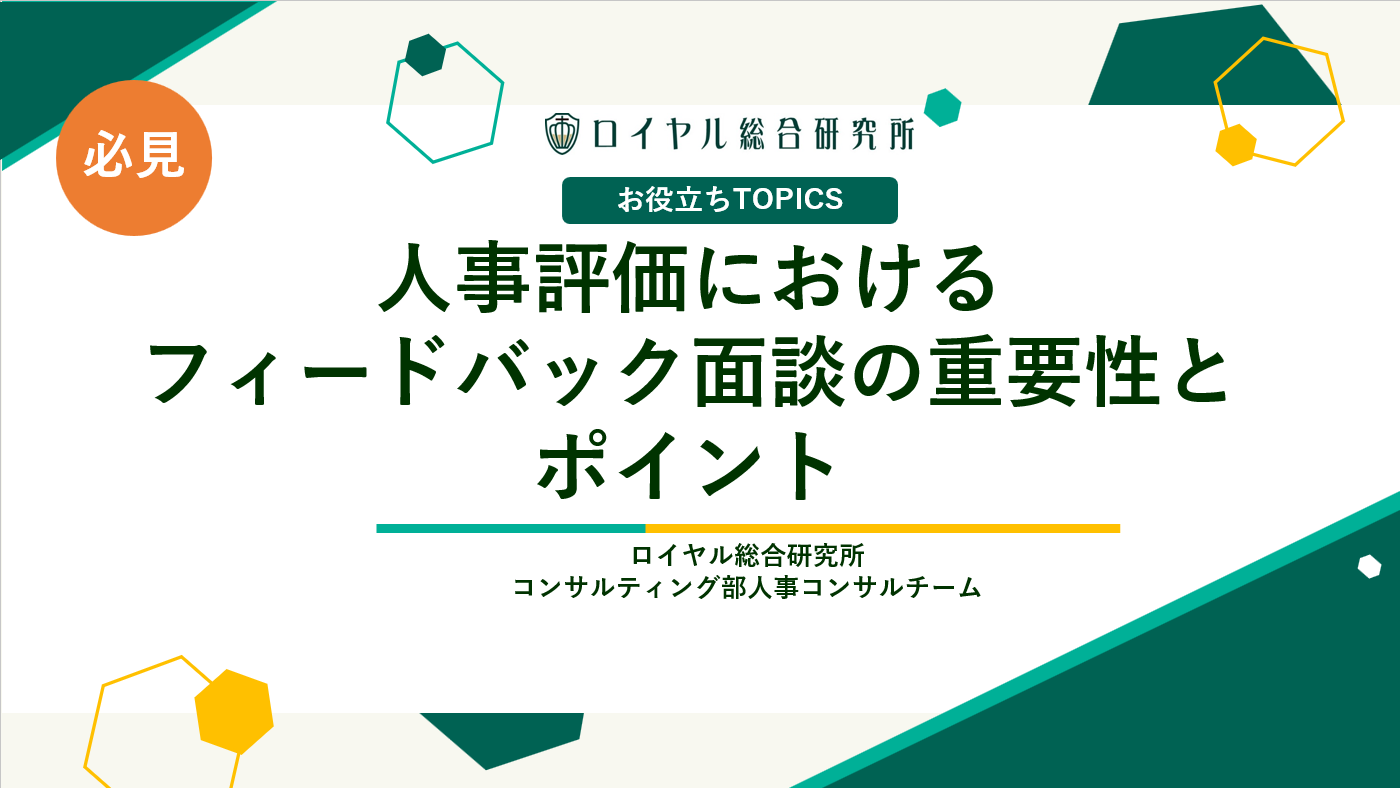





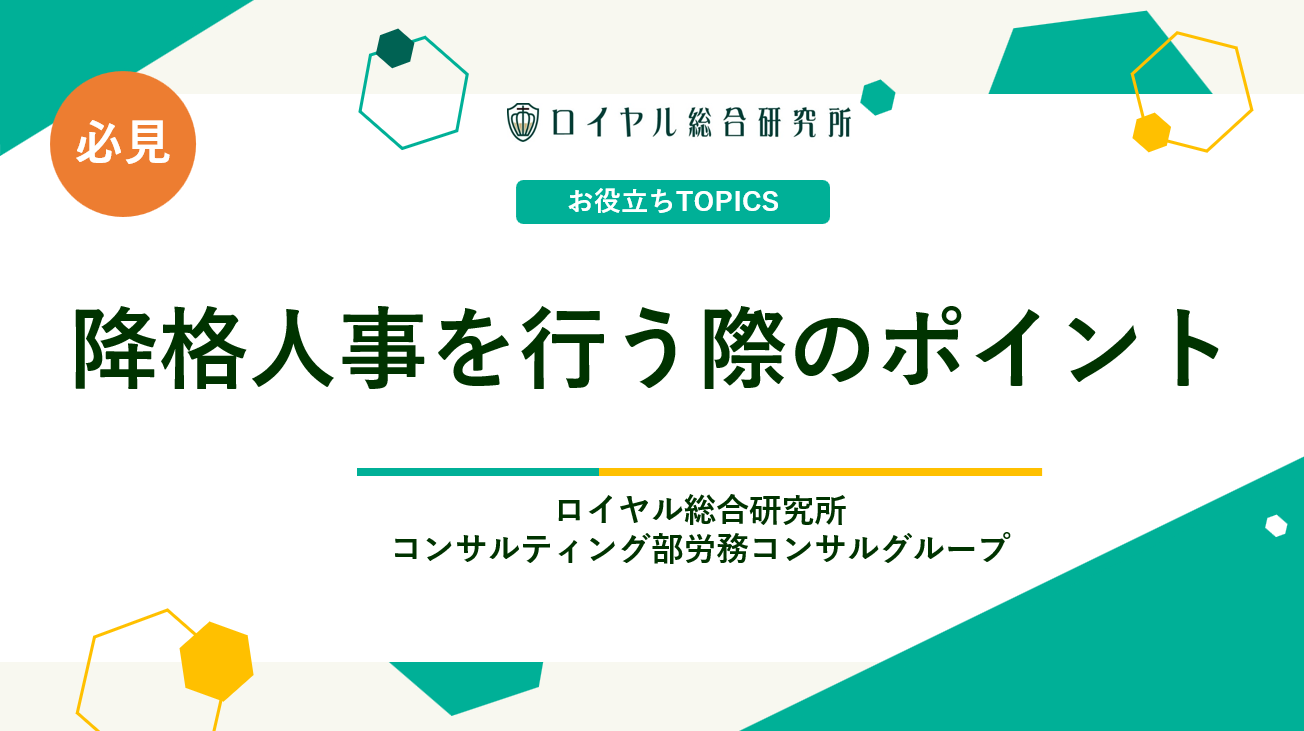
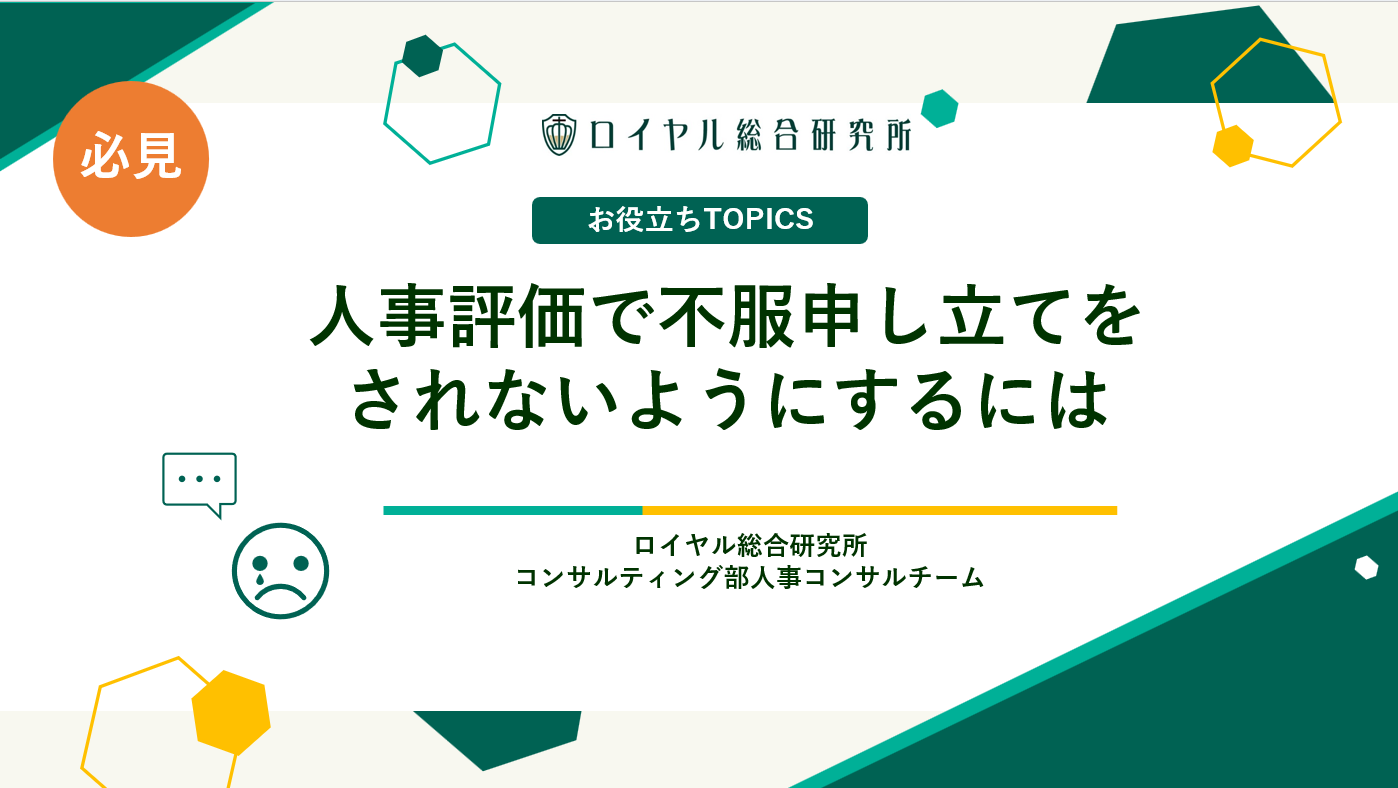
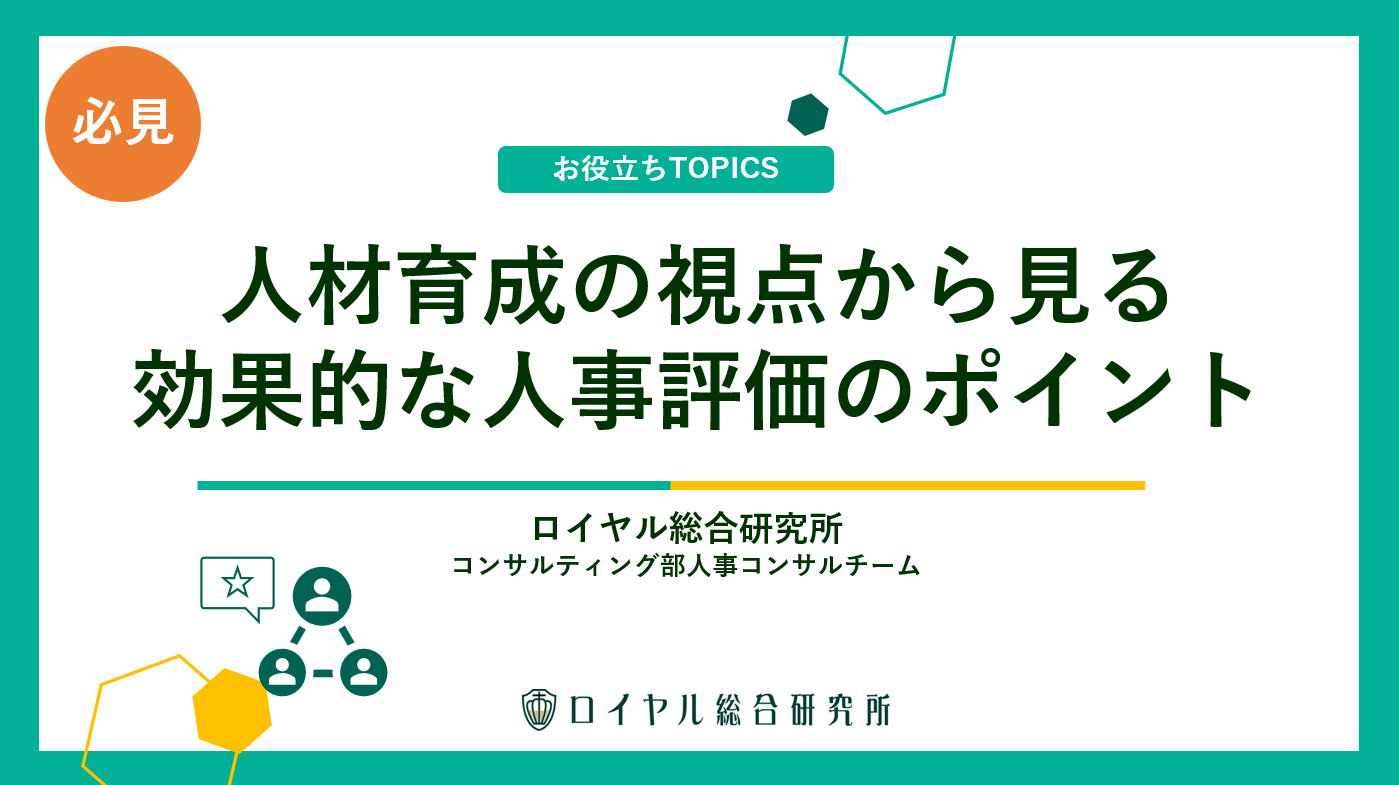
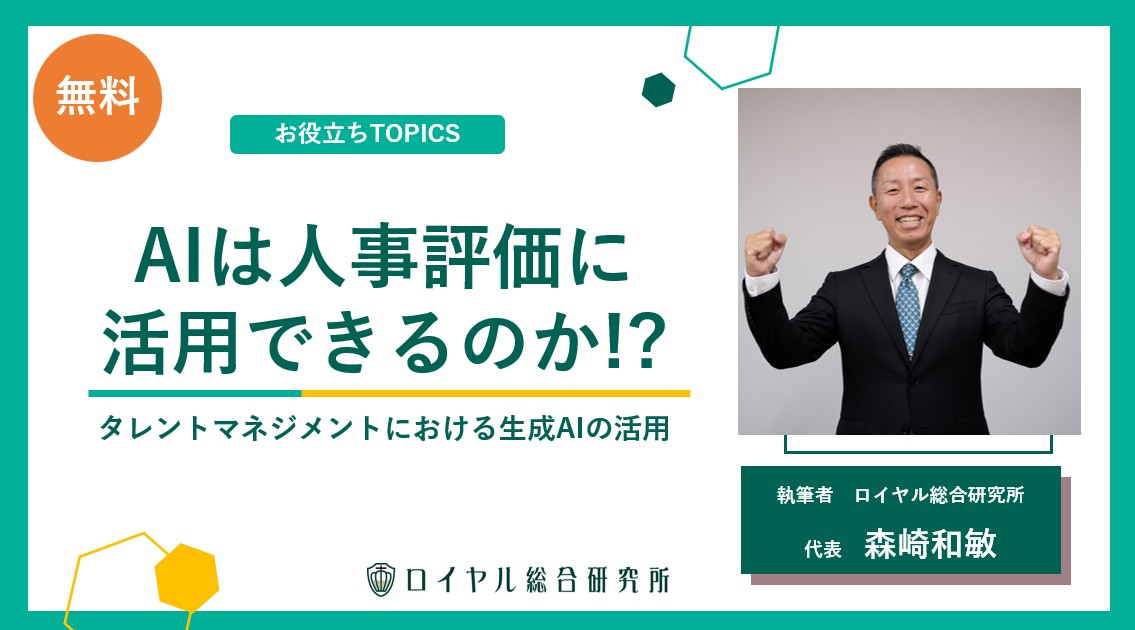

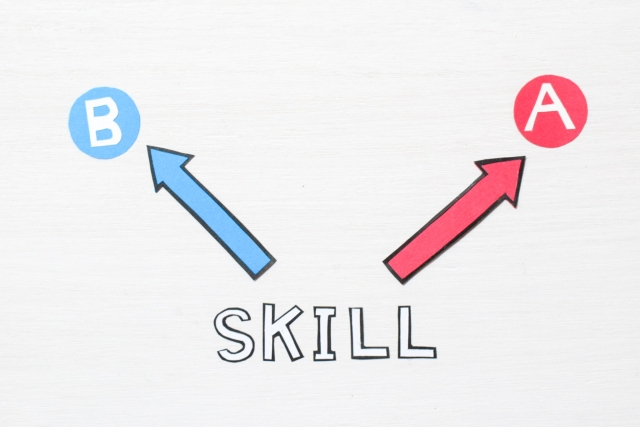
 ページトップに戻る
ページトップに戻る