「人事評価って、結局は上司の主観だよね…」
そんな風に感じたことはありませんか? 多くの企業で、人事評価の不透明感が社員のモチベーション低下や不満の温床になっています。
しかし、AI(人工知能)の進化は、この課題に光を当てています。この記事では、AIが人事評価をどう変えるのか、その具体的な活用方法と、公正で透明性の高い評価制度を構築するためのポイントについて解説します。
目次
人事評価システムへのAI活用
近年の人事評価システムへのAI活用事例
近年の人事評価システムでは、AIが単なるデータ管理ツールを超え、評価そのものの中核を担うようになっています。
例えば、社員が設定した目標と自己評価、そして上司の確認結果に基づいて、AIが一次評価のたたき台を生成するシステムが実用化されています。
これは、評価のスタート地点から公正性を確保する画期的なアプローチです。
さらに、評価コメントの自動生成機能もその一つです。
これにより、評価者である上司は、コメント作成にかかる時間を大幅に削減できるだけでなく、誰が評価してもばらつきのない、一貫した基準に基づいた評価コメントを作成できるようになります。
テクノロジーと人事評価業務の合わせ技
人事評価は、個人の成長を促し、組織全体のパフォーマンスを向上させるために必要不可欠なものです。
しかし、これまでの人事評価は、評価者の主観や経験に大きく左右されがちでした。
ここでAIが持つ強みは、膨大なデータを客観的に分析し、一定の基準に基づいた評価を導き出す能力です。
テクノロジーと人事評価業務を組み合わせることで、私たちは「人間にしかできない業務」に集中できます。
例えば、AIが評価のたたき台を生成することで、評価者は「この評価は本当に適切か?」「この社員の今後の成長には何が必要か?」といった、より本質的な議論に時間を費やすことができるようになります。
AIに期待される役割
人事評価において、AIは以下のような役割を担うことができます。
- 目標設定の支援: 前提条件(例えば、部署の役割、個人のスキル、過去の実績など)を正確に入力すれば、AIが実現可能で、精度の高い目標のたたき台を提案します。上司は、その内容を調整・承認するだけで目標設定を短時間で完了できます。
- 評価の標準化: 上司の主観や評価の“甘辛”を排除し、公正な評価を行う。
- 効率化: 評価コメントの自動生成やデータ分析により、評価にかかる時間を大幅に短縮し、評価者がより多くの時間を社員とのコミュニケーションに使えるようにします。
このように、AIを活用することで、人事担当者や評価者の業務負担は大幅に軽減され、よりコア業務に注力できるようになります。
AI導入のメリット
AIを人事評価に導入することによって、企業はどのようなメリットを享受できるのでしょうか。その鍵は「透明性」と「公正性」にあります。
人事評価の透明性向上
AIが人事評価のたたき台を生成するプロセスは、評価の基準を明確にします。
AIはシステム内のデータにに基づいて評価のたたき台を生成します。そのため、社員の 「なぜこの評価になったのか?」という疑問に対して、システム内のデータを明確な根拠として示すことができます。社員が評価結果に納得しやすく、かつ評価される過程全体が見える化されます。
また、評価コメントの自動生成機能も透明性向上に貢献します。 統一されたフォーマットと基準でコメントが生成されるため、社員は自分の評価が他の社員と比べて不当なものではないと考えることができます。
AIによる公正性の実現
AIは、特定の個人に対する偏見や先入観を持つことはありません。
データだけを基に評価を行うため、上司の主観による評価のばらつきを解消し、公正な評価を行えます。
また、「評価のルール」をAIに命令すれば、その評価のルールに基づいて評価のたたき台を生成できます。
例えば、「A評価は上位10%」「S評価のコメントは最低50文字以上」といったルールを命令することで、評価者が迷うことなく、公平な評価基準に則った評価を機械的に行えます。
しかし、AIが生成した評価が最終的な答えではありません。
AIには、もっともらしいけれど事実ではない情報を出力してしまう「ハルシネーション」というトラブルが起きてしまうリスクがあります。
AIが出力するものは、あくまでもたたき台です。最終的な評価は上司が追認することで初めて確定します。
AIの持つ客観性と人間の判断を組み合わせることで、質の高い評価を実現させることができます。
人事評価でのAI活用がもたらす今後の展望
人事評価におけるAIの活用は、単なる業務効率化に留まらない、組織全体の大きな変革に繋がります。
業務効率化がもたらす組織の成長
AIが人事評価の事務作業を肩代わりすることで、人事担当者は社員一人ひとりのキャリアプランの相談に乗ったり、より戦略的な人材配置を検討したりといった、「人にしかできない、創造的な業務」に時間を割くことができます。
これにより、社員のやる気が向上し、離職率の低下や生産性の向上といった、組織全体の成長に繋がる好循環を生み出します。
人事部門の新たな役割:AIとの共存
AIの導入は、人事部門の役割を根本的に変えつつあります。 これまでの「事務作業」中心の業務から、AIが提供するデータを活用した「戦略策定」へとシフトしていくでしょう。
AIはあくまでもツールであり、最終的な判断を下すのは人間です。 人事部門は、AIが提供するデータを読み解き、適切な評価基準を設定し、そして最終的には、社員の成長を後押しするための「信頼されるパートナー」としての役割を担っていくことが求められます。
人事評価制度とAIとの共存は、より公正で、より人間味のある組織づくりへとつながるのです。
AIで変わる人事評価、HRvisがその先導役
人事評価の“見える化”は、社員の納得感とやる気を引き出す鍵です。
AIの活用により、評価のばらつきや主観的な判断を排除し、誰もが同じ基準で評価される環境が整います。
これにより、社員は「公平に見てもらえている」と実感し、やる気の向上につながります。
HRvisでは、企業情報や社員のスキル・実績をもとに、AIが一人ひとりに最適な目標を提案します。
また、目標設定後は自己評価と上司の追認を踏まえ、一次評価と評価コメントのたたき台を自動生成します。
これにより、評価者は本質的な判断やコミュニケーションに集中でき、業務の効率化と評価の質向上を両立させられます。
HRvisは、AIと人の力を融合させた、次世代の人事評価システムです。



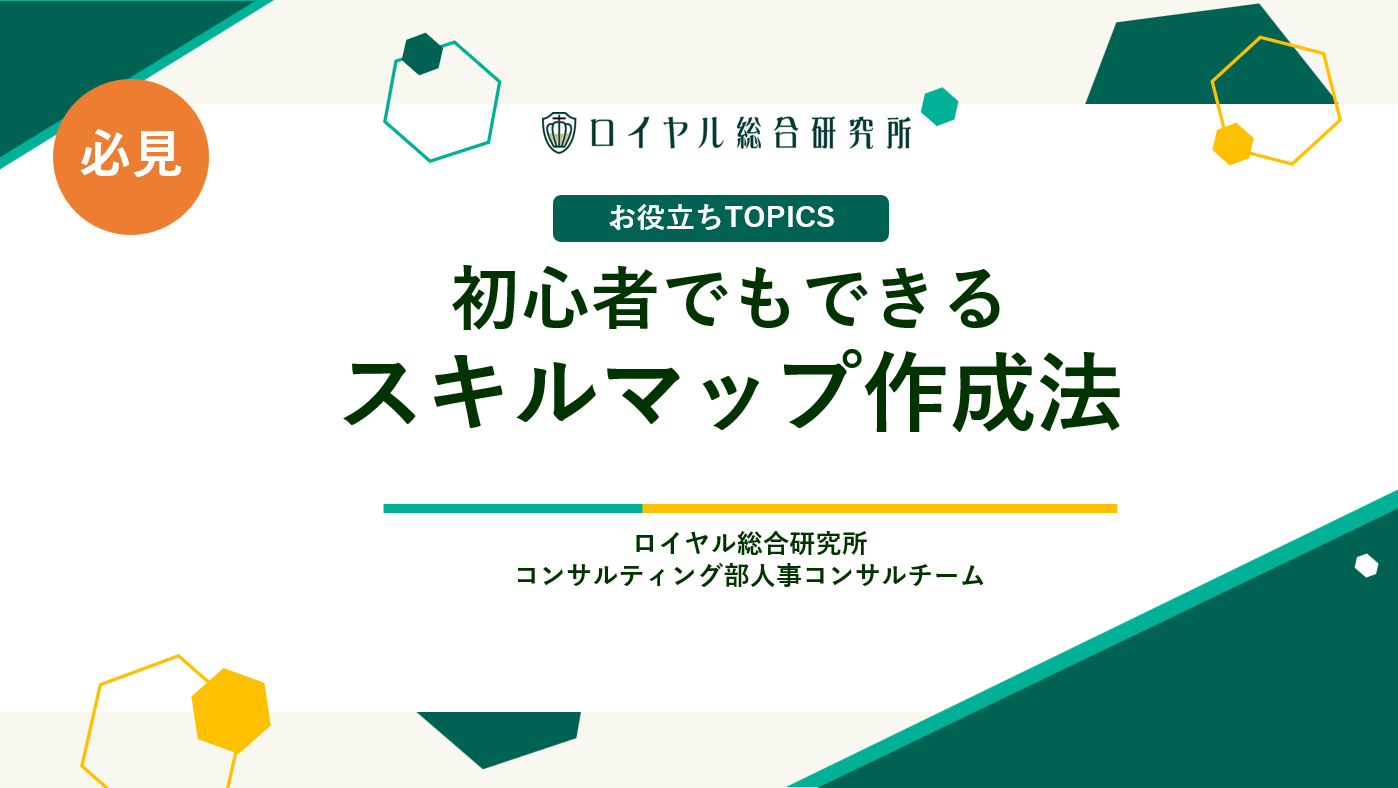
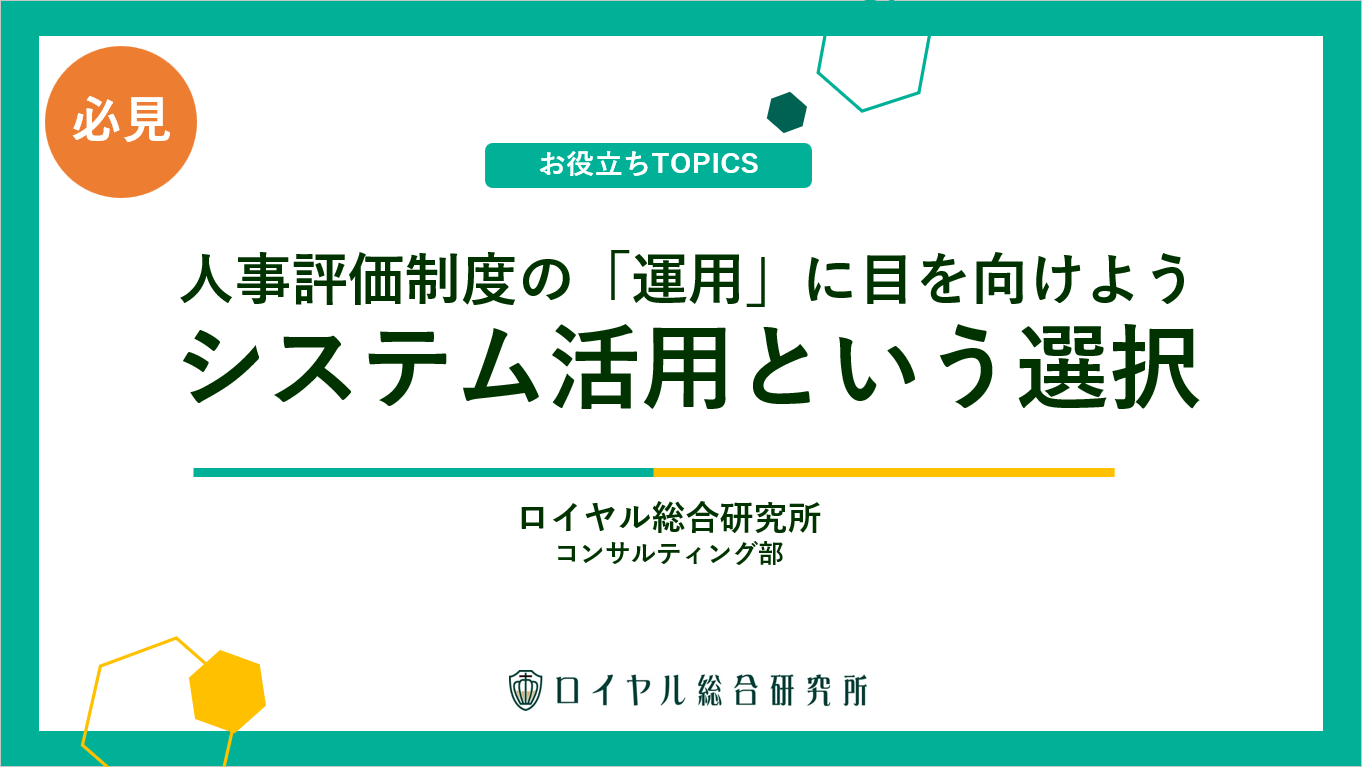
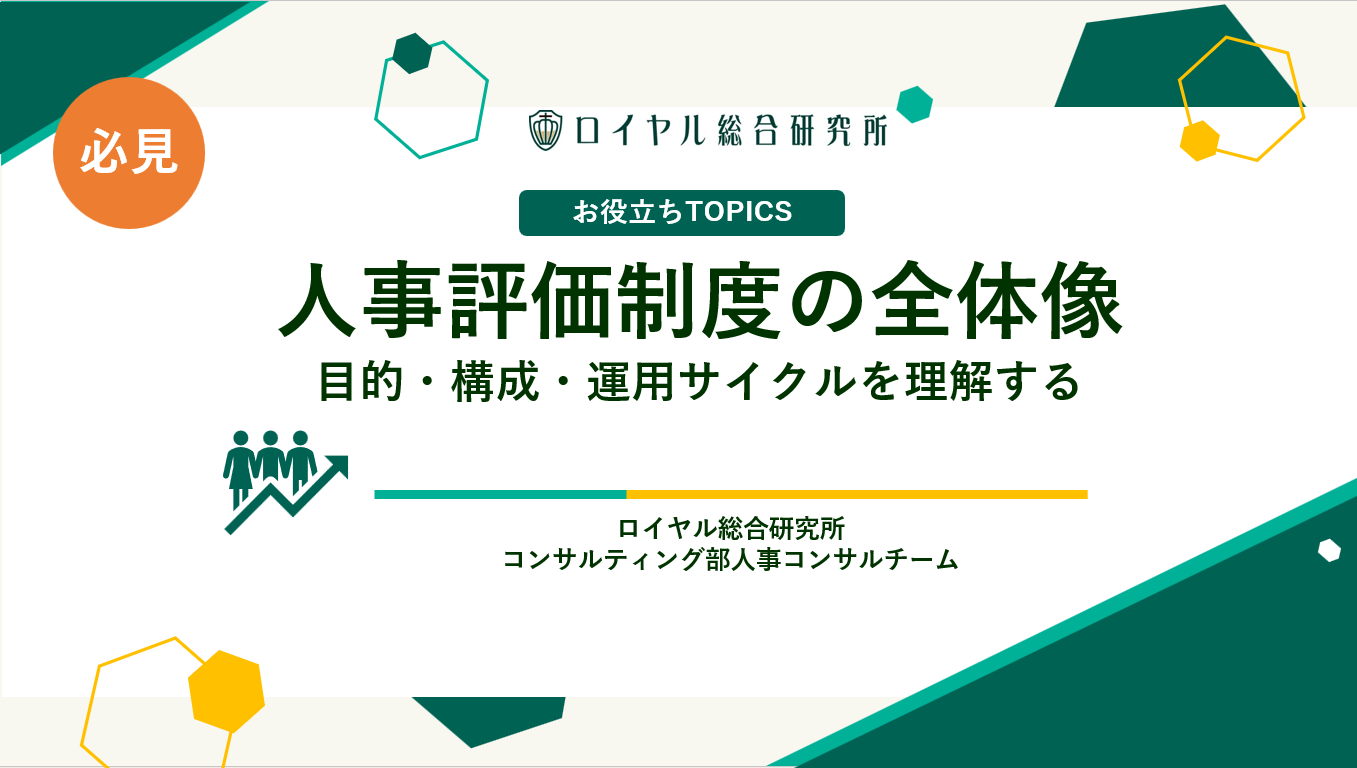
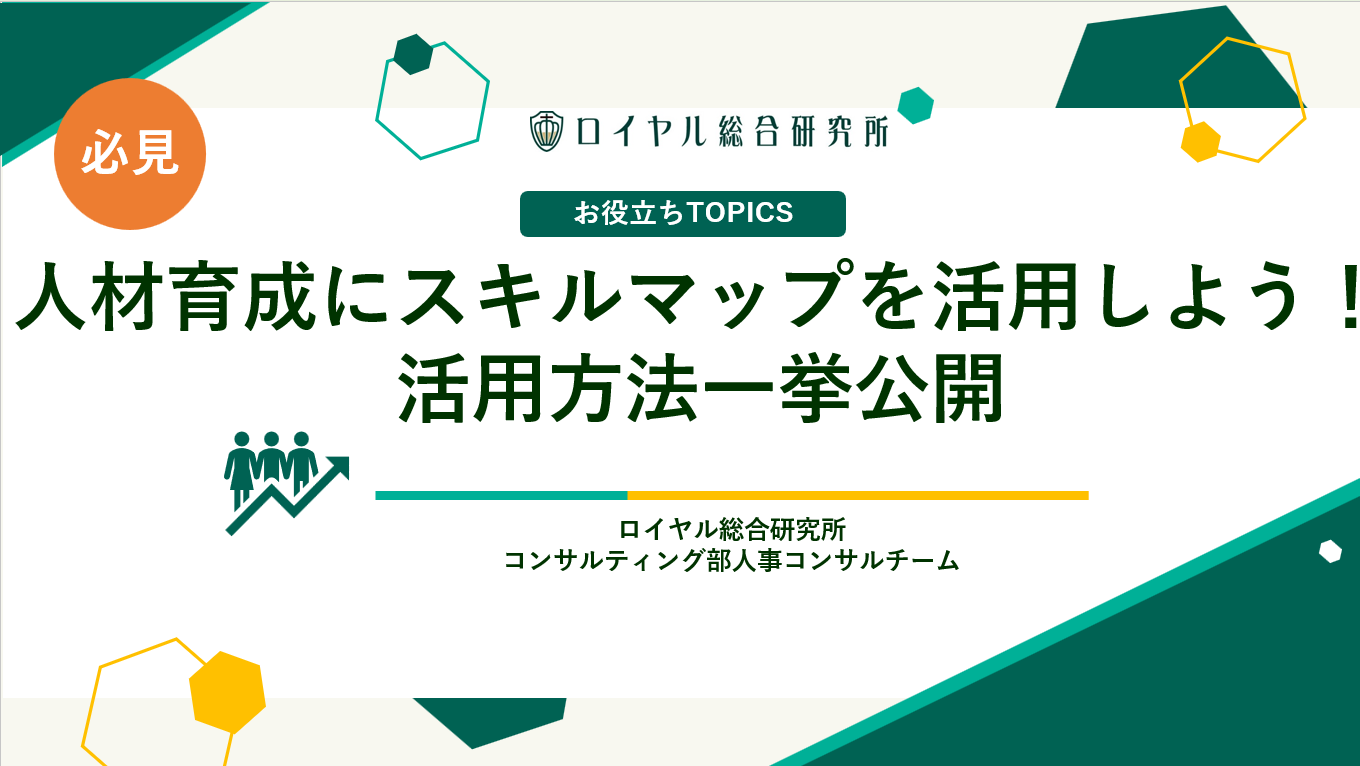
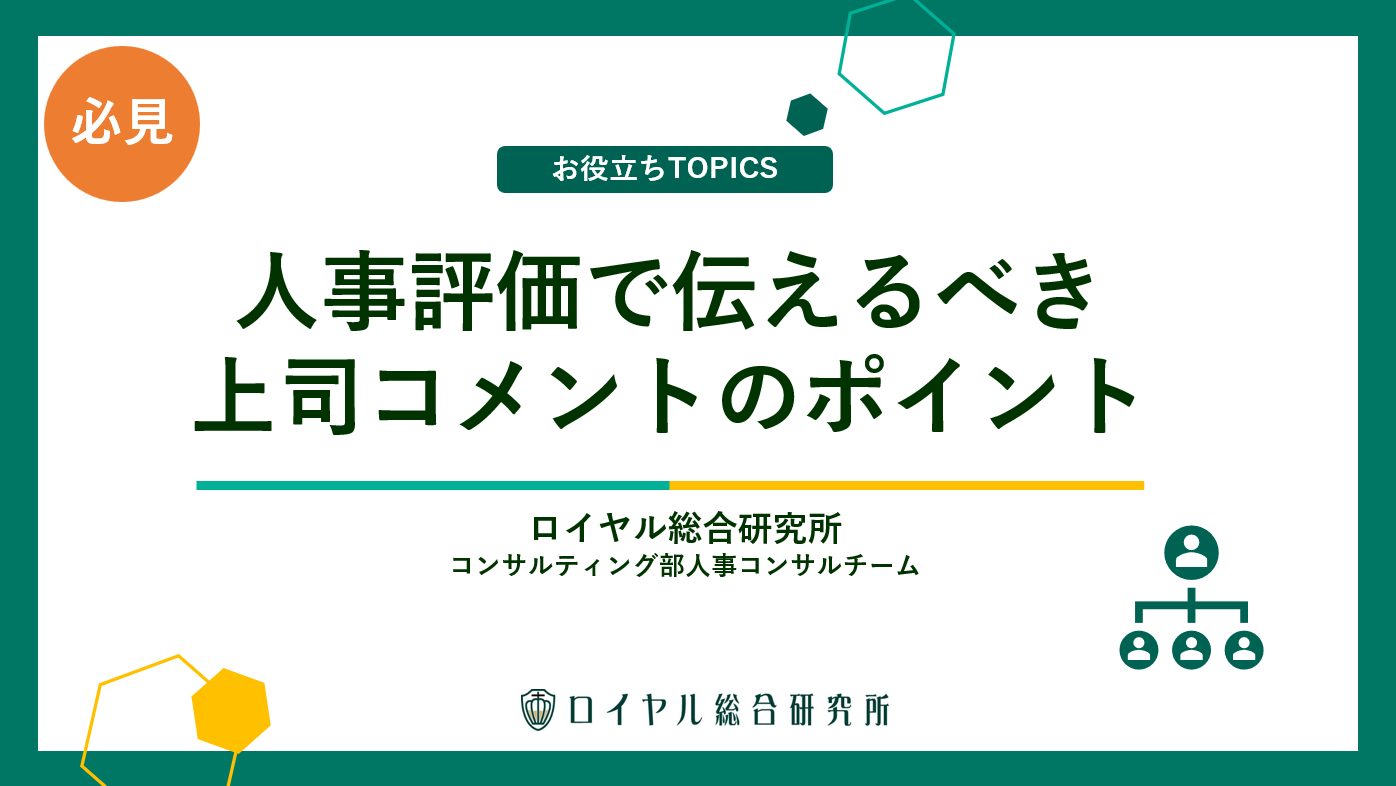
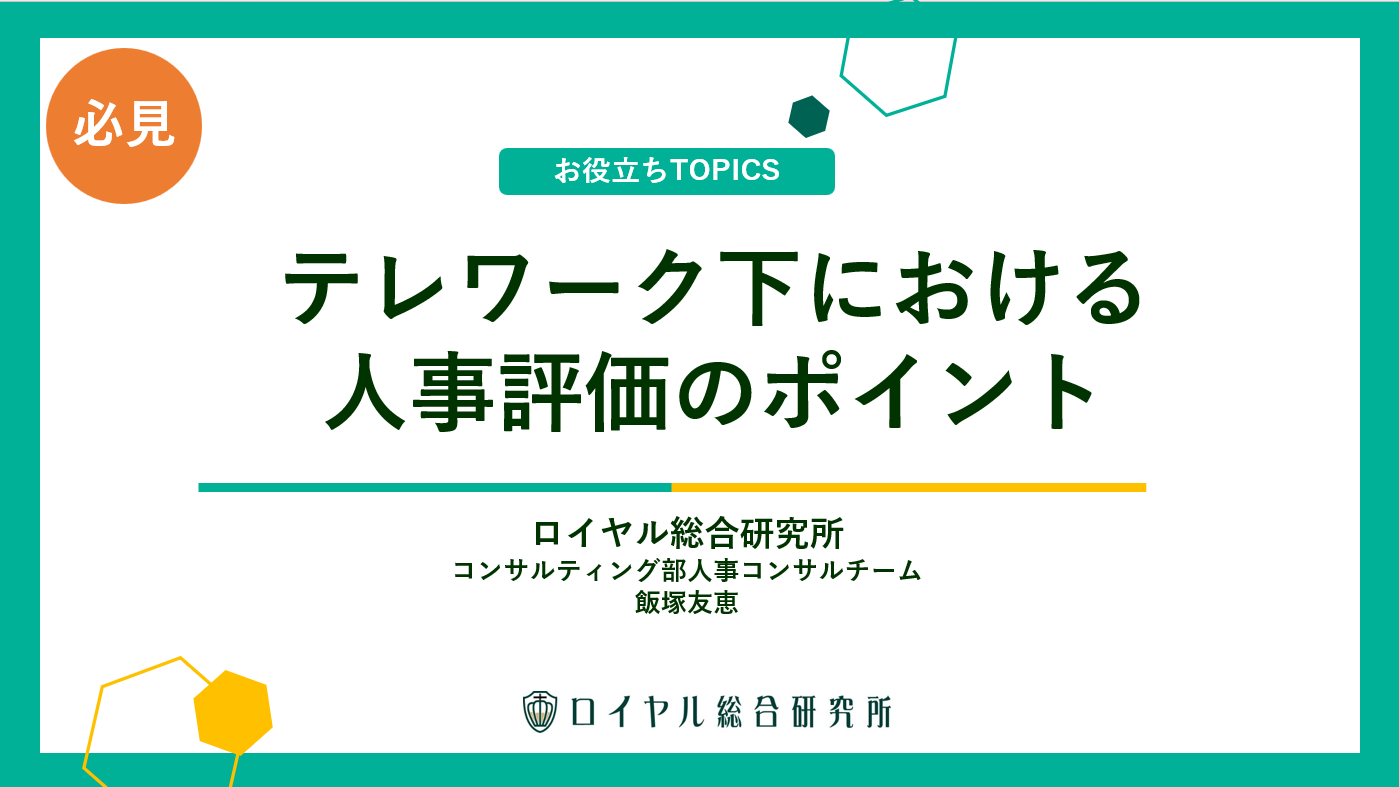
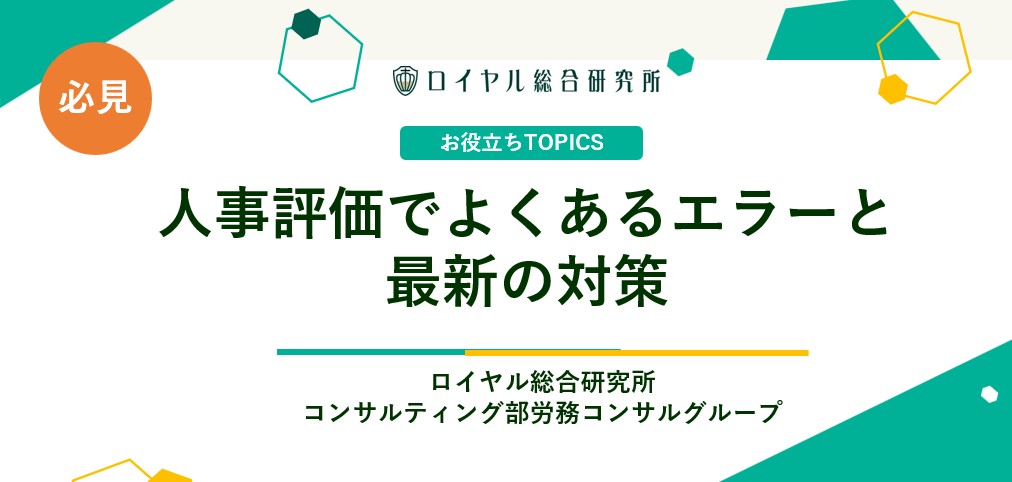
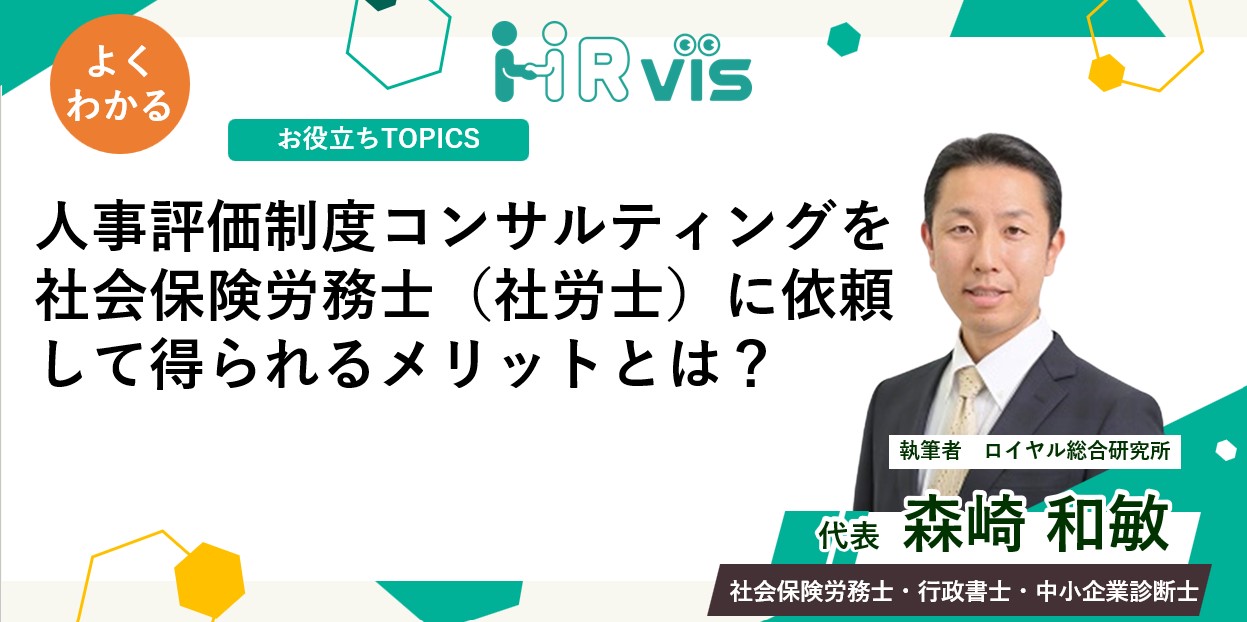
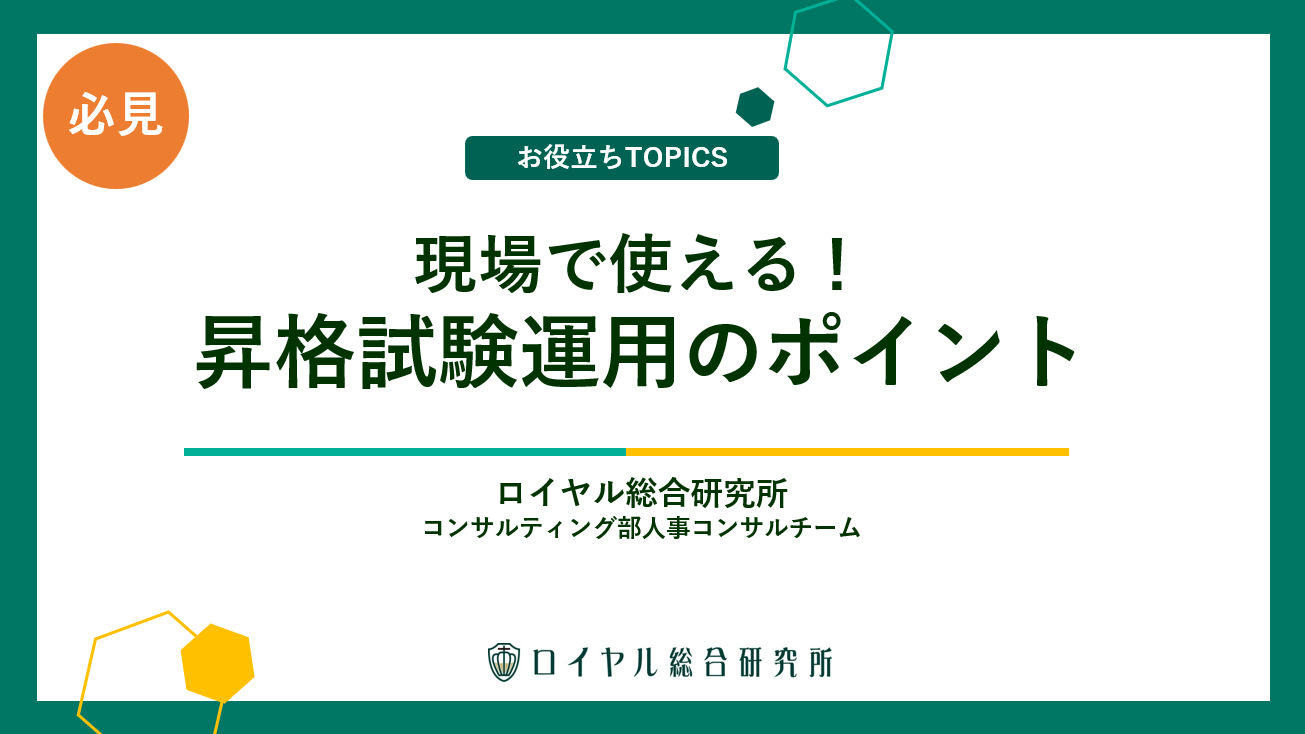
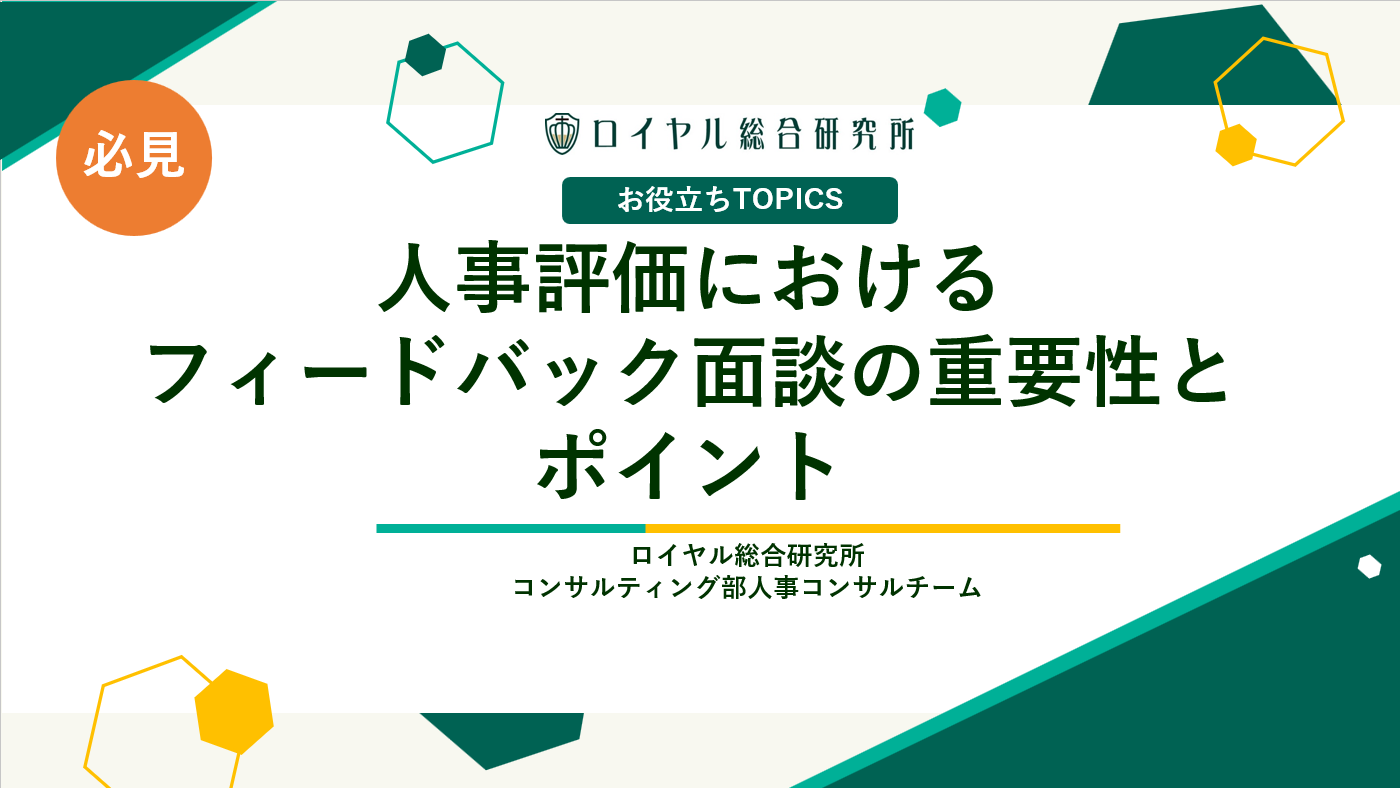



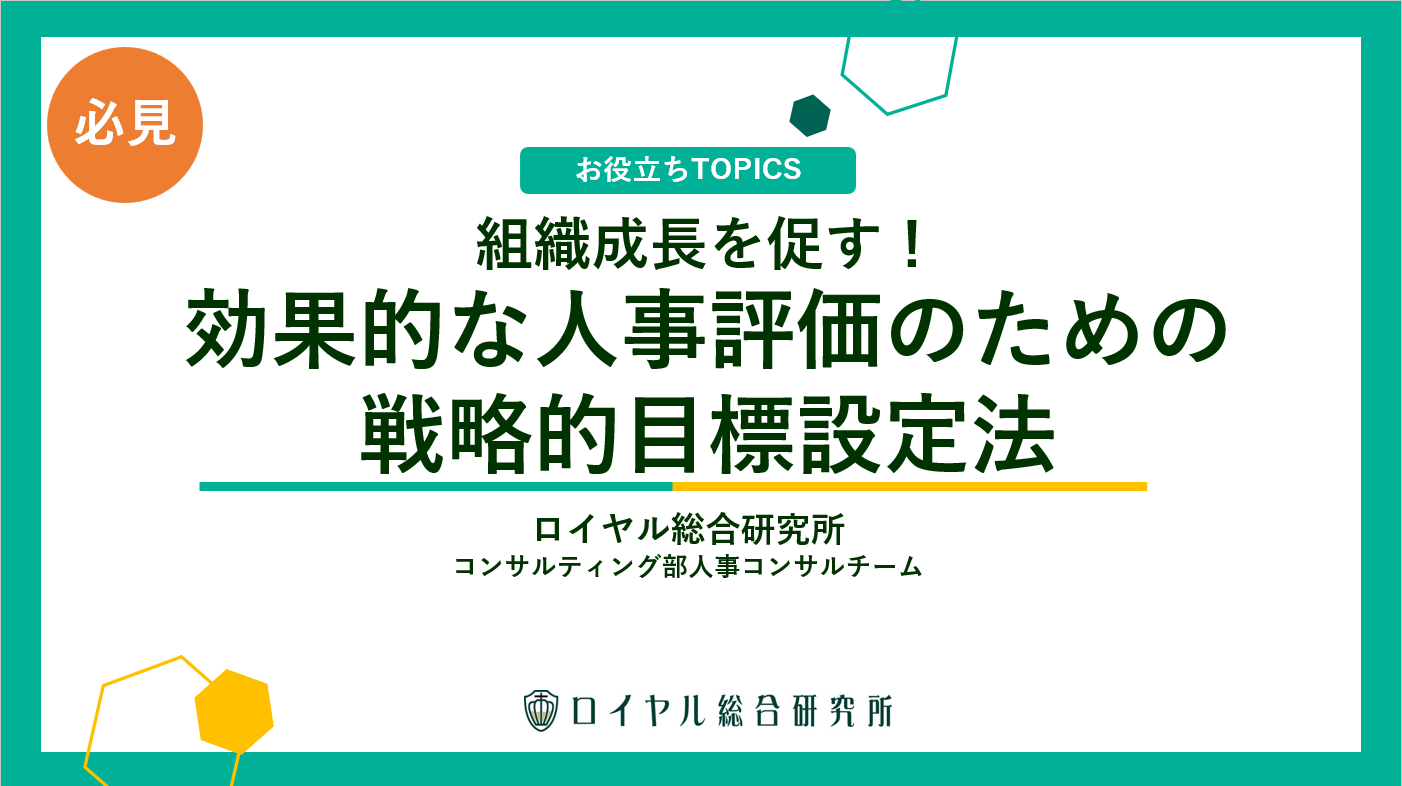
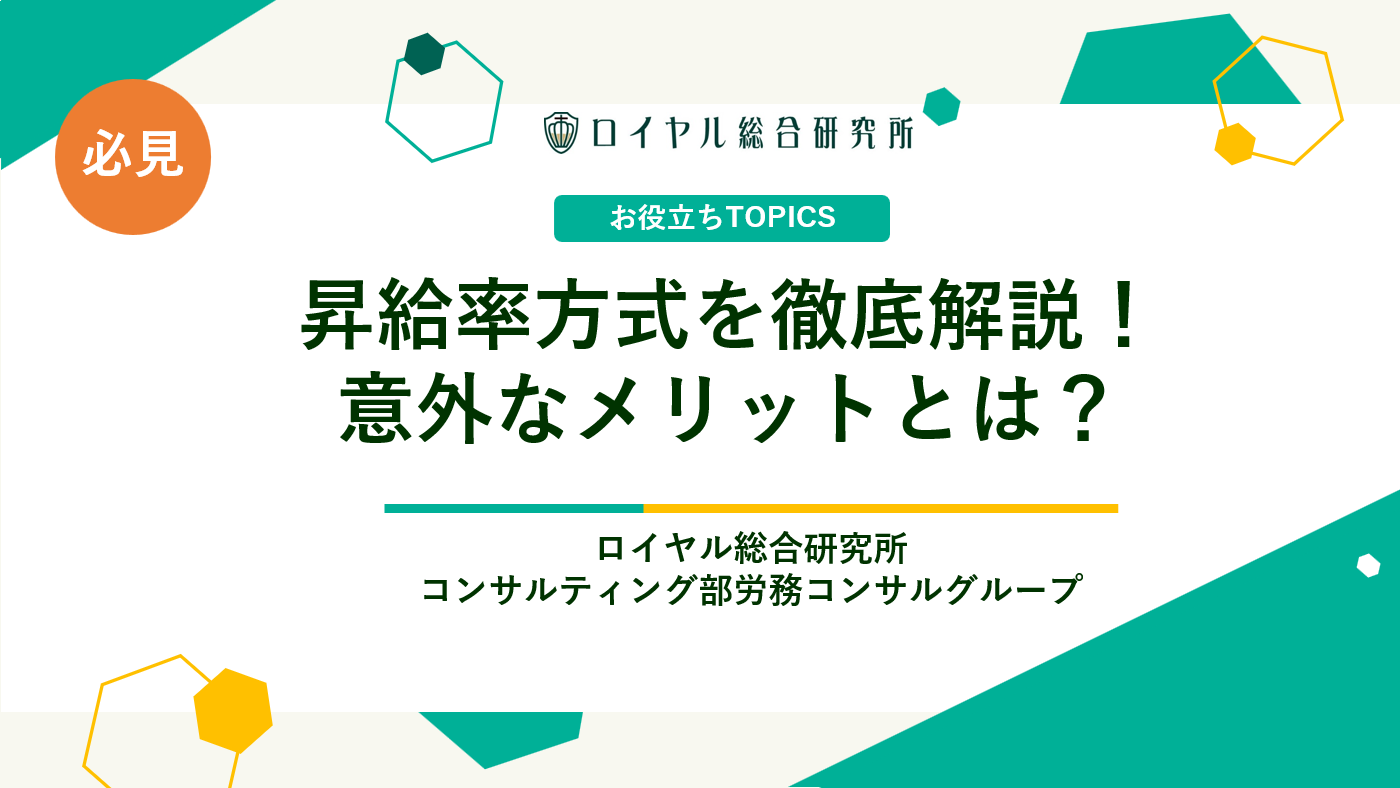


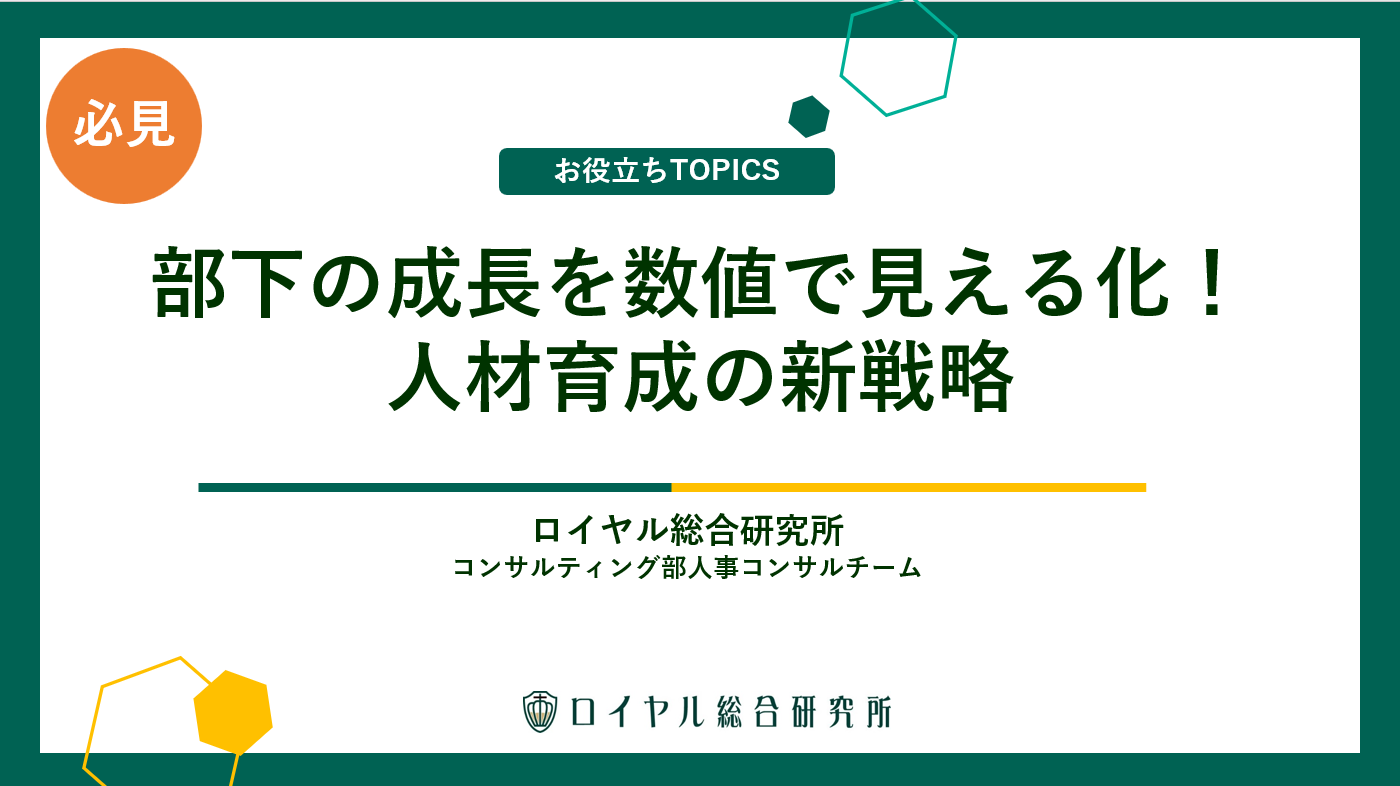
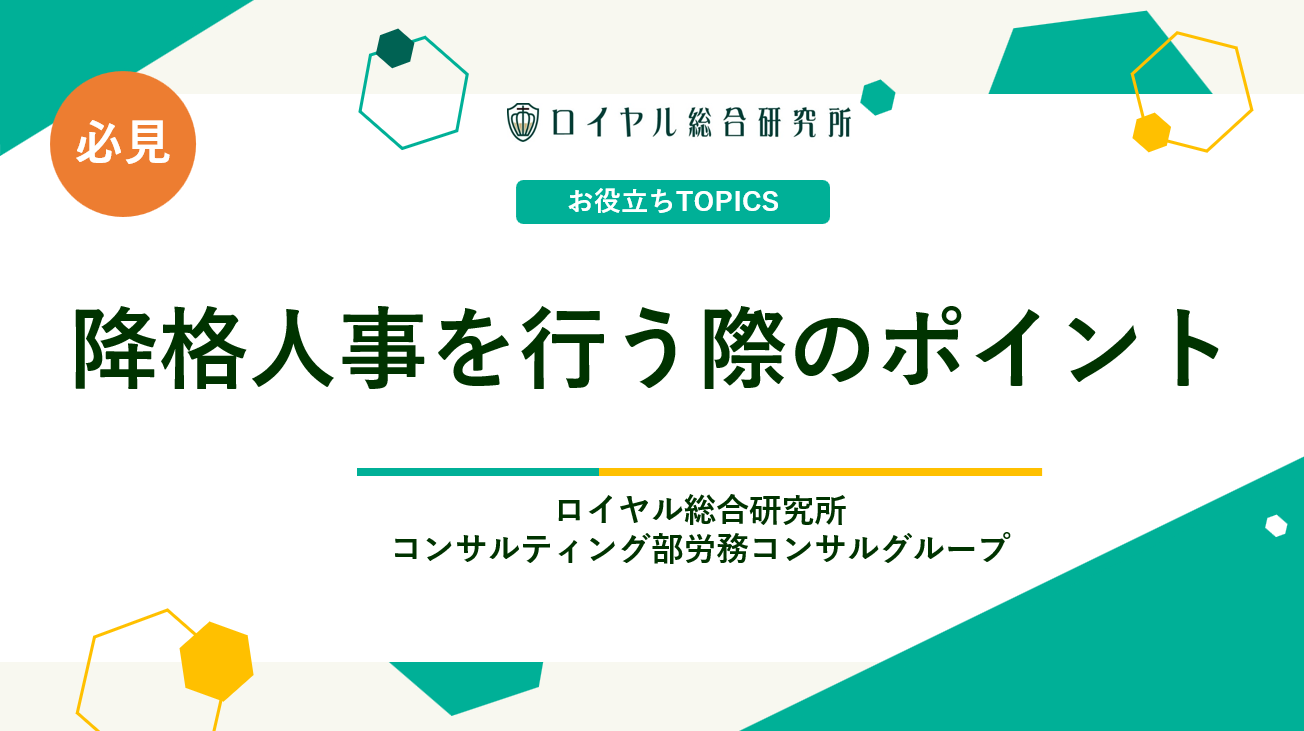
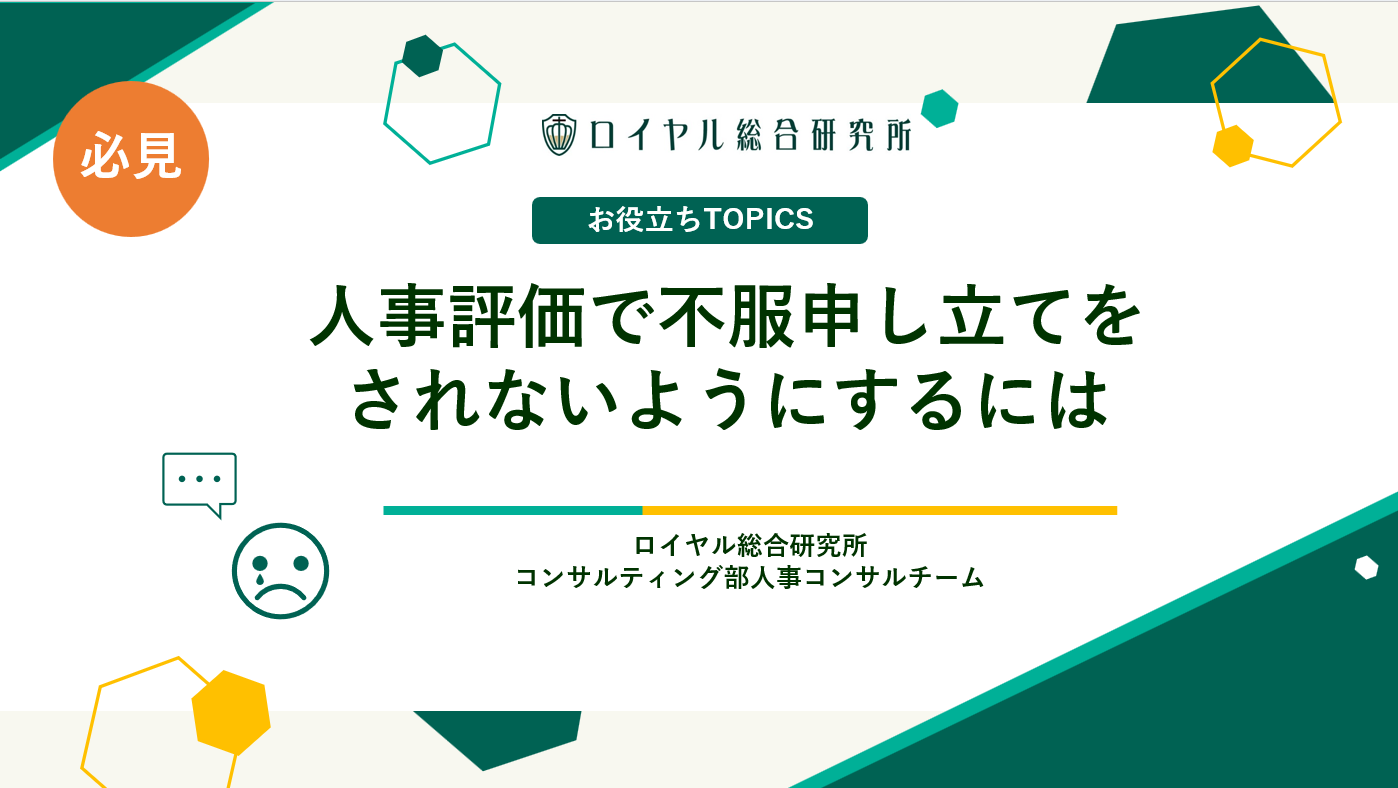
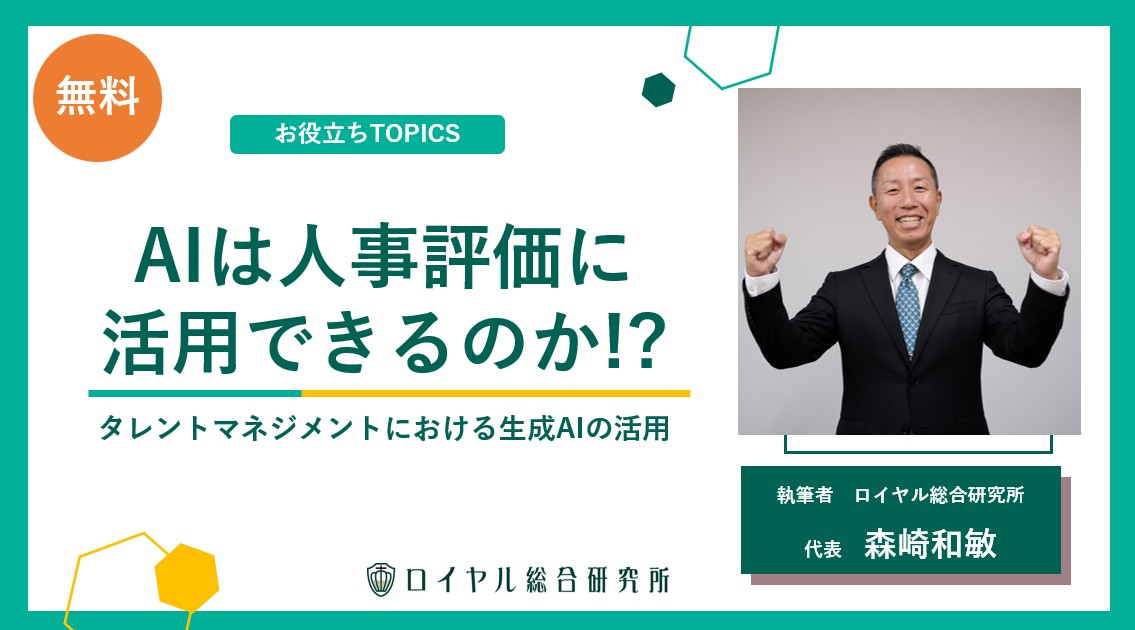

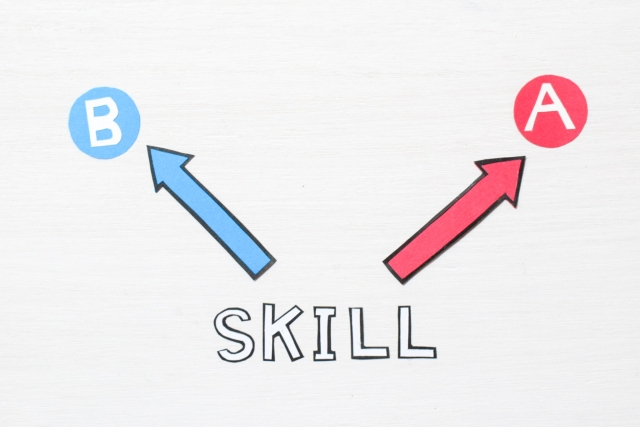


 ページトップに戻る
ページトップに戻る