目次
人事評価における上司コメントの重要性
上司コメントがもたらす影響
人事評価における上司コメントは、単なるフィードバックにとどまらず、部下の成長やチームの士気に大きな影響を与えます。
「この評価、ちゃんと見てもらえているのかな?」と部下が感じてしまうような形式的なコメントでは、せっかくの評価制度も意味をなしません。
反対に「この上司はちゃんと見てくれている」と思えるコメントは、部下のやる気を引き出し、パフォーマンスの向上につながります。上司コメントの良し悪しは、部下の仕事への取り組み方にも影響を与えます。
部下の成長を促す役割
適切なコメントは、部下にとって成長の道しるべとなります。
「よく頑張ったね!」だけではなく、「〇〇のスキルが向上したので、次は△△にも挑戦してみよう」など、次のステップを示すことで、部下のやる気を引き出せます。
また、「以前はプレゼンで緊張してしまうことが多かったが、今回は堂々と話せていたね!」と、過去との比較を交えながら伝えると、部下は自分の成長を実感しやすくなります。成長の実感は、モチベーション維持に必要不可欠です。
陥りがちな人事評価のミス
過去の業績に偏ってしまう
評価を行う際に、過去の成果にばかり注目しすぎると、直近の成長や課題を見落とすことになります。
過去の実績が素晴らしくても、最近のパフォーマンスが低下していれば、その要因を探ることが重要です。
一方で、過去にミスがあったからといって、現在の成長を正しく評価しないのも公平ではありません。
評価は、現在の状況を踏まえてバランスよく行うのが良いでしょう。
上司の甘辛が生まれる
上司の性格、上司と部下との人間関係等が部下の業績評価に反映されてはいませんか?
「A上司は評価が甘いけれど、B上司は評価が厳しい」「上司はAさんには甘いけれど、同じ評価でもBさんには厳しい」と部下が感じると、会社や組織に対して不信感を抱いてしまいます。
評価は主観ではなく、事実ベースで客観的に行うことが必要です。
誰が見ても納得できる評価を行うことで、部下が会社を信頼して業務に取り組むことができます。
上司コメントに含めるべき項目
行動目標と成果の繋がり
評価コメントでは、具体的な行動目標とその成果を明示することが重要です。
「目標達成のために〇〇を実施し、成果を上げた」と記載しましょう。
目標に対してどのような努力をし、その結果どのような成果を上げたのかを具体的に書くことで、部下は「努力が報われた」と感じることができます。
個人の強みと改善点の指摘
部下の強みを活かしながら、改善点を伝えることで、成長を促せます。
「分析力が高いが、もう少し決断力をつけるとさらに良くなる」など、バランスよく指摘しましょう。短所は時に長所にもなります。
改善事項を並べて話すのではなく、短所を活かす方法を探しながら部下一人一人に合わせた改善案を提案することも必要です。
評価コメントの具体的な書き方
ポジティブな表現を使う
たとえ改善点を指摘する場合でも、ポジティブな表現を心がけましょう。
ネガティブな指摘だけではなく、成長のチャンスとして伝えることが大切です。また、ポジティブな表現を使うことで、部下は「もっと頑張ろう」という前向きな気持ちになりやすくなります。
「課題はあるけれど、着実に成長している」「次のステップに進む準備ができている」といった伝え方を工夫すると、部下がより主体的に取り組めるようになります。
事実ベースで評価する
「最近頑張っているみたい」ではなく、「今月の売上が先月比20%向上した」「プロジェクトの納期を3日前倒しで完了させた」など、客観的なデータを基にした評価を行いましょう。
事実に基づく評価は、評価を受ける側の納得感を高めるだけでなく、不公平感をなくすためにも重要です。
また、数字だけでなく、具体的な行動や工夫した点も加えることで、より伝わりやすくなります。
「〇〇の対応が迅速で、顧客からの評価が上がった」など、成果の背景も説明できるとより効果的です。
感覚的な評価ではなく、実際の成果や行動に基づいたフィードバックをすることで、部下は「自分が評価された理由」が明確に理解できます。
評価基準に基づいて作成する
評価コメントが個人的な感想になってしまうと、不公平感が生じます。
会社の評価基準に基づき、「期待される行動」や「成果」に沿ったコメントを作成しましょう。
例えば、「リーダーシップを発揮したかどうか」を評価基準とするなら、「チーム内のコミュニケーションを活性化し、目標達成に向けた行動を促した」といった具合に、具体的なエピソードを盛り込むとよいでしょう。
評価を受ける側が、どのような行動が求められているのかを理解しやすくなり、次の行動につなげやすくなります。
部下へのメッセージの伝え方
明確な目標を設定させる
評価を伝える際には、次の目標を明確に設定しましょう。
「来期はさらに成長できるよう、〇〇に挑戦してみよう」といった前向きなメッセージが効果的です。
目標設定の際には、「具体的」「達成可能」「期限付き」の要素を含めることで、より実行しやすくなります。
また、目標は短期と長期の両面で考えると効果的です。短期的には「次の3カ月でプレゼンの回数を増やす」、長期的には「1年後には社内研修の講師を務める」など、段階的にステップアップできるようにすると、成長の実感を持ちやすくなります。
課題を明示する
部下が成長するためには、明確な課題を伝えることが重要です。
「プレゼンが苦手」と言うよりも、「プレゼン時の説得力を高めるために、事前にシミュレーションをしてみよう」と具体的に指摘すると、改善しやすくなります。
期待する行動を明示する
評価コメントでは、「このままでいい」ではなく、「こうすればさらに良くなる」という視点を持ちましょう。
「積極的に意見を発信することで、チームの議論がより活発になる」といったように、期待する行動を伝えることで、部下の成長を促せます。
部下に改善を促すには?
改善を促す指摘では、「具体的」「客観的」「チームへの貢献」を意識しましょう。
「具体的」では「売上が上がった」「成果が出た」と評価するのではなく、どのような努力や工夫があったのかを具体的に伝えることで、部下の成功体験をより深めることができます。
次に「客観的」です。感情や個人的な印象ではなく、データや具体的な行動に基づいて評価することが重要です。「リーダーシップがある」と言うなら、「会議で積極的に発言し、チームをまとめた」といった根拠を示しましょう。
最後は「チームへの貢献」です。評価の際には、個人の成長だけでなく、その成長が業務の効率化や組織の目標達成にどのように貢献したかを伝えることが大切です。これによって、「自分の成長は役に立っている」と部下が感じることができます。
部下を評価する際の心構え
信頼関係を築く
評価は信頼関係の上に成り立ちます。普段から部下とコミュニケーションを取り、信頼を築くことが大切です。
ただし上司と部下の馴れ合いではなく、共に会社を支える一員として、業務のパフォーマンスを上げるような信頼関係を築くと良いでしょう。
目標に対して当事者意識を持たせる
「自分の目標」として捉えられるように、部下が主体的に取り組めるような評価コメントを作成することが大切です。
現実とかけ離れた目標設定や、チームに関係ない目標設定では部下が当事者意識を持ちにくく、目標に向かって努力する意欲が湧きません。繰り返しになりますが、「部下本人が努力すれば実現可能であること」「目標を達成すればチームに貢献できること」を目標設定で意識することで、部下が目標に対して当事者意識を持ち、意欲的に活動することができます。
部下の人事評価、大変ではありませんか?
人事評価の上司コメントには、大きく3つのポイントがあります。
・明確な目標と事実に基づいた成果によって評価する
・チームへの貢献を評価に反映させる
・ポジティブにフィードバック面談を行い、部下の成長ステップを示す。
ですが現実的には、3つを完全に備えたコメントを上司が書くのは膨大な経験や技術、時間が必要です。この記事をご覧になっているということは、「社員を公平に評価したい」「人事評価によって、社員のやる気を維持・向上させたい」とお考えだからではないでしょうか。
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ「HRvis」の導入をご検討ください!
「HRvis」は、人事のプロである社会保険労務士と、システムのプロが共同開発した、クラウド型タレントマネジメント人事評価システムです。
AI評価支援機能を搭載しており、HRvisに登録されている各種情報を参考にChatGPTが人事評価を支援します。目標案の作成では、本人の等級や能力だけでなく、全社・所属目標、前回の評価シート結果まで参考にするので会社の方針と一致させつつ本人の成長に繋がる目標を作成できます。評価では目標に対して事実のみを入力し、上司が追認することで、AIが1次評価を実施し、自動的に評価コメントを作成します。
AI評価支援機能で、効率的かつ公平な人事評価をしませんか?
ロイヤル総合研究所 コンサルティング部
人事コンサルタント 飯塚友恵

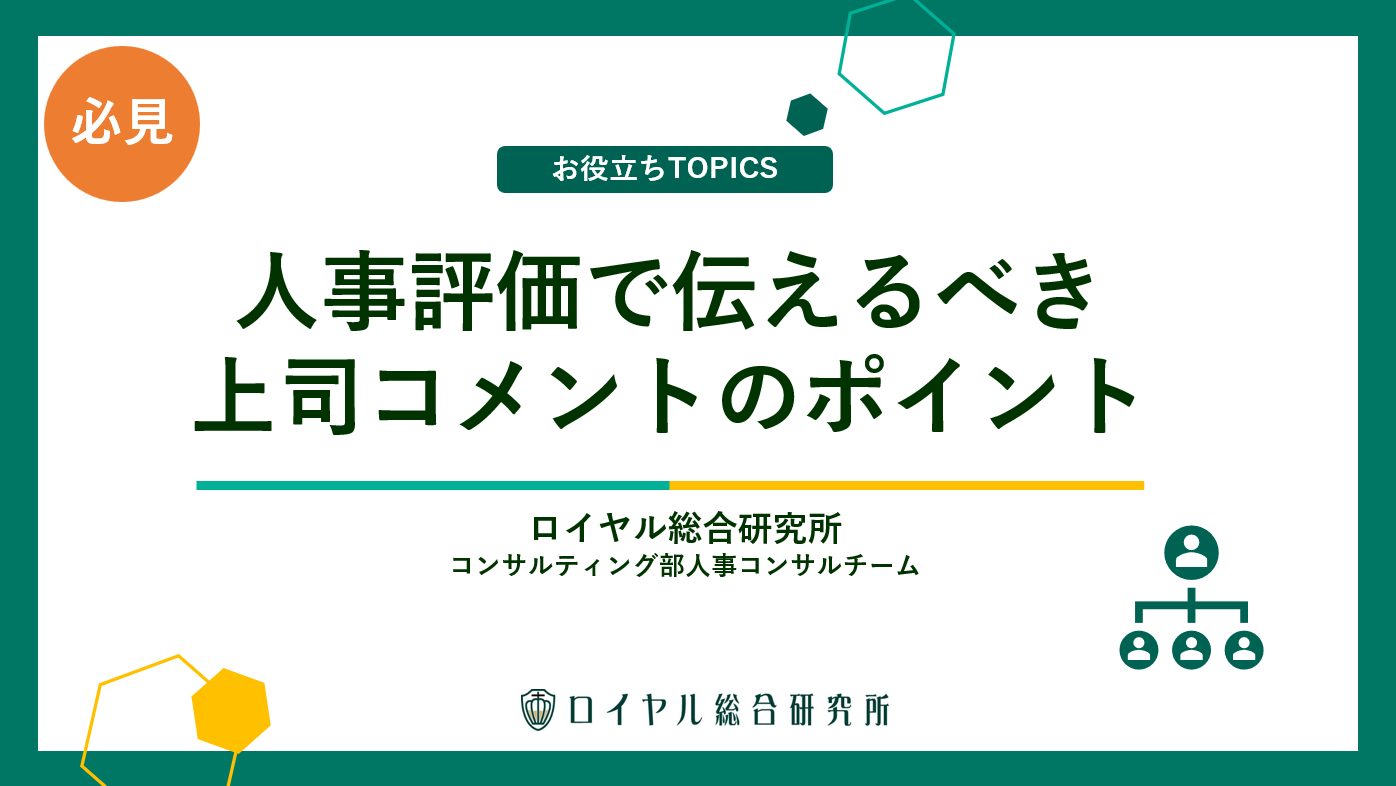
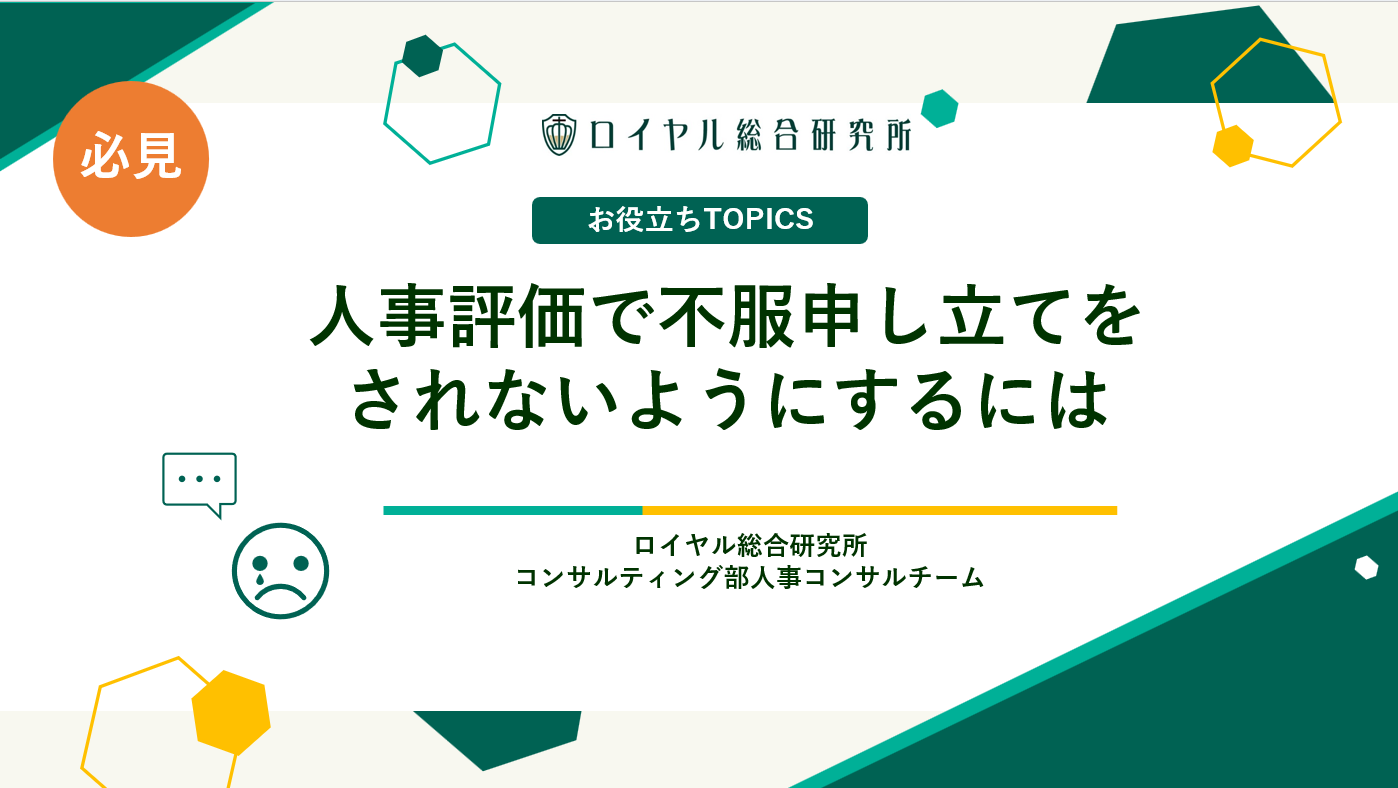
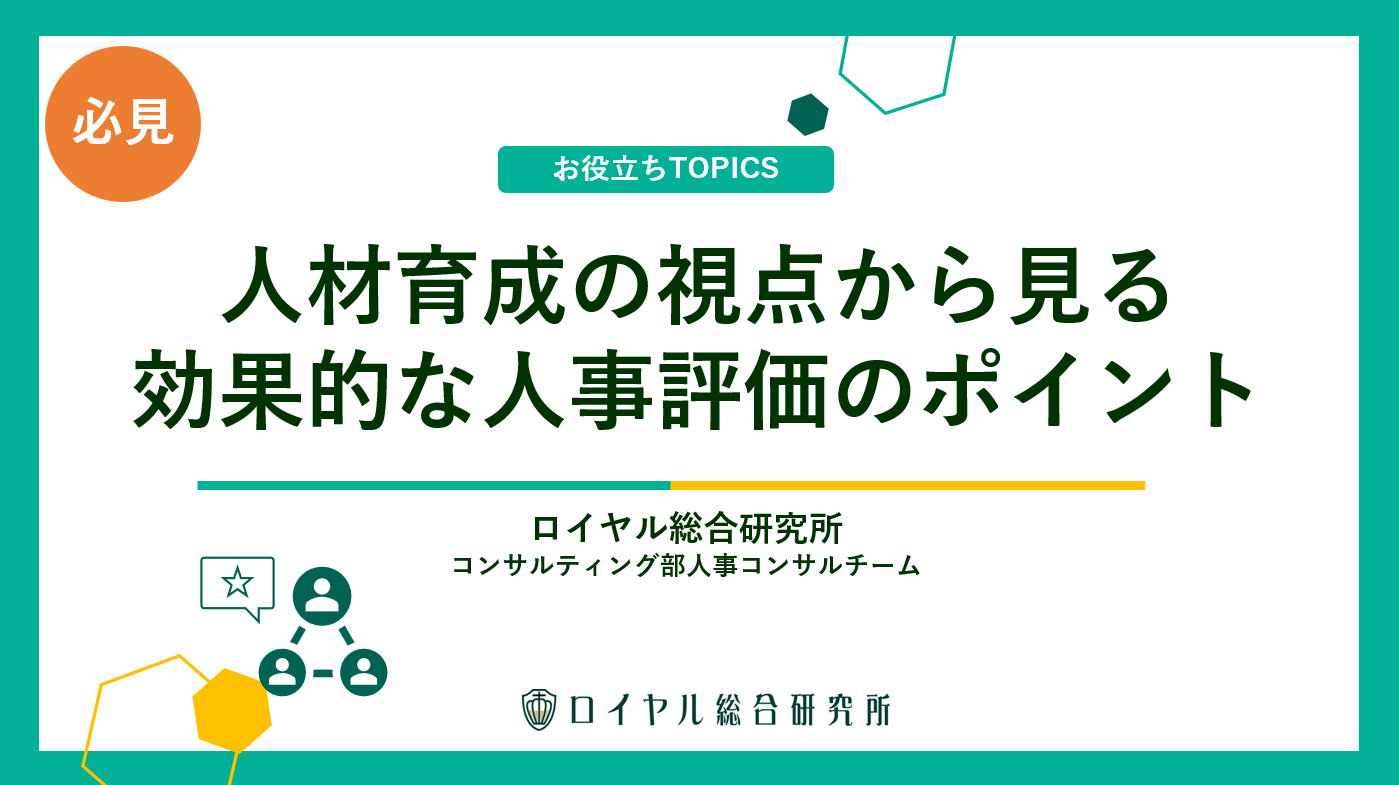
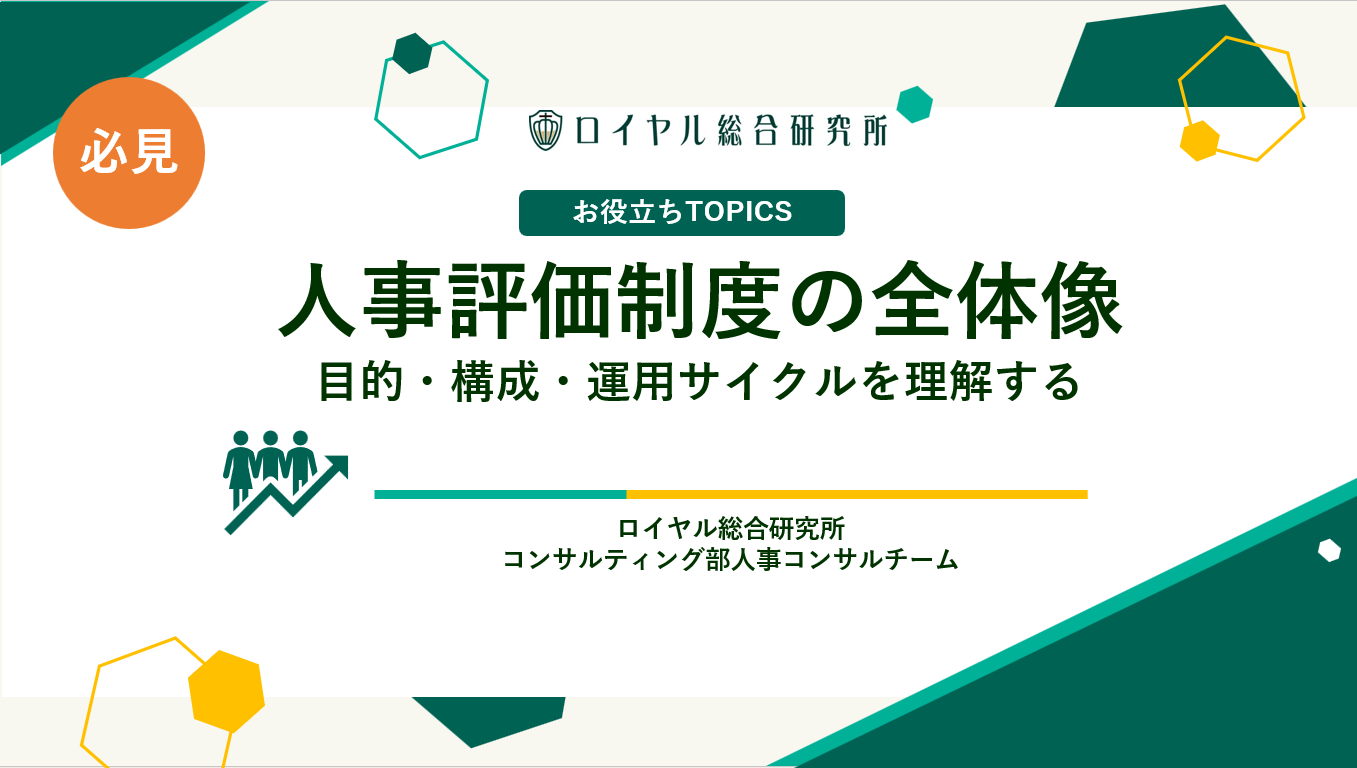
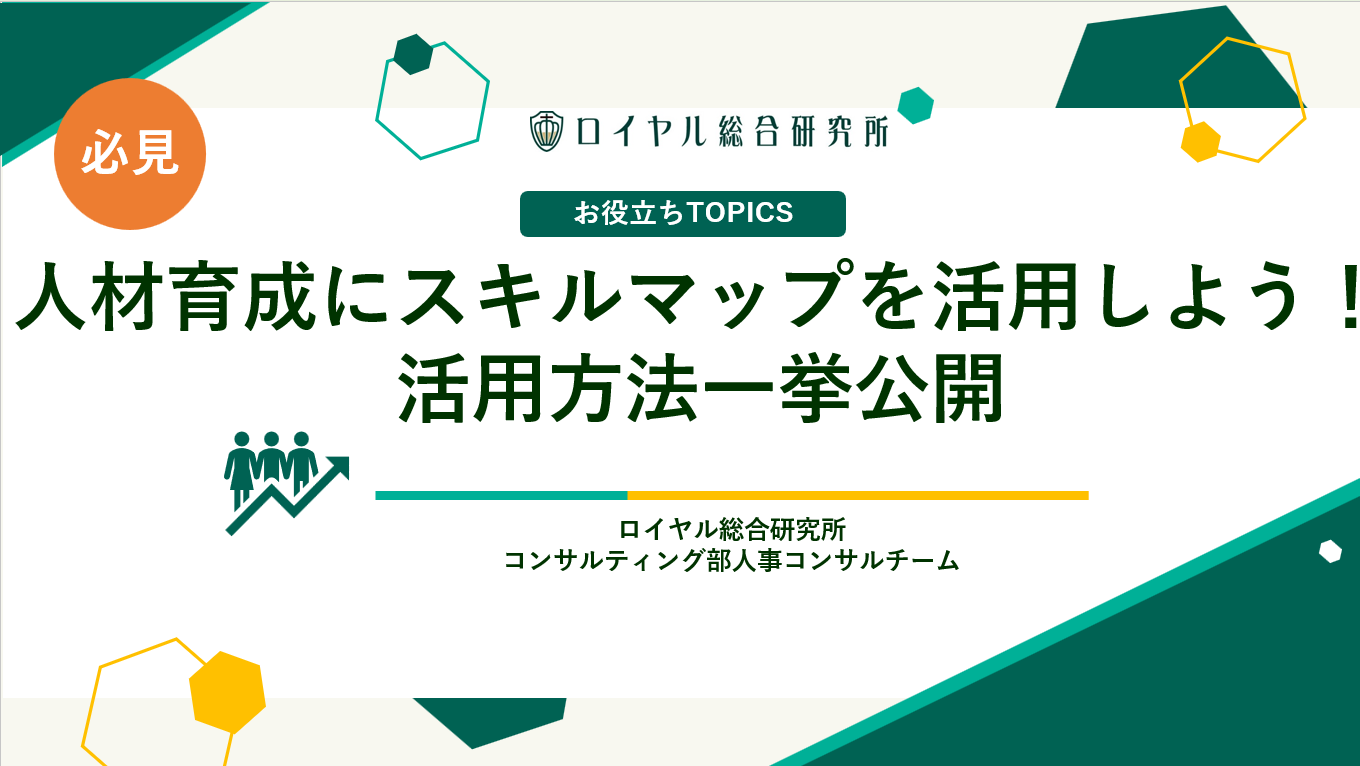
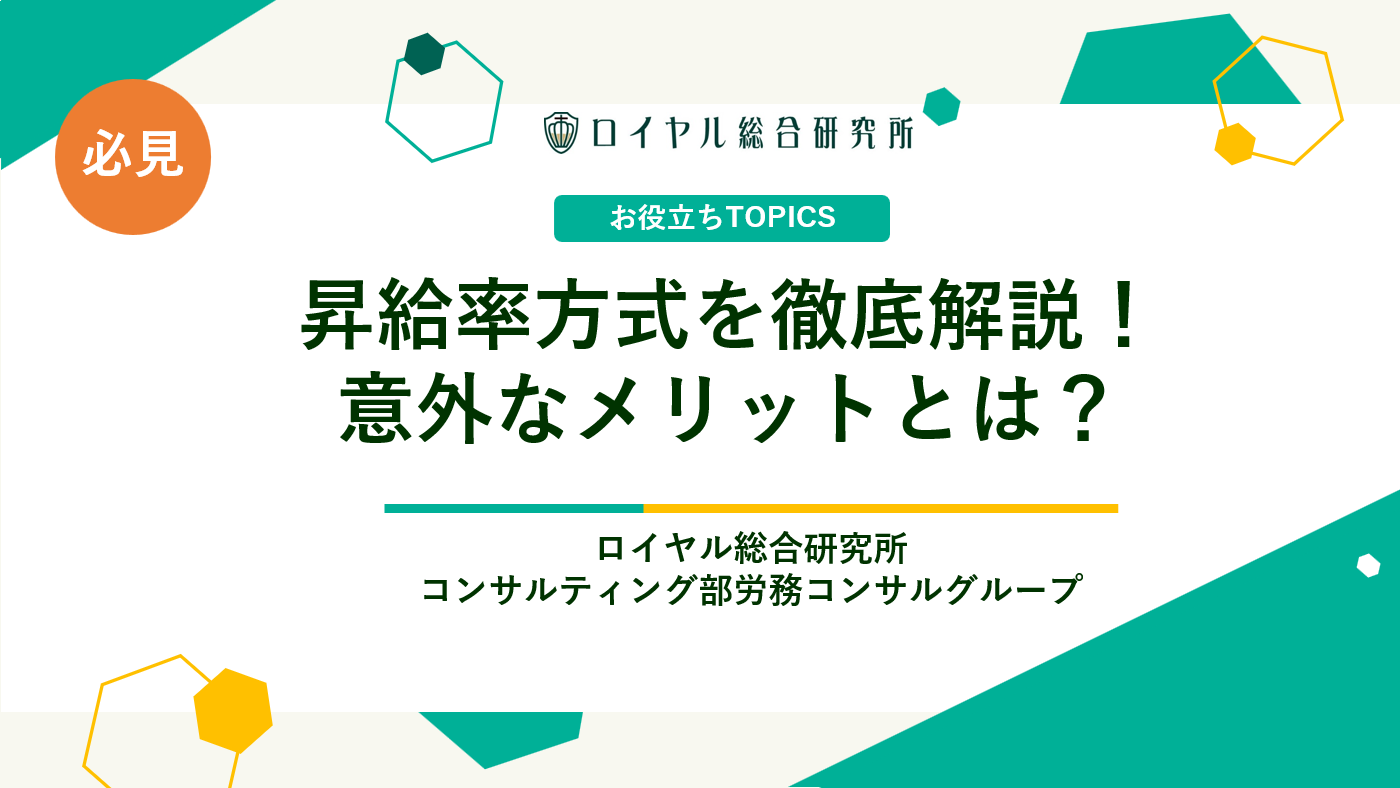
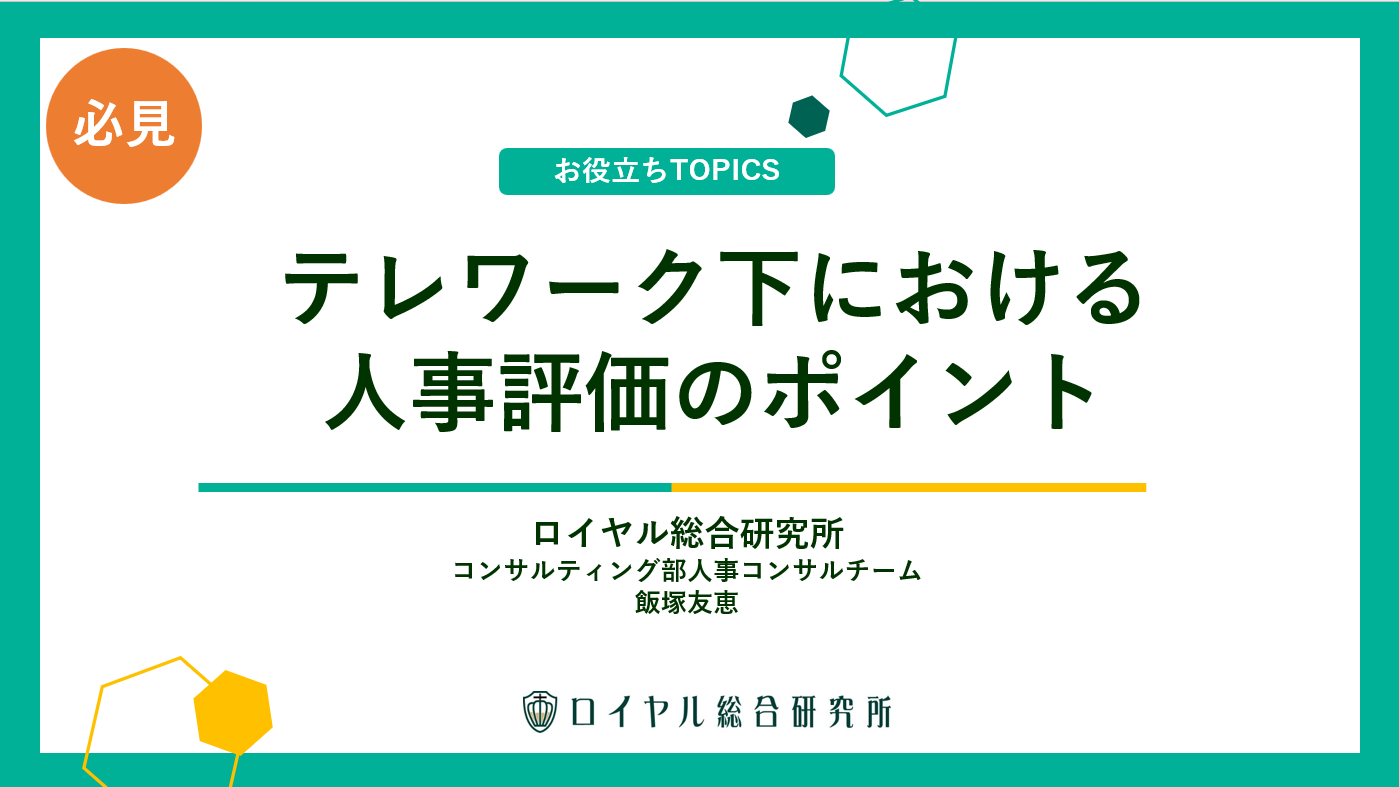
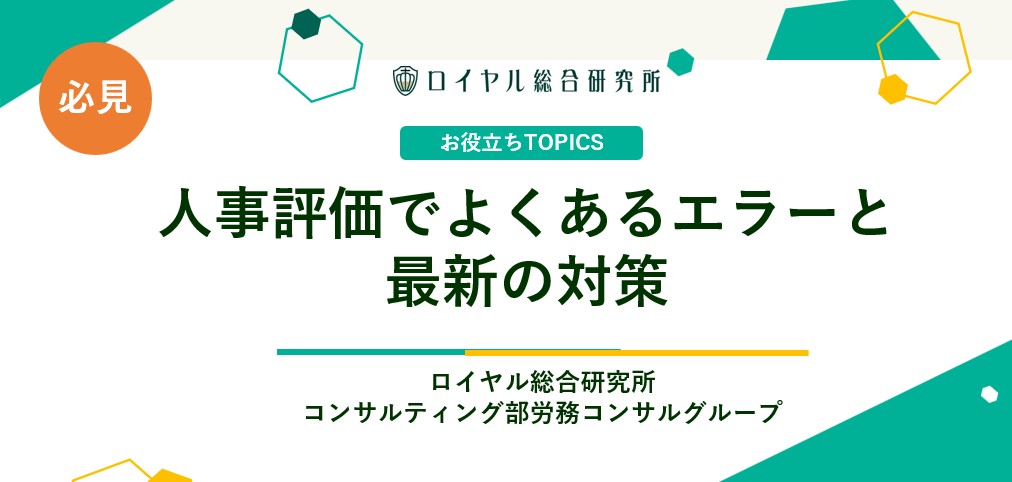
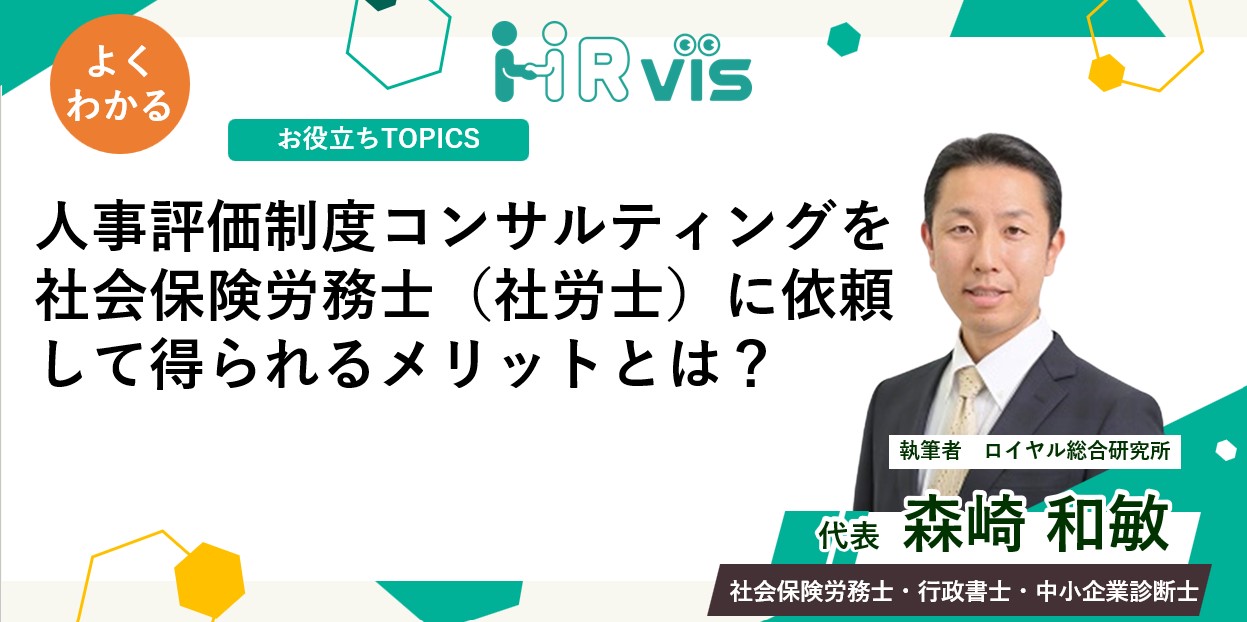
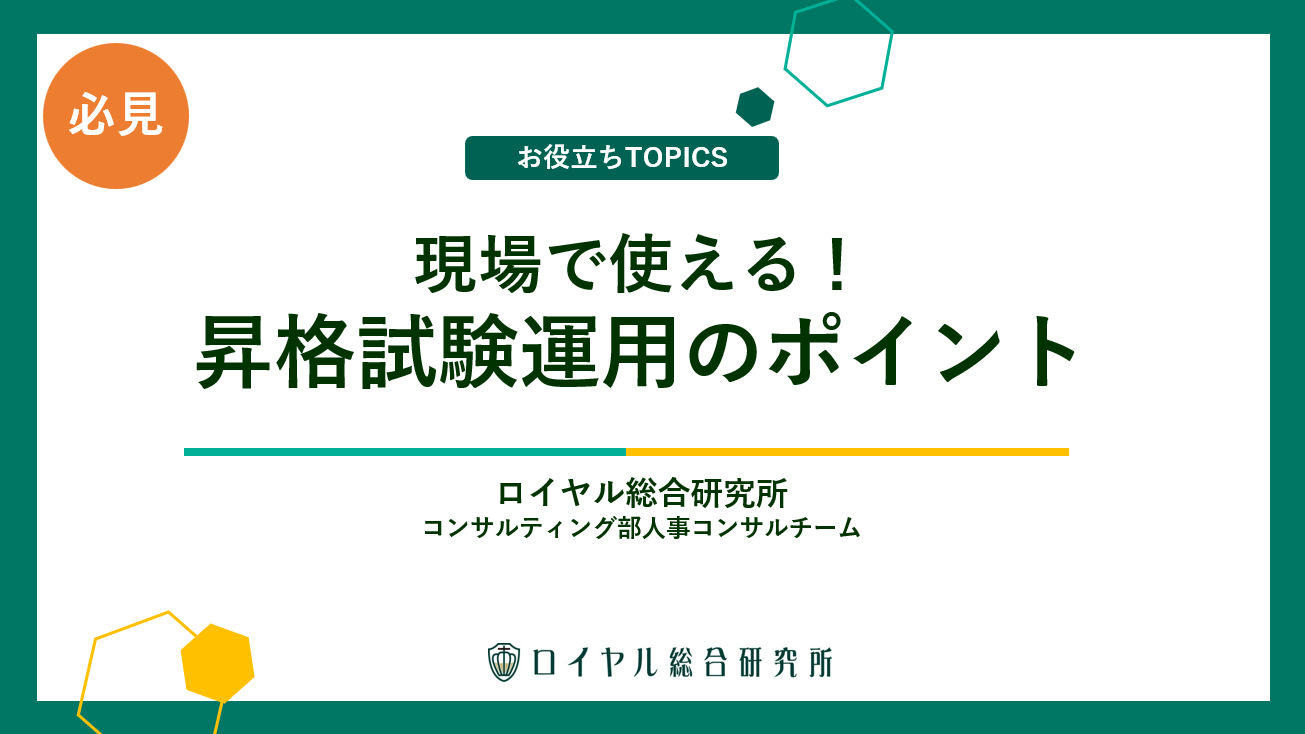
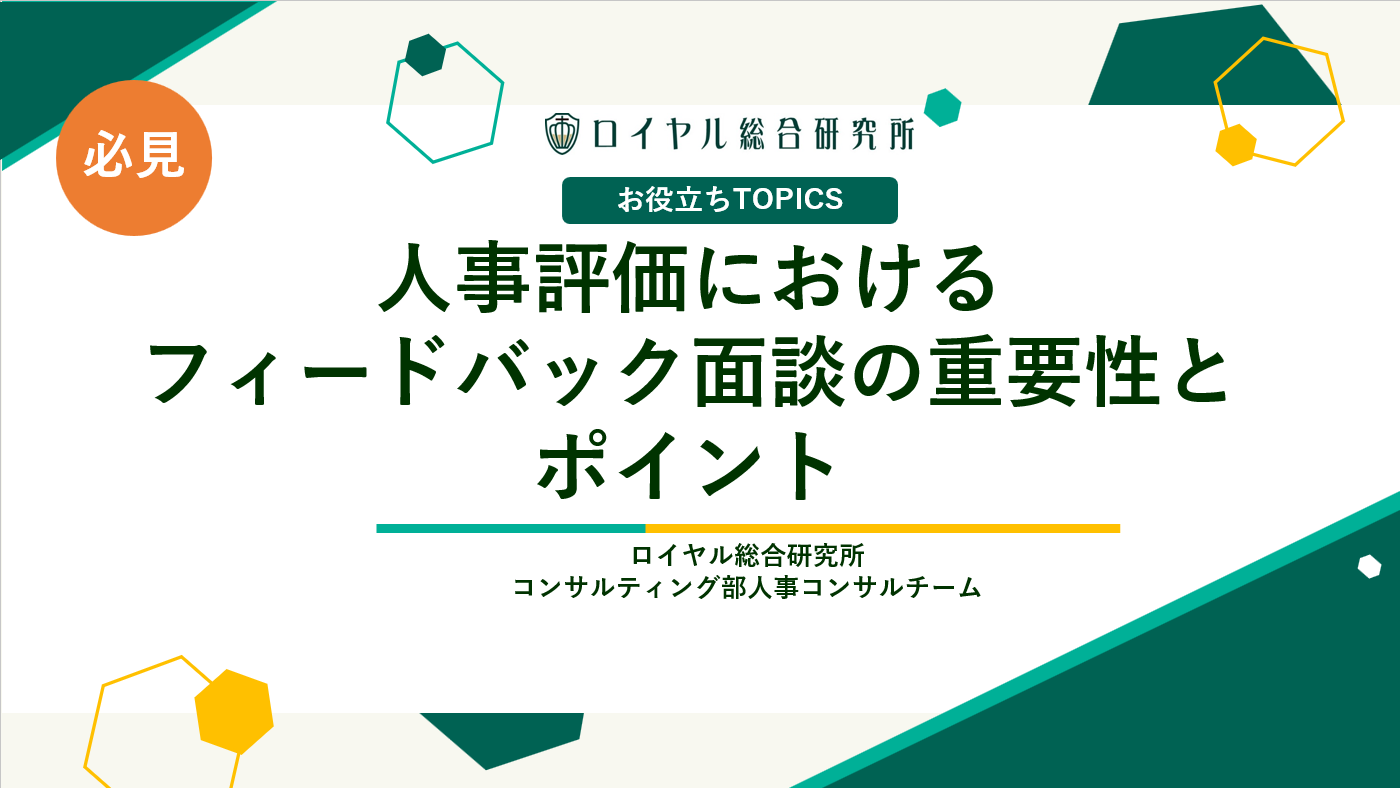



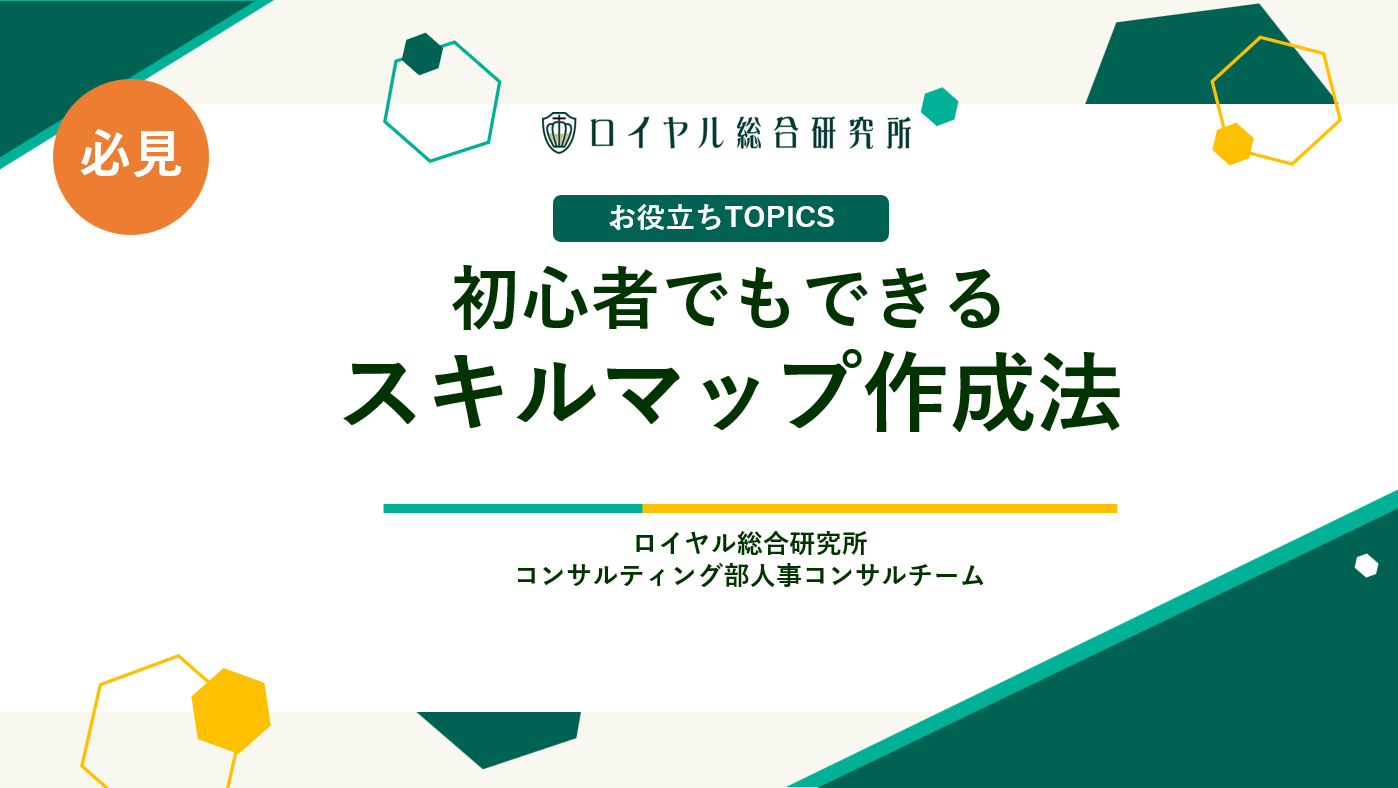
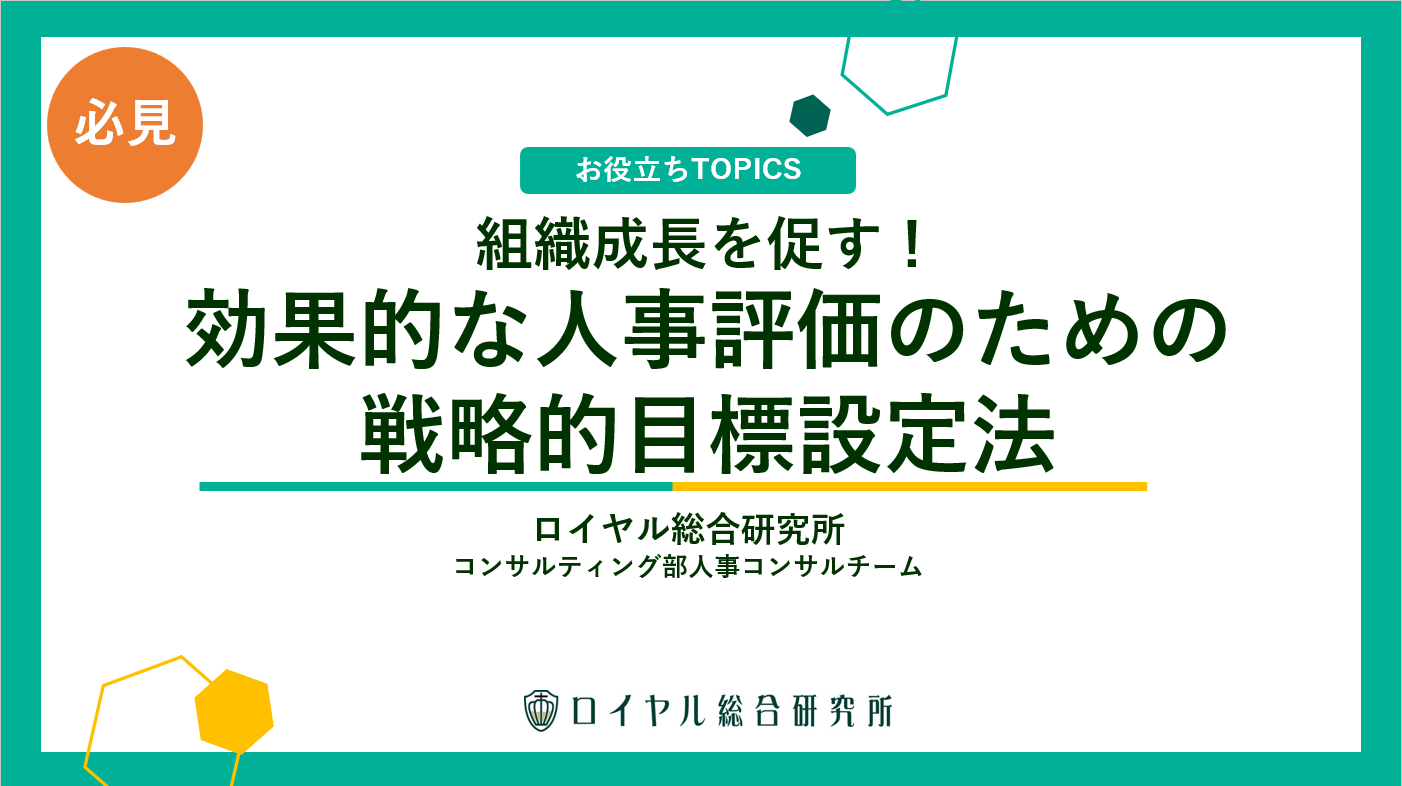


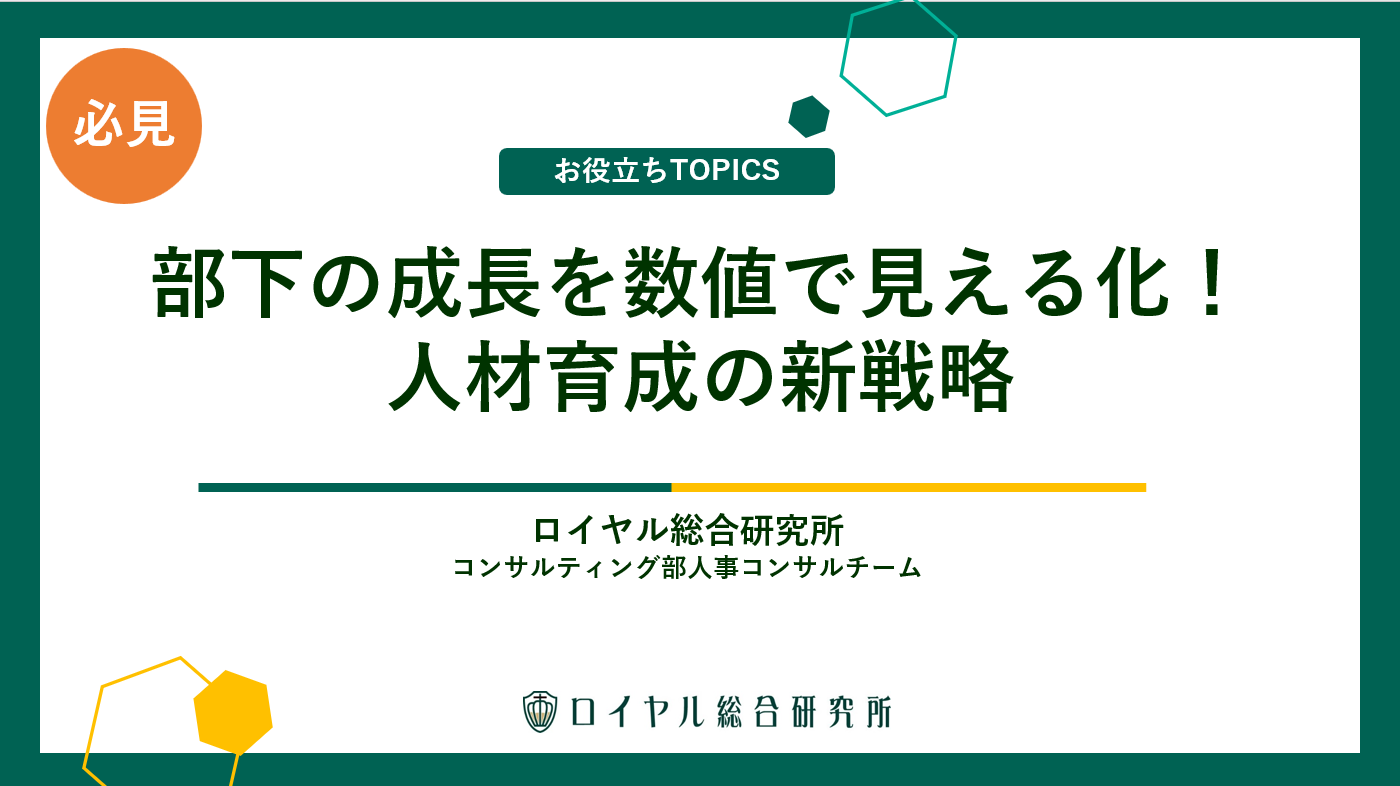
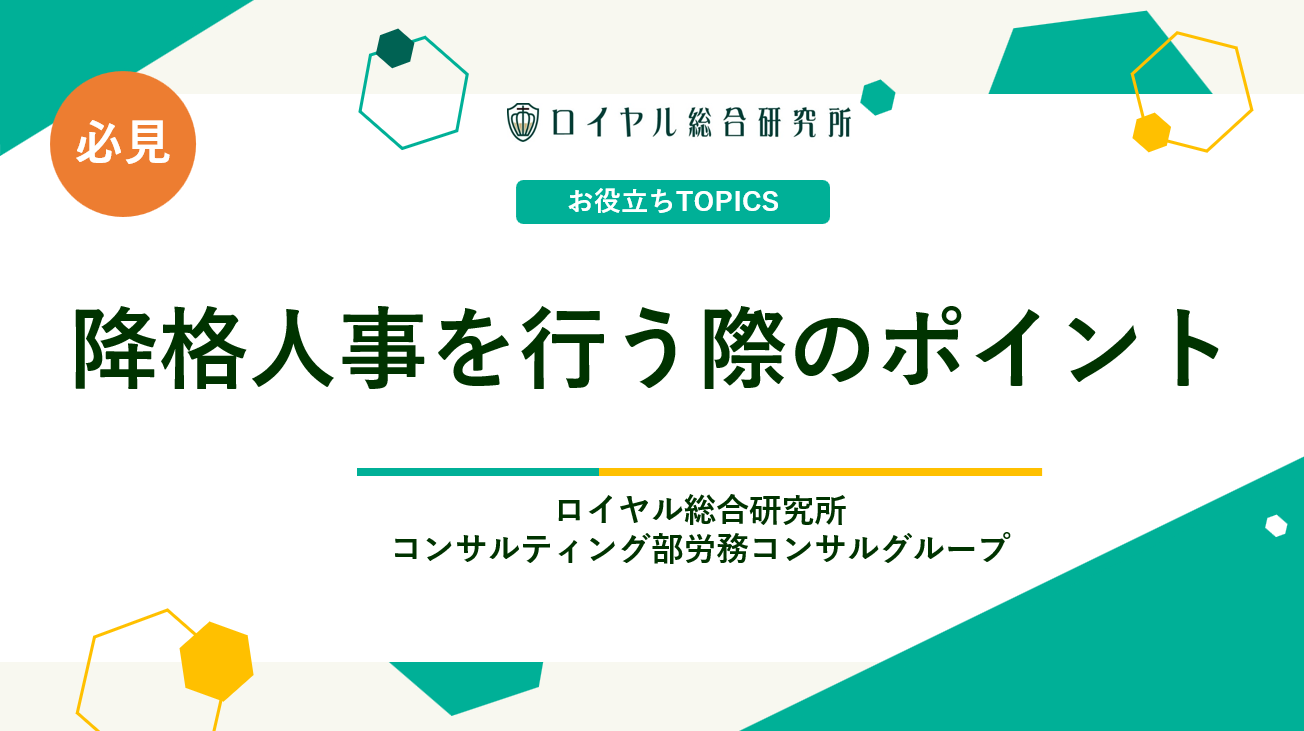
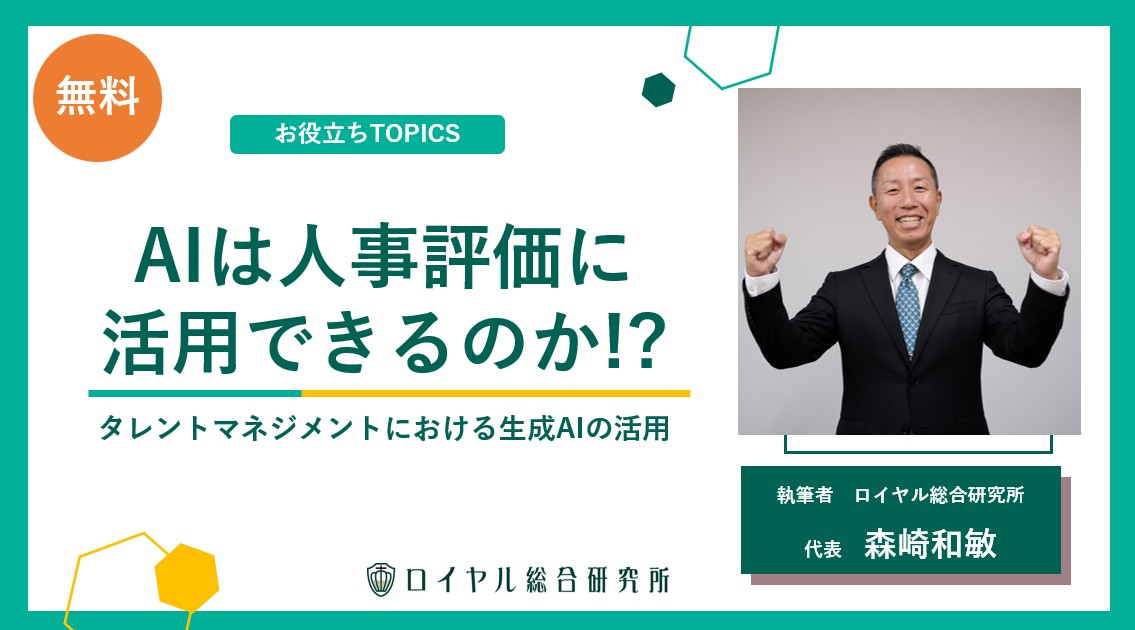

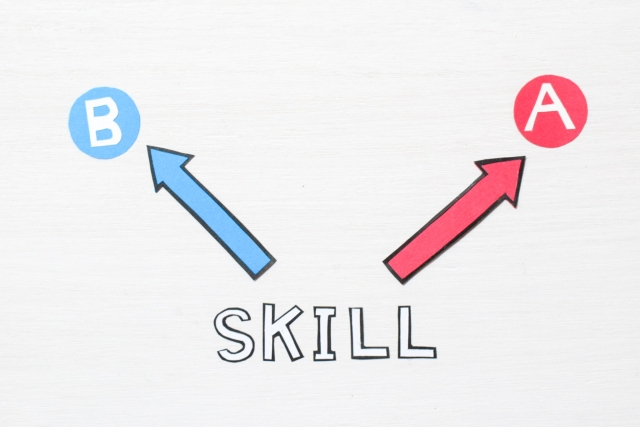


 ページトップに戻る
ページトップに戻る