目次
昇格試験の重要性
昇格試験とは?
昇格試験は、従業員が上位の職務や責任を担う準備ができているかを確認するプロセスです。単なる年功序列や感覚的な判断ではなく、試験という明確な形式を取ることで、客観的に昇格の判断を行うことができます。試験を通じて、社員は自分の現在地を理解し、成長の方向性を認識できます。また、組織としては後継者育成の観点からも計画的なキャリア設計が可能になります。
昇格試験制度を通じて、企業は将来のリーダー候補を見極め、成長機会を与えることができます。
昇格試験(技能評価)はなぜ必要?
昇格試験は、単に肩書きを与えるための試練ではなく、業務遂行能力を可視化し、適切な人材配置を実現するための仕組みです。現場のニーズに即したスキルが備わっているか、将来的なリーダーとしての素養があるかを多角的に判断することが、企業全体の競争力向上にもつながります。技能評価は、従業員の得意分野を活かす配置や、不得意分野の補強にも活用でき、より戦略的な人材運用を可能にします。
昇格試験+αを狙え!
人事評価とリンクさせる
人事評価を、昇格試験の前提資料として活用しましょう。継続的な評価データに基づき、昇格試験の対象者を選定しましょう。そして、昇格後には適切なフィードバックを行うことで試験の公平性と納得性が高まります。評価は過去のパフォーマンスを振り返るための指標であり、昇格は将来に向けた期待を測るものですが、この両者を連動させることで、より信頼性の高い人事制度となります。
人材育成とリンクさせる
人事評価と昇格試験は切り離して行うのではなく、人材育成の一貫として設計しましょう。日々の業務を通じたスキル習得、面談を通じた指導、その成果を昇格試験で測るという流れが理想です。これにより、昇格試験が「一過性の試験」ではなく、「育成の集大成」として位置付けられるようになります。育成と試験を連動させることで、従業員の主体的な学びの姿勢が促されます。昇格試験は、継続的なスキルアップを組織全体に根付かせる重要な役目があります。
効果的な昇格試験はここを意識!
昇格試験は未来評価
人事評価はあくまで過去の実績や行動に対するものですが、昇格基準は「これから担う職務にふさわしいかどうか」を評価する将来視点のものです。従って、業績評価だけでなく、リーダーシップ、論理的思考力、判断力、周囲との連携力など、多角的な視点から基準を設ける必要があります。将来のミッションを遂行できる人物かどうかを見極める目線を持つことが不可欠です。
そのため、昇格試験では、管理能力やリーダーシップ、問題解決力など「将来的に必要とされる能力」に対する評価基準を設定することが必要です。
昇格基準の見える化
昇格基準は明文化し、社内に周知しておくことが重要です。評価項目、判断の基準、試験内容などを明確にすることで、従業員の納得感とモチベーション向上に繋がります。さらに、昇格に必要なスキルや経験年数、過去の評価の傾向なども含めてガイドライン化することで、従業員は自身のキャリアパスをより具体的に描くことができます。
公平性を保つ
昇格試験には、「公平性」が必要不可欠です。以下の取り組みを必ず行いましょう。
・事前に試験の内容や日程、評価基準を公開する
・実施者と評価者を分離する
・会社と社員の相互フィードバックを行う
こうした取り組みにより、公平性と透明性を確保できます。加えて、過去の昇格実績の傾向を社員に開示するなどの工夫も、試験制度の公正さへの信頼を高めます。組織全体で「公平な評価・試験」を文化として根付かせることが大切です。さらに、試験の実施結果に対して社員からフィードバックを募る仕組みを設けると、制度改善の材料としても機能し、従業員の声を反映した持続可能な人事制度が実現できます。
フィードバックまでが昇格試験
試験後の適切な評価
昇格試験後は、合否だけでなく、その理由や評価されたポイント、今後の課題を丁寧にフィードバックすることが大切です。このフィードバックがあるかどうかで、社員の納得度や次への挑戦意欲が大きく変わります。将来的な育成にもつながるため、個別面談の場などを通じて誠実に伝えることが求められます。
成長する機会の提供
試験に不合格だった場合でも、次回に向けた改善ポイントや具体的な行動計画をフィードバックとして提示することで、従業員の自己成長を促進できます。試験が成長の場であると理解されれば、社員は結果に一喜一憂することなく、長期的な視野でキャリアを考えるようになります。さらに、失敗を恐れず挑戦できる組織風土を醸成することが、長期的には人材の厚みを増す鍵となります。
ありがちなミスと注意点
昇格試験にありがちな問題
多くの企業は、昇格試験で以下のような問題を抱えています。
・評価者の主観による選抜
・試験内容が現場の実務と乖離している
・結果が適切にフィードバックされない
こうした問題は、従業員の信頼を損ね、組織の不満要因となります。これを防ぐには、試験制度の見直しや、評価者の教育が不可欠です。また、評価対象の明確化や、実際の業務との整合性があるかを確認することで、より現場に即した昇格試験を実施することができます。さらに、昇格の決定プロセスにおいては関係部署との連携や、評価の透明性を高める施策も求められます。
管理職の試験ではここに注意!
「仕事ができる」「高い業績がある」だけでは、管理職にふさわしいか判断することができません。管理職の昇格試験では、実務能力だけでなく、部下の育成力やチーム運営力も重要な評価要素です。加えて、コンプライアンス意識やメンタルケアへの対応力など、近年重視されるソフトスキルも含めて、多角的に評価することが望まれます。組織を牽引する立場にふさわしい人材かどうかを見極めるためには、長期的な視野に立った評価が不可欠です。
昇格後フォローにHRvisの活用を!
昇格試験の実施後、「昇格させて終わり」になってしまっていませんか?
本来、昇格は新たなスタートであり、その後のフォローや育成こそが重要です。
HRvisなら、1on1ミーティングの内容をクラウド上で記録できるため、現在の上司と昇格後の新たな上司との引継ぎがスムーズになります。これにより、従業員のフォローや育成に注力できます。今までの評価記録をもとにした目標設定、上司からの具体的なアドバイス、面談履歴による振り返りなど、昇格後の成長を確実に後押しします。
HRvisは「昇格がゴール」ではなく「成長のスタート」に変える仕組みを提供します。
ロイヤル総合研究所 コンサルティング部

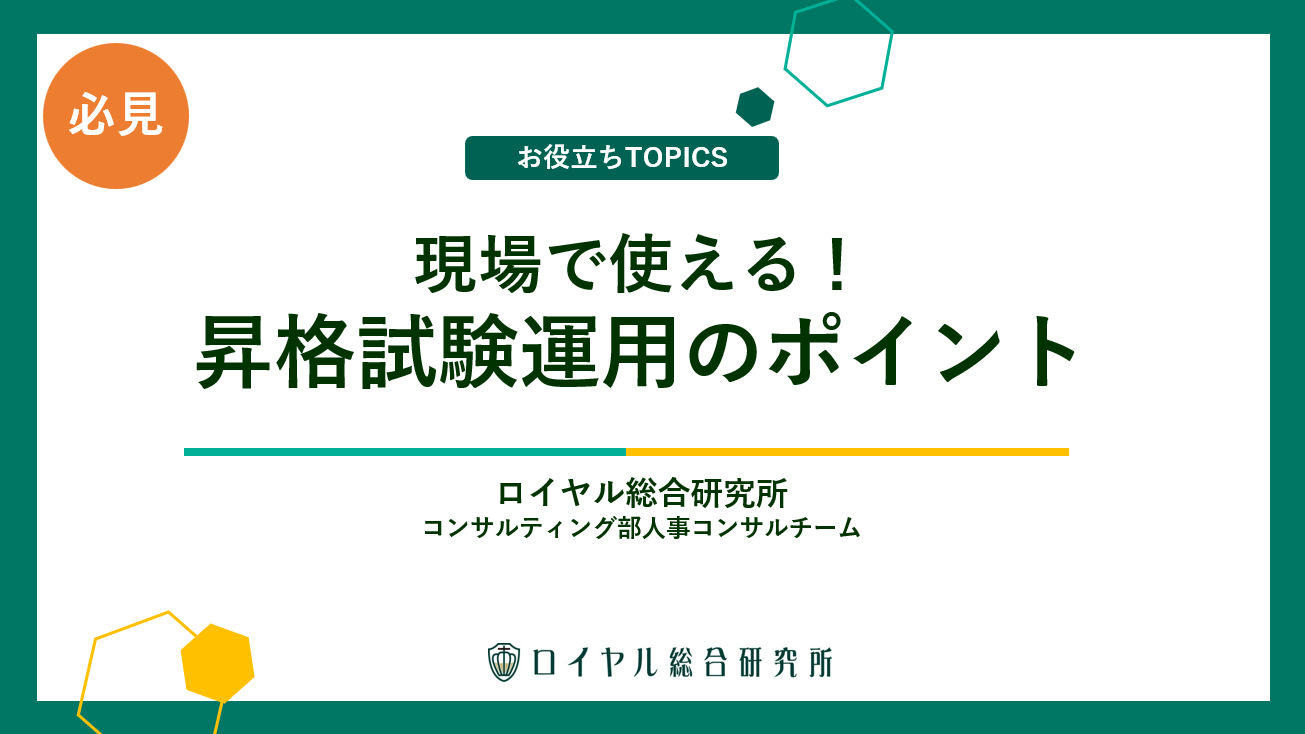
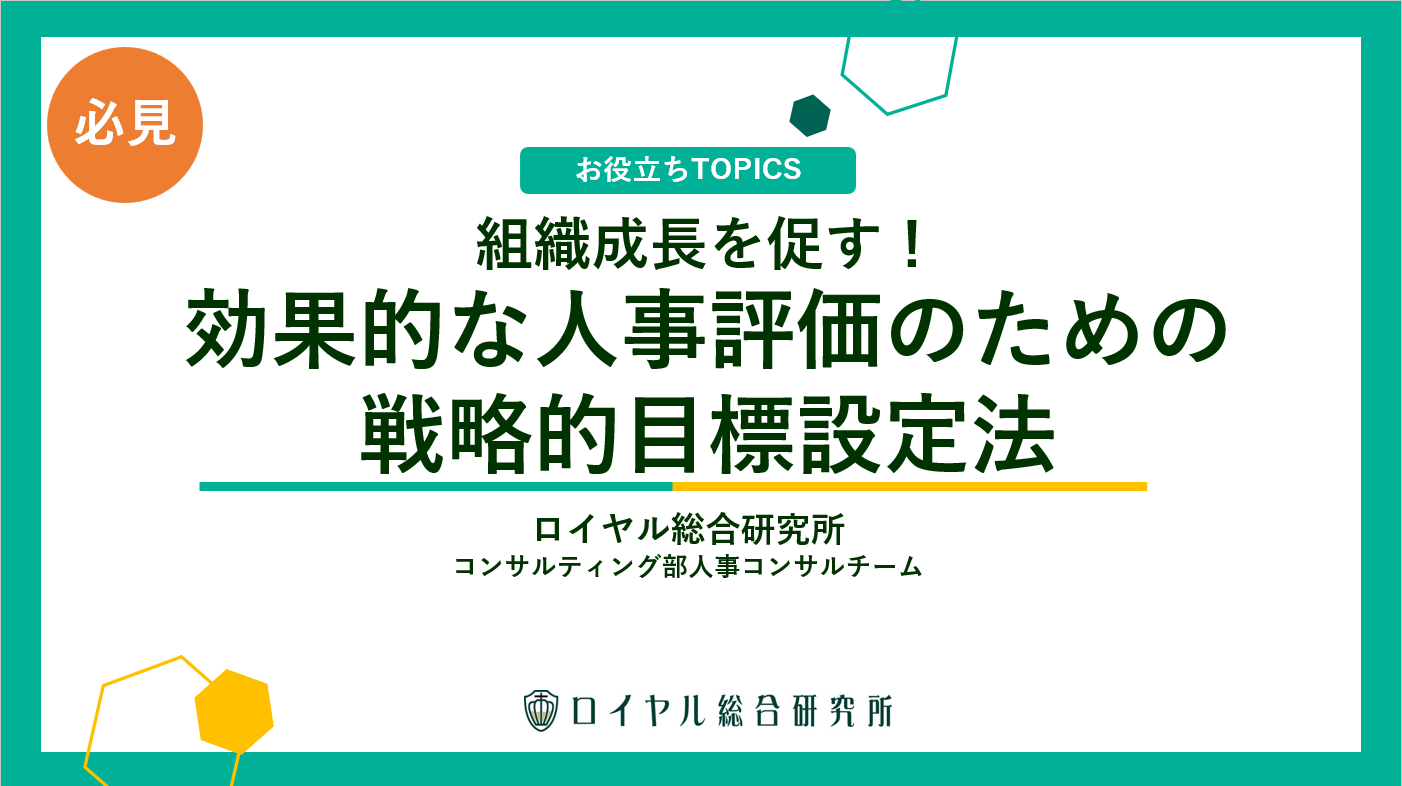
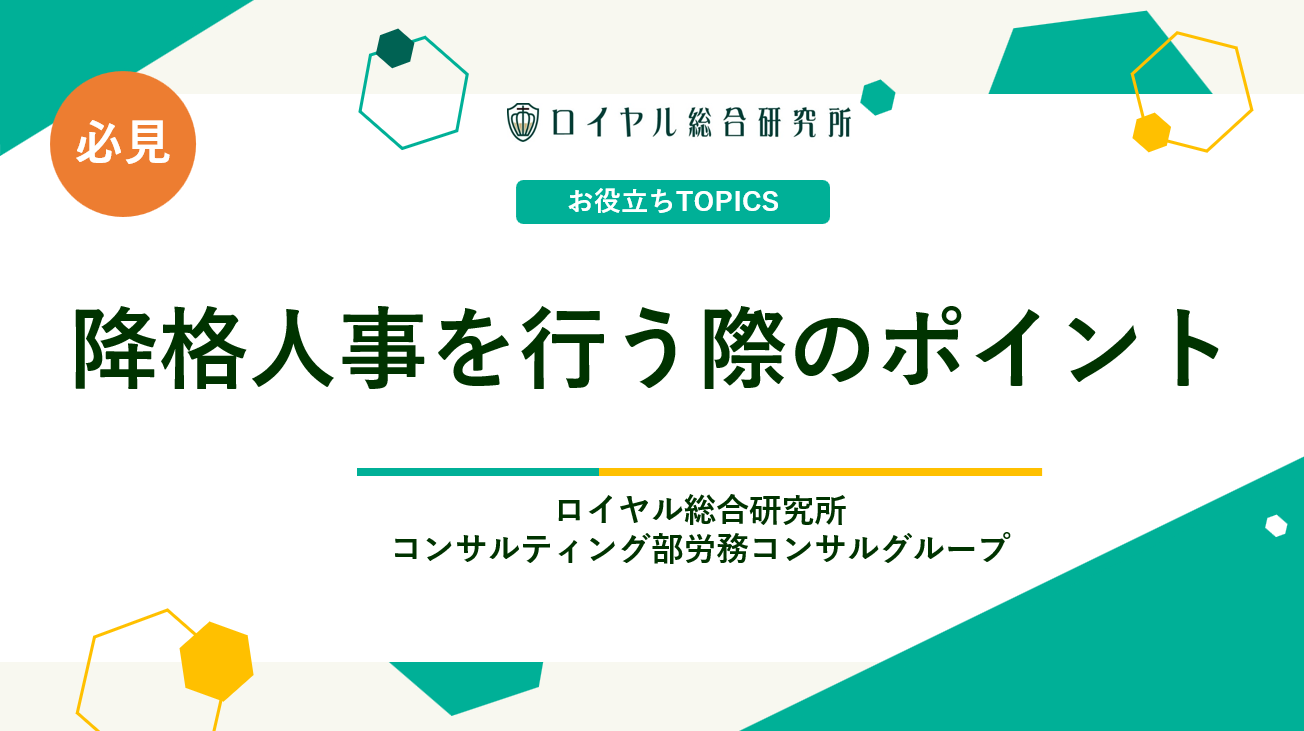
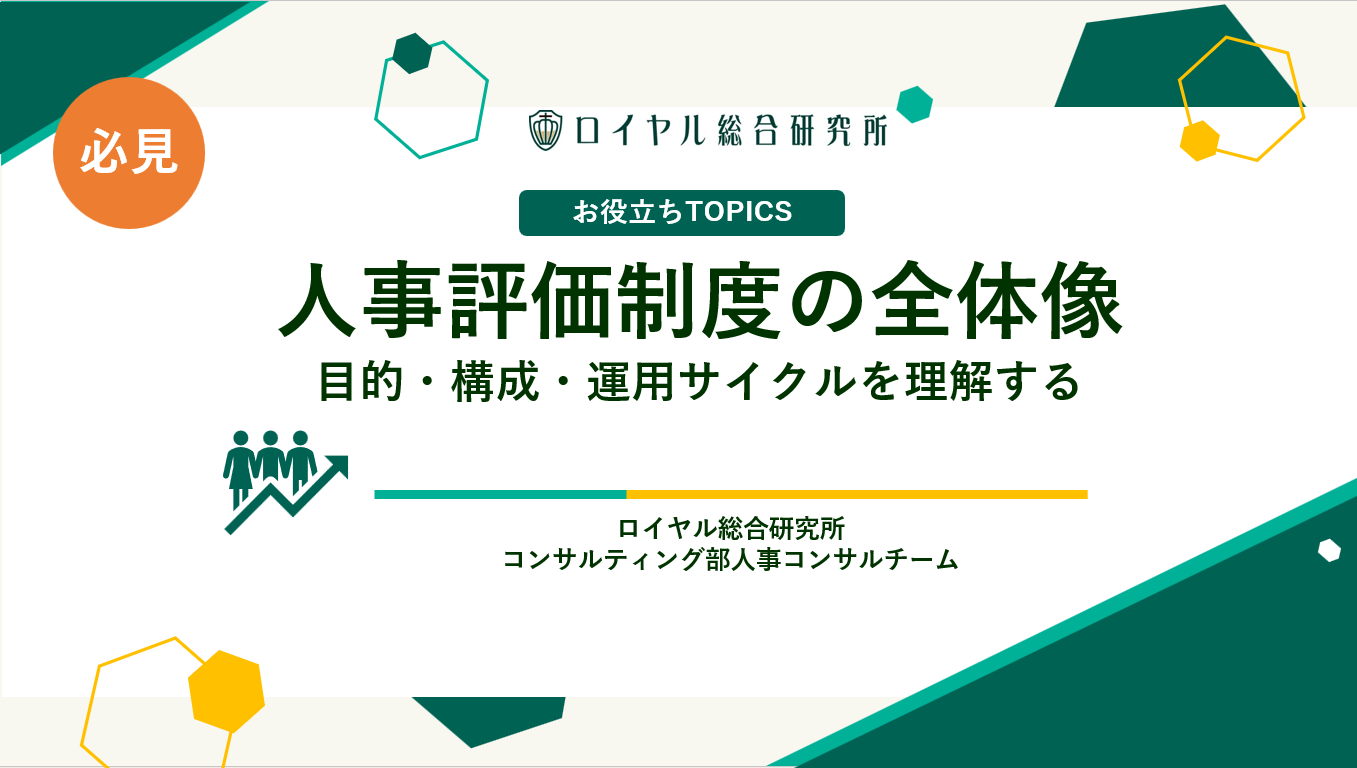
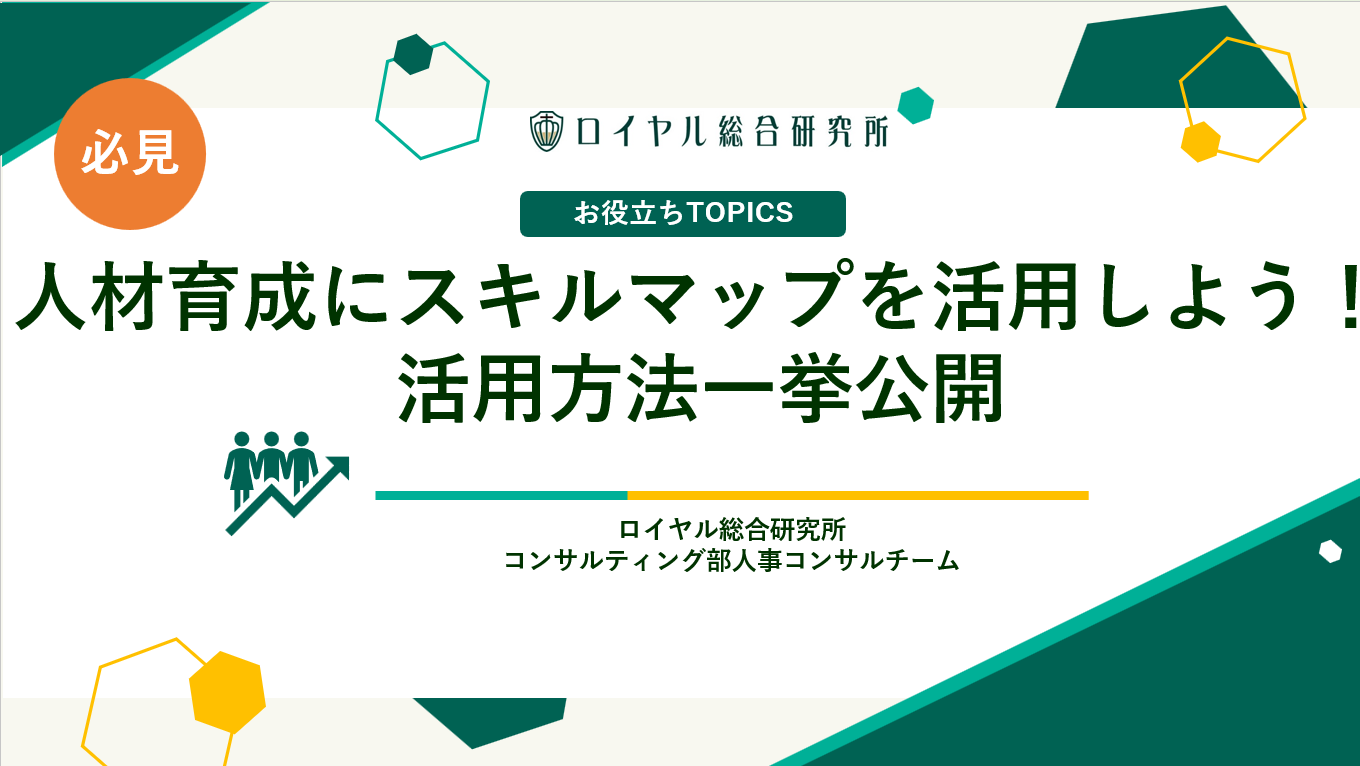
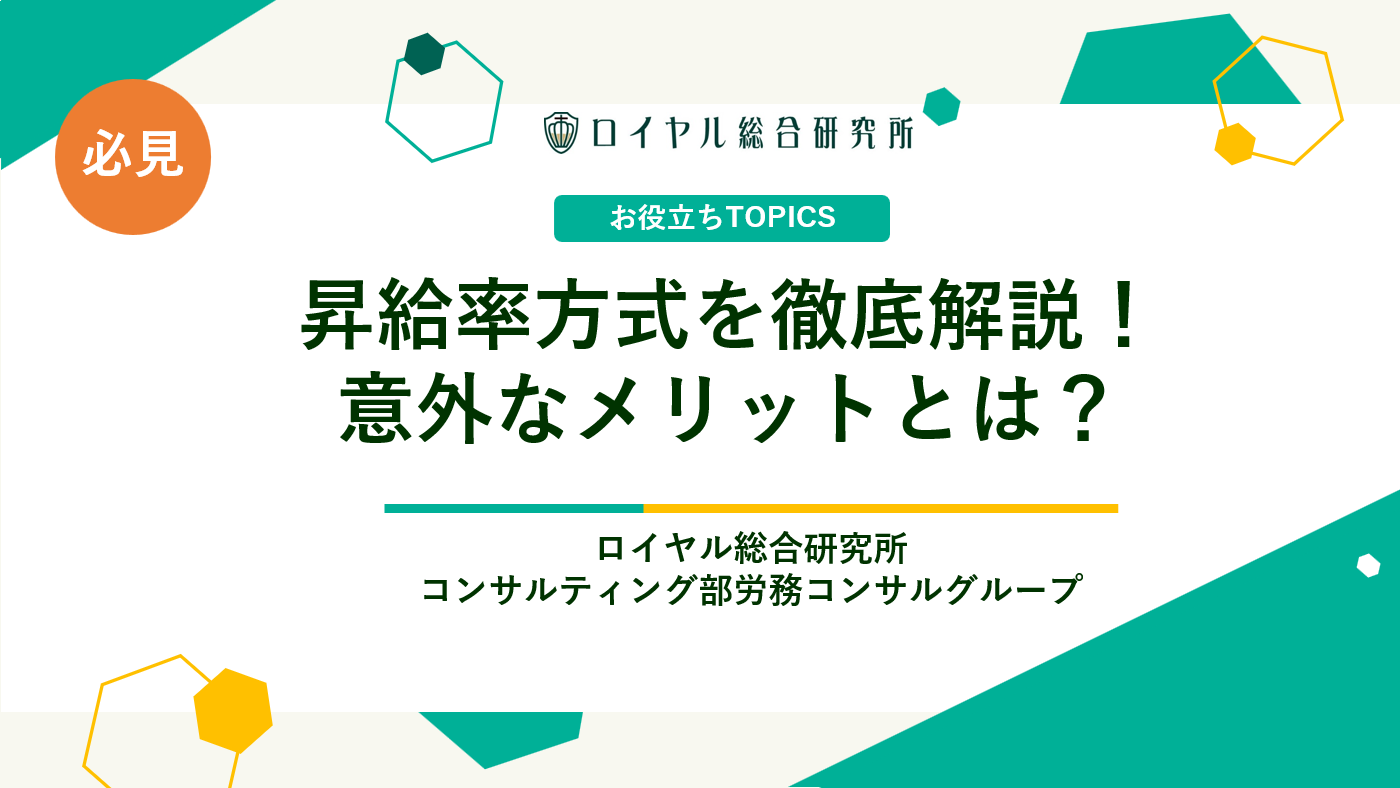
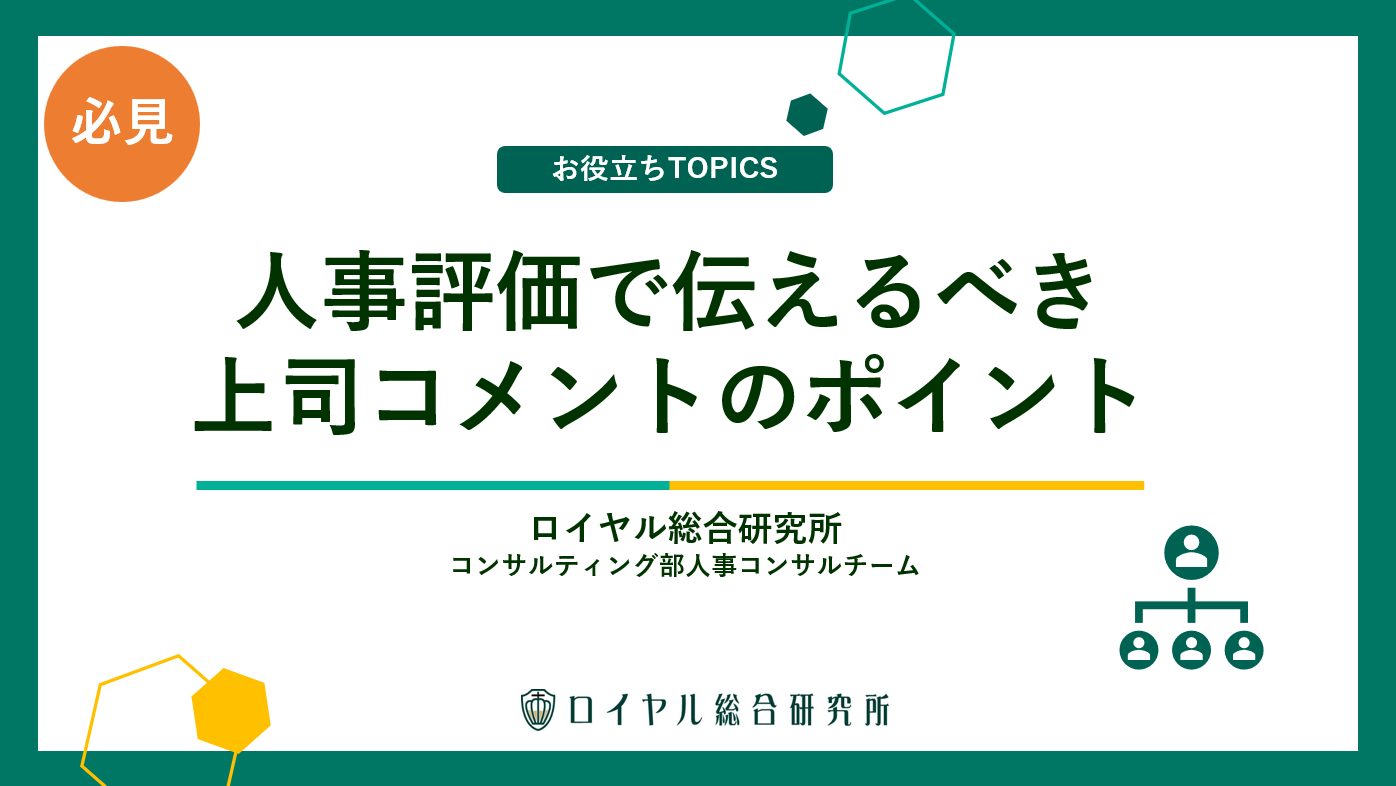
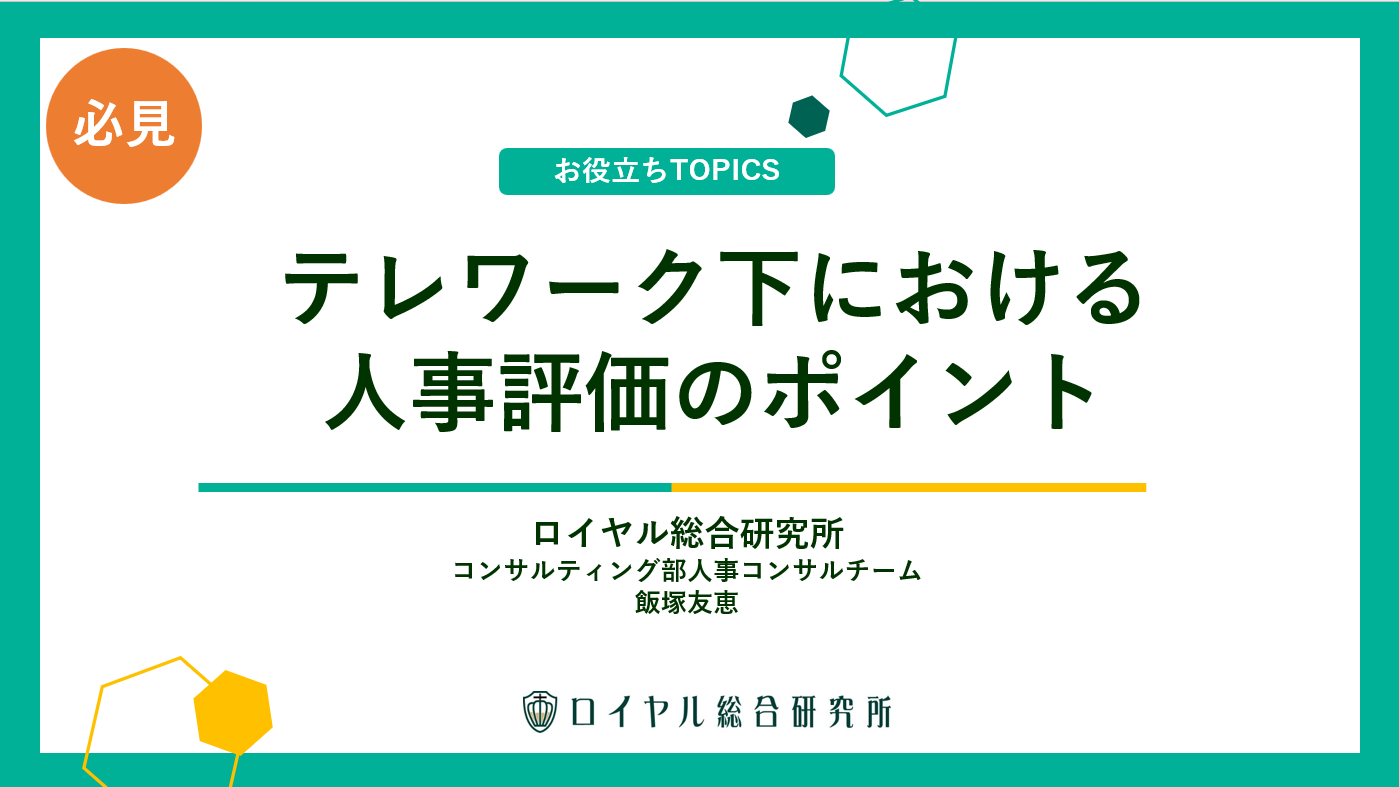
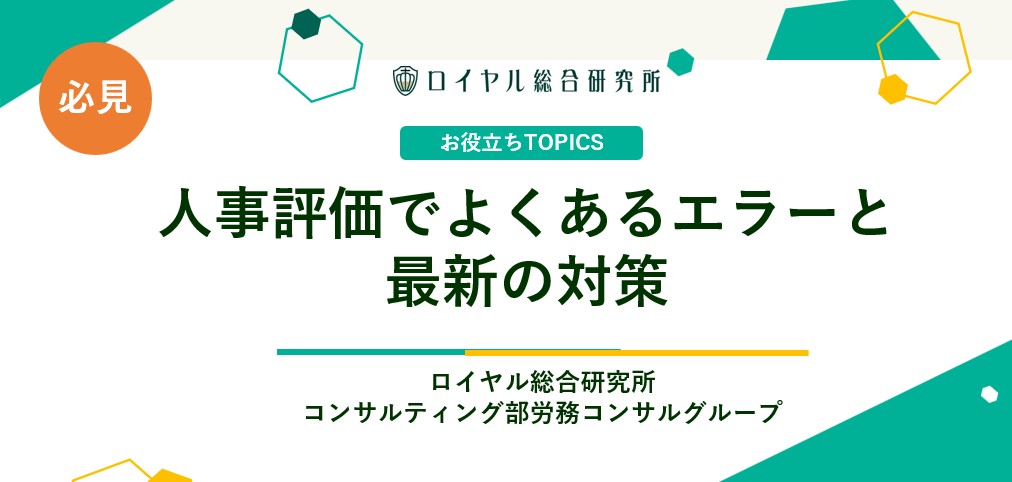
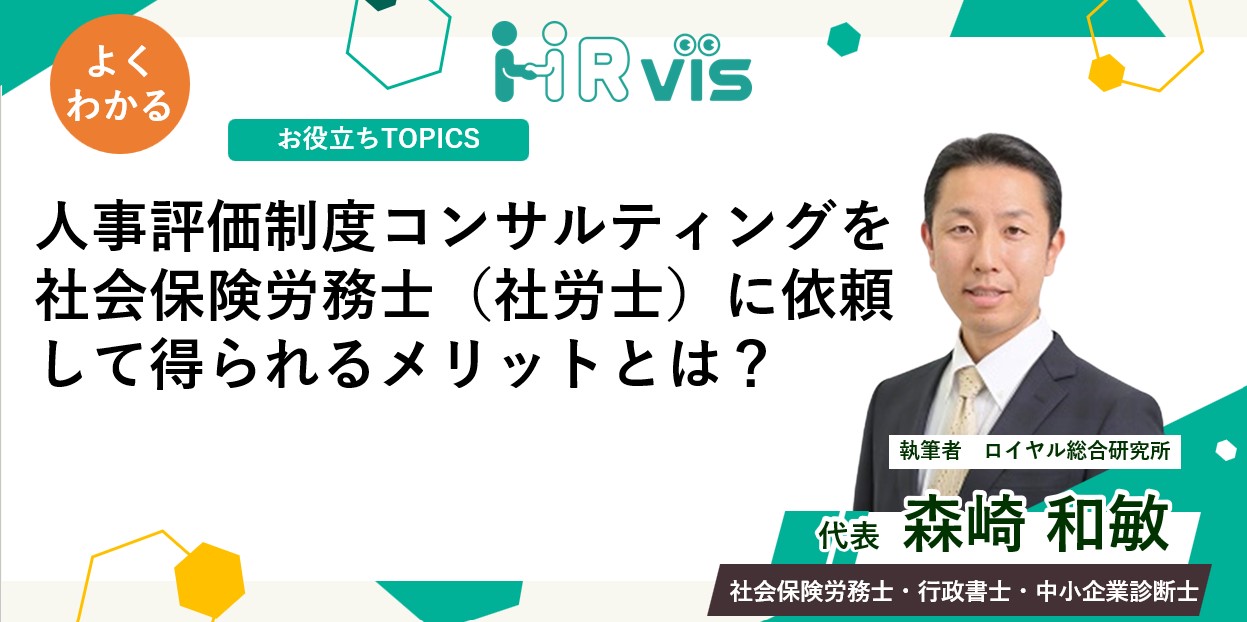
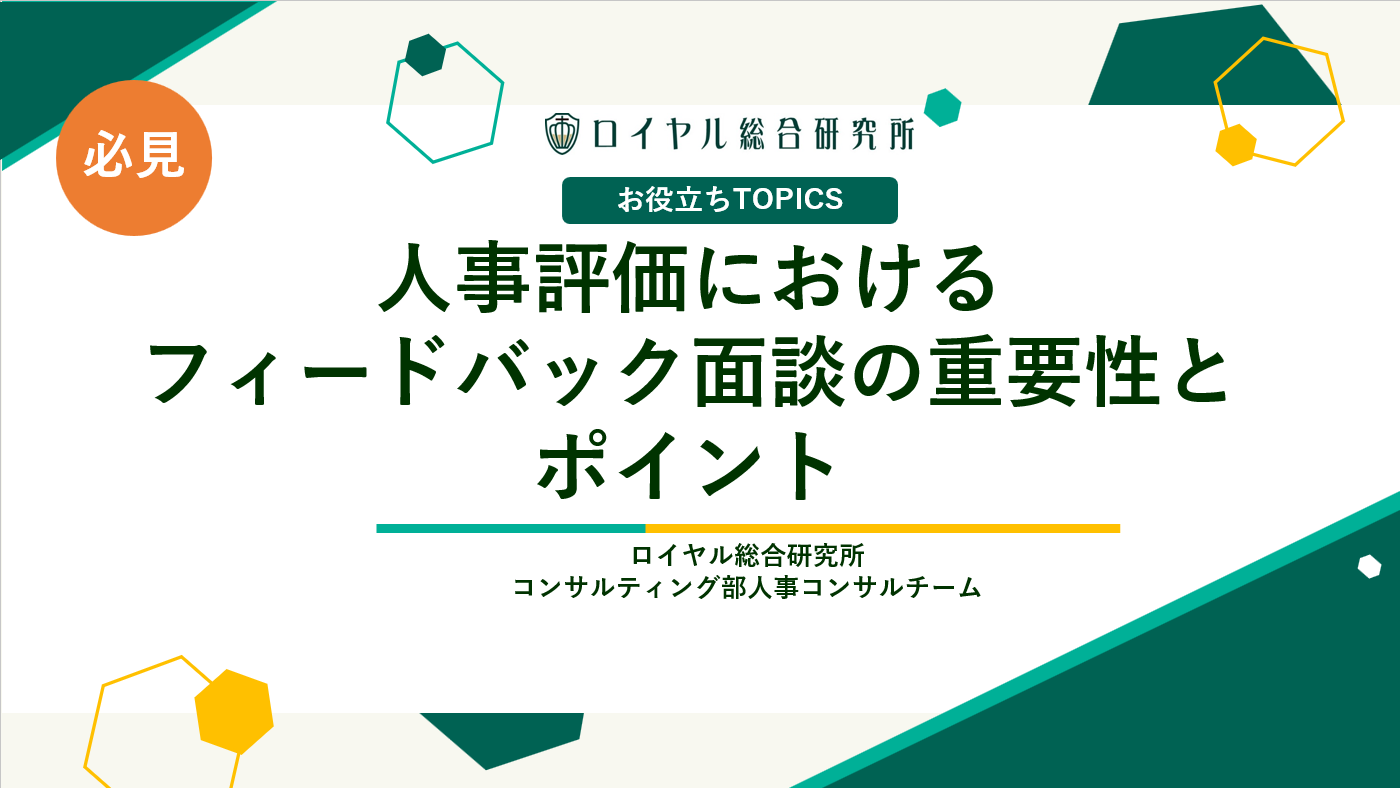



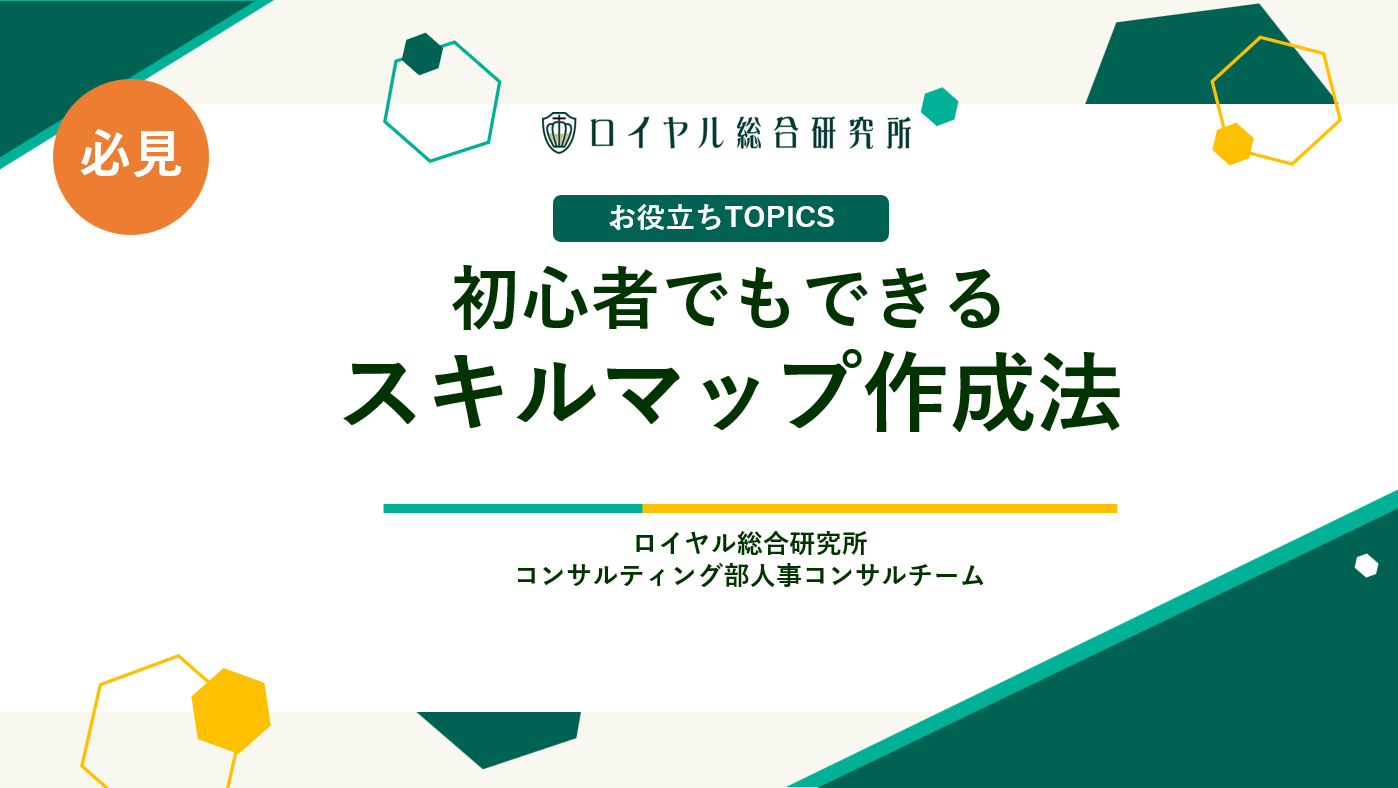


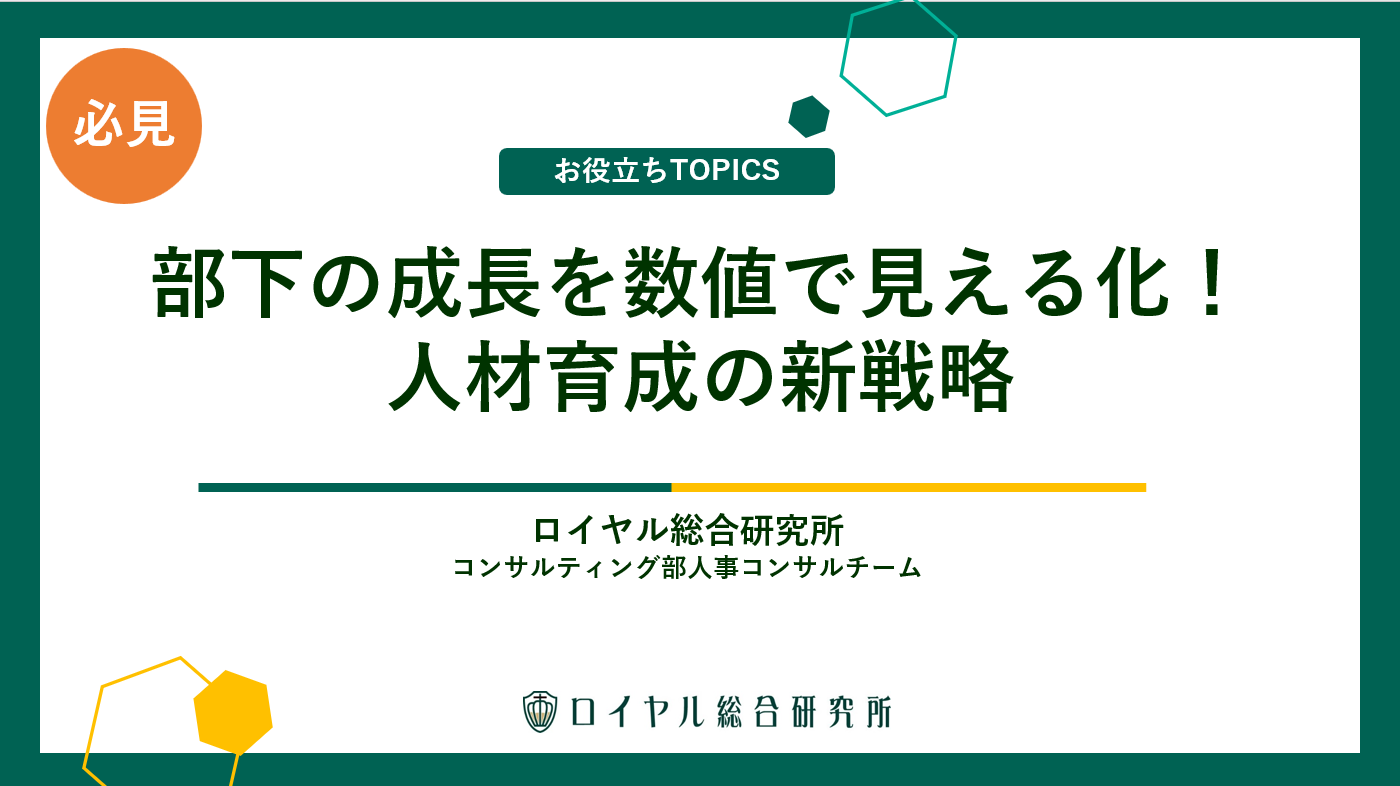
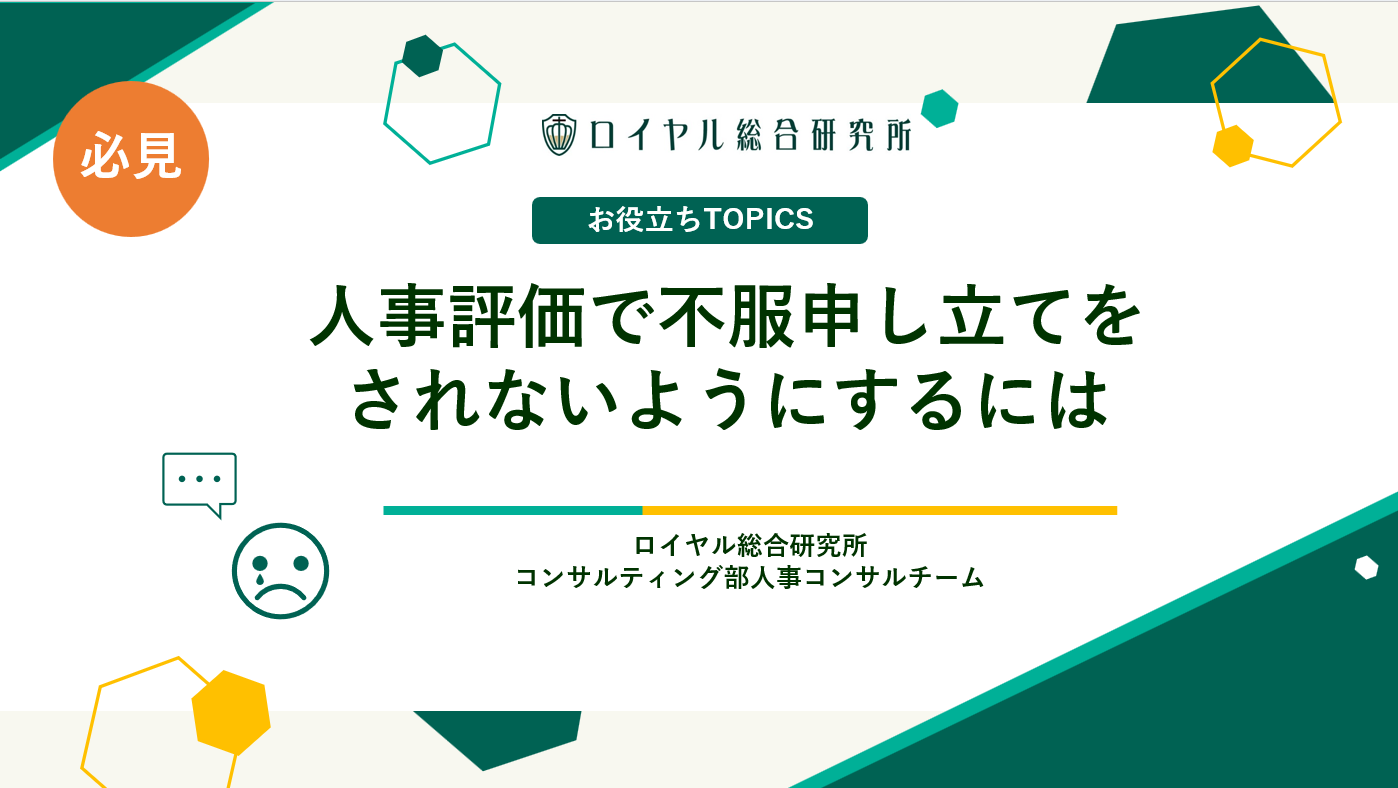
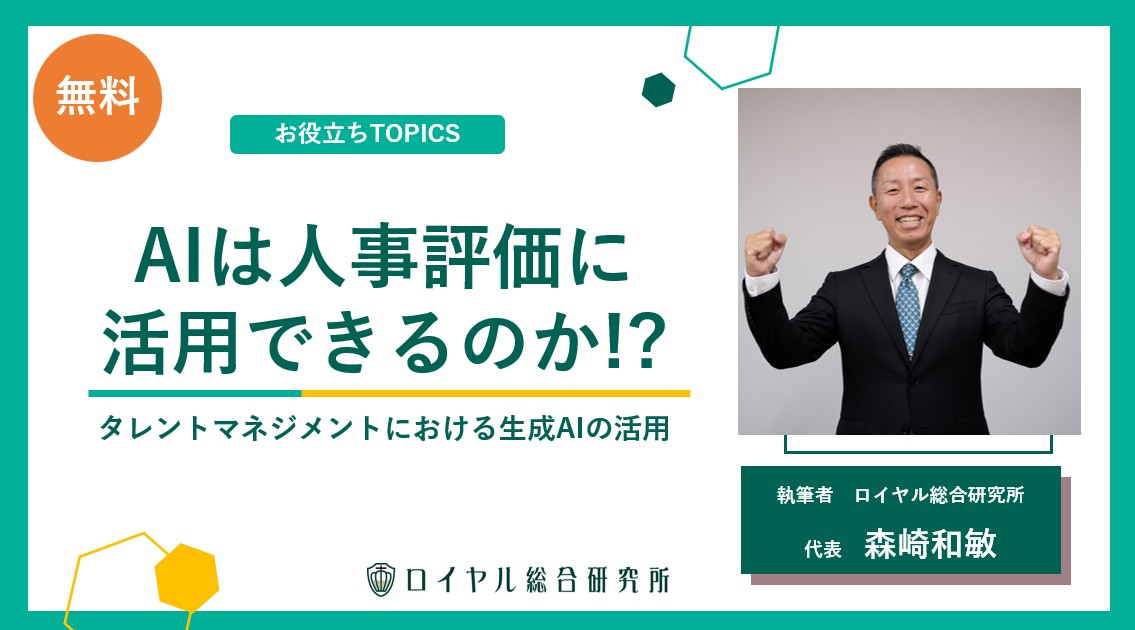

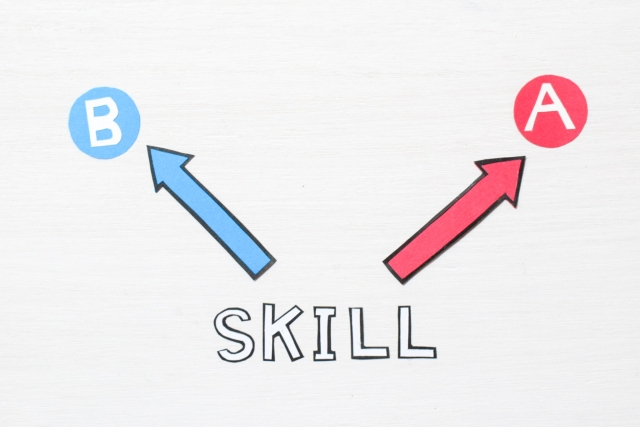


 ページトップに戻る
ページトップに戻る