従業員を雇用している企業にとって、人事評価制度の設計は必要不可欠です。何年も社労士をやっていると多くの企業様の人事評価制度を目にします。似たような人事評価制度が多いのですが、大手企業や老舗企業の人事制度によくある事例として、「人事評価制度が複雑すぎる」ということがあります。しかし、そんな複雑な制度は社員が理解できません。私の経験則では、制度が複雑になればなるほど社員が制度を理解できなくなり、制度が形骸化していきます。
今回のコラムでは人事評価制度の設計時や改良時の注意点をお話したいと思います。
目次
人事評価制度とは
人事評価制度とは、労務制度、採用、人材育成など人材管理に関する制度全般を指しますが、評価制度という場合にはその中でも特に従業員の評価制度や報酬、等級に関する制度のことを指すことが一般的です。日本の人事評価制度は一般的に「業績面の評価」「能力面の評価」「行動(意欲)面の評価」の3種類を区分して評価することが多いですが、これらの評価に加えて各企業の実態に応じて様々な改良を加える場合がほとんどです。例えば、360度評価を取り入れたり、期間限定で特別に販売したい商品の売上によってボーナスポイントを加算したり、あるいは社内でチームや同僚に貢献した人に「ありがとう」の意味を込めてサンクスポイントを付与して評価ポイントを増やしたり、業務の難易度によって評価点数をレベル分けしたりと言ったような感じです。
人事評価制度の目的
人事評価制度の目的は「社員の能力向上」と「社員の意欲向上」です。そのため、企業が成長していくために、人事評価制度の設計は必要不可欠になります。
複雑な人事評価制度の弊害
人事評価制度は各企業で独自の評価体制を設計することができます。しかしそのために、制度が複雑化してしまい、わかりづらくなっている場合も多くみられます。何年も人事評価に携わってきたコンサルタントや人事担当者は、制度に慣れているため制度が複雑になってわかりにくいことに気づかないのです。初めて人事評価制度の説明を受けたときの難しさを忘れてしまっているのです。そんな一部の人しか理解できないような制度を導入して運用しても本来の目的を達成することはできません。
複雑な制度は、社員が理解できないだけでなく、以下のような弊害を生みます。
・上司が部下に評価結果のフィードバックがうまくできない。結果として部下も理解できず納得できない。
・制度の複雑すぎて正しい運用ができない。
・評価点の算出が複雑で一部の人しか計算できない。
・評価制度の運用に必要以上の時間がかかる。
人事評価制度設計のポイント
これらの問題は、人事評価制度の目的や効果を損なうだけでなく、社員の不満や不信感を生み出し、組織の風土や文化に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、私は人事評価制度は改良を重ねて複雑にするよりも、シンプルで明確なものにすることが望ましいと考えています。
○ 評価基準は組織のビジョンや戦略に沿って設定し、社員に周知徹底する
○ 評価項目は必要最低限に絞り、社員の役割や責任に応じて適切に設定する
○ 評価方法は簡潔で効率的なものにし、評価者の能力や教育も重視する
○ 評価結果はタイムリーかつ具体的にフィードバックし、社員の成長やキャリア開発に活用する
シンプルで明確な人事評価制度は、社員にとっても評価者にとってもメリットがあります。社員は自分の評価基準や目標を理解しやすくなり、自己管理や自己改善に励むことができます。評価者は評価作業の負担を軽減し、より質の高いフィードバックを提供することができます。また、シンプルで明確な人事評価制度は、組織全体のコミュニケーションや協力を促進し、組織のパフォーマンスや競争力を高めることにも寄与します。
人事評価制度は、企業の成長や変化に合わせて見直しや改良をする必要があります。しかし、それは必ずしも複雑化することを意味しません。むしろ、シンプルで明確な人事評価制度を目指すことが、より効果的で持続可能な人事管理につながると私は信じています。
人事評価制度の設計はHRvisをご活用ください
人事評価についてお悩みの中小企業経営者の方は少なくありません。しかし、既存のサービスでは自社の事業体制に合わない、人事評価制度についてシステムで構築するのは難しそう、と考え、導入せずに終わってしまいます。
「HRvis」は、人事のプロである社会保険労務士と、システムのプロが共同開発した、クラウド型タレントマネジメント人事評価システムです。スキルマップを活用した社員のタレント管理自社に合わせた人事評価制度のカスタマイズが可能です。また、他の人事評価サービスにはない、賃金・賞与査定機能も取り揃えております。
人材評価の方法についてお悩みの方は、ぜひ人事評価システムの導入をご検討ください!
ロイヤル総合研究所
コンサルティング部


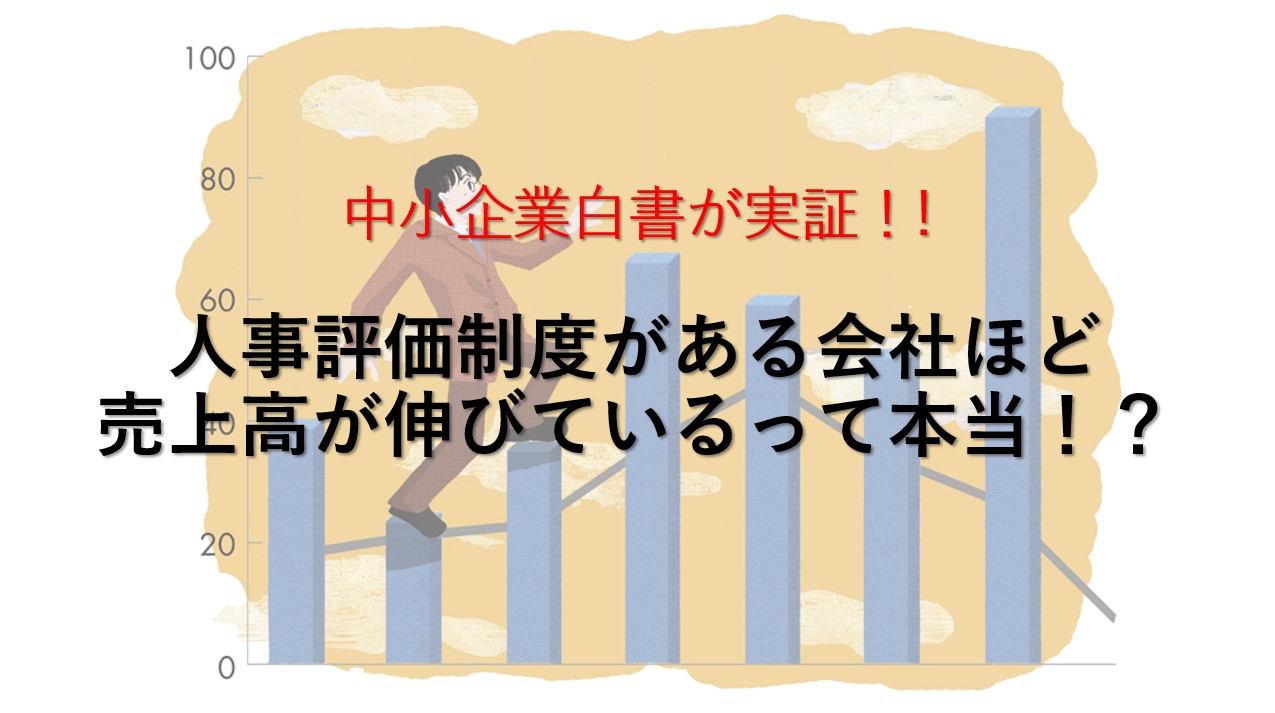
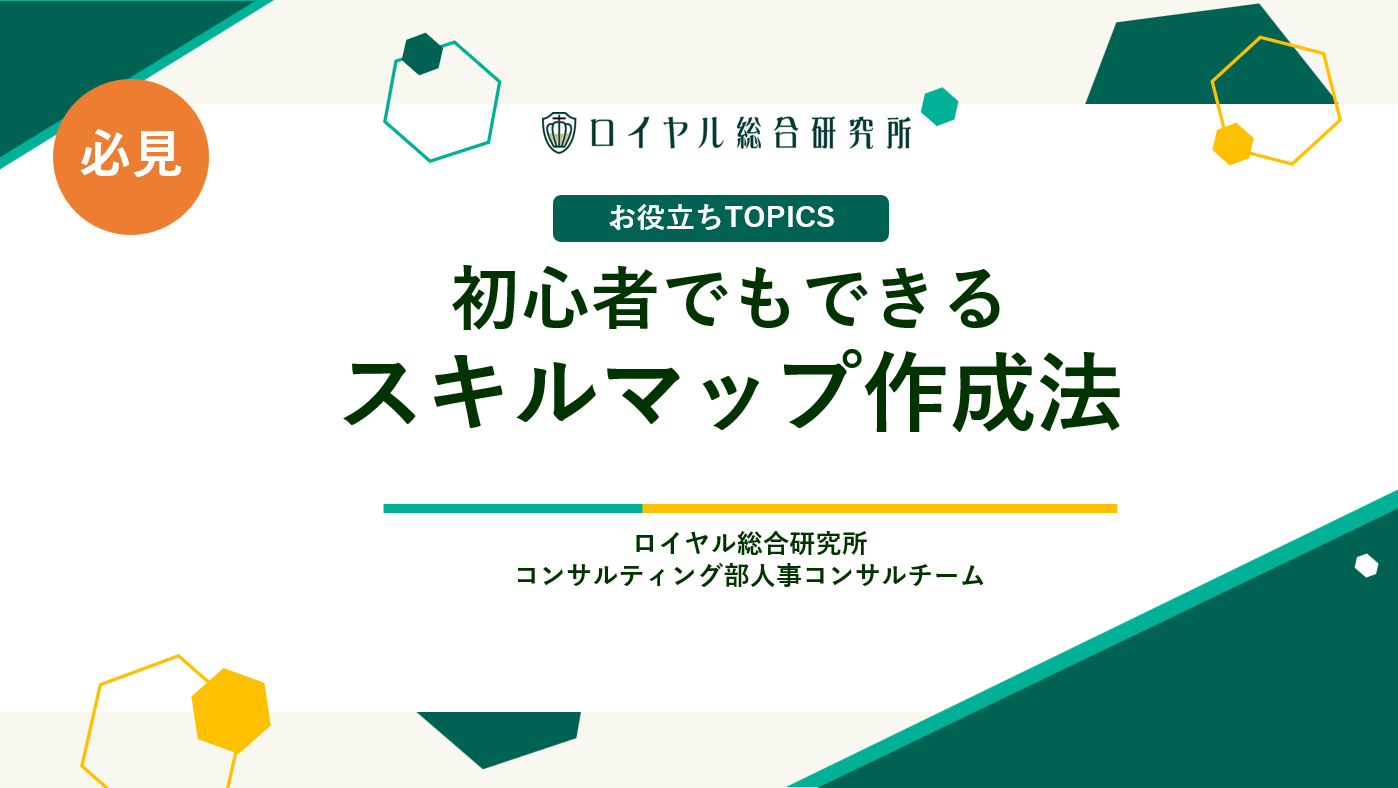
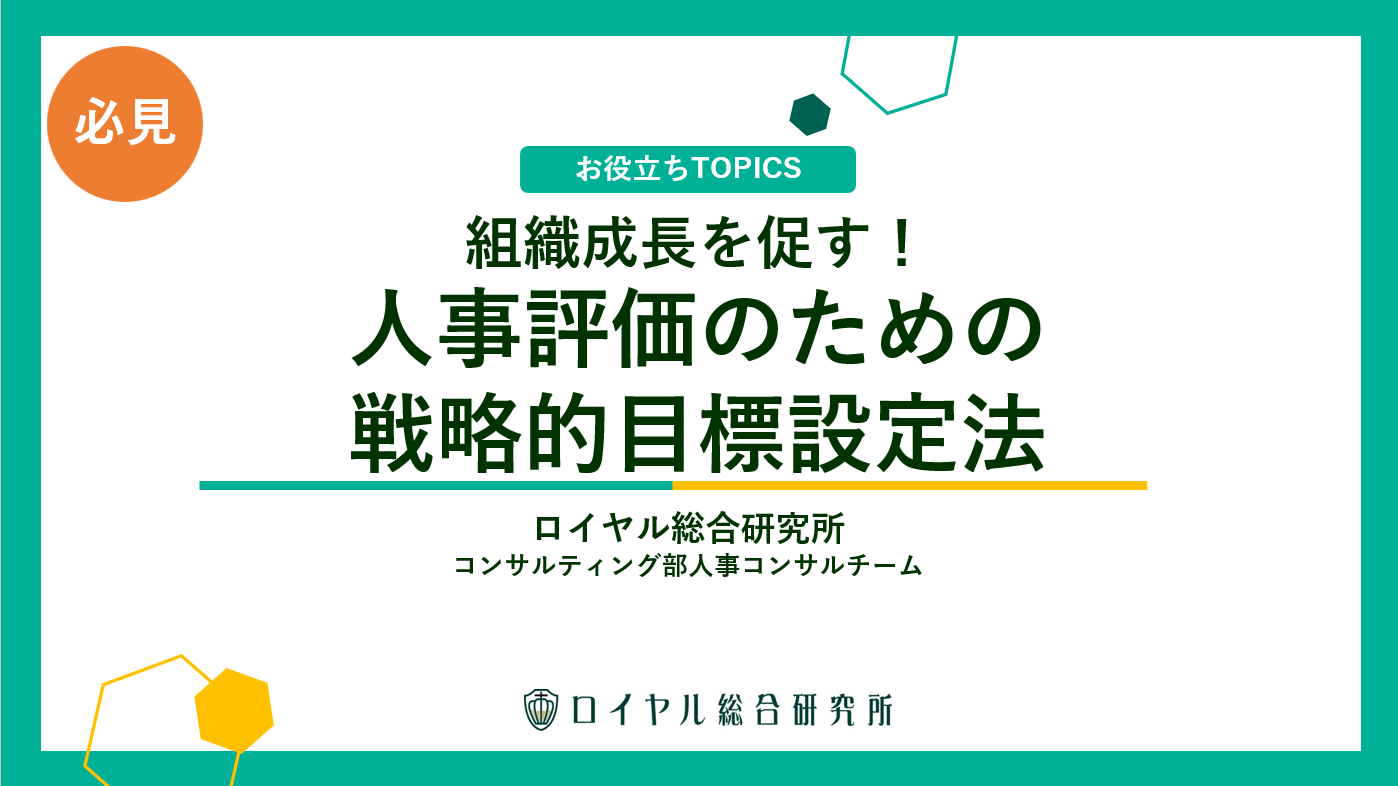
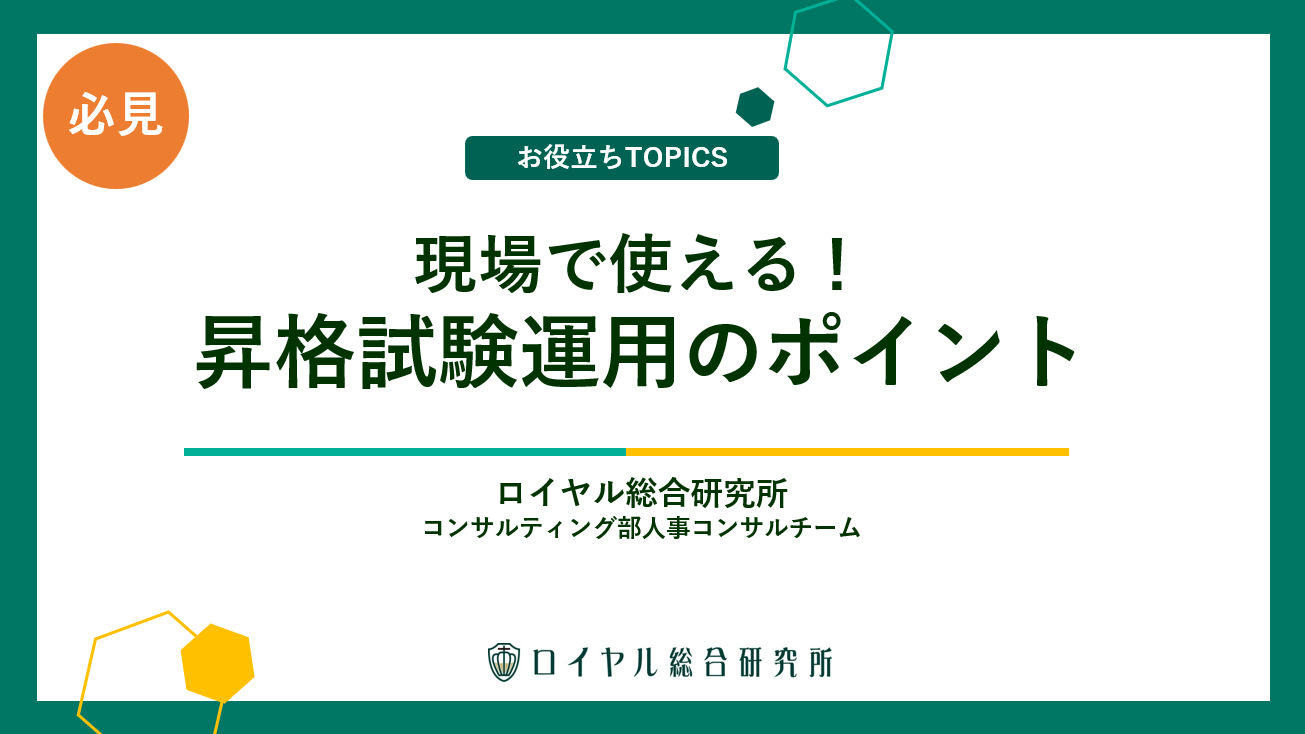
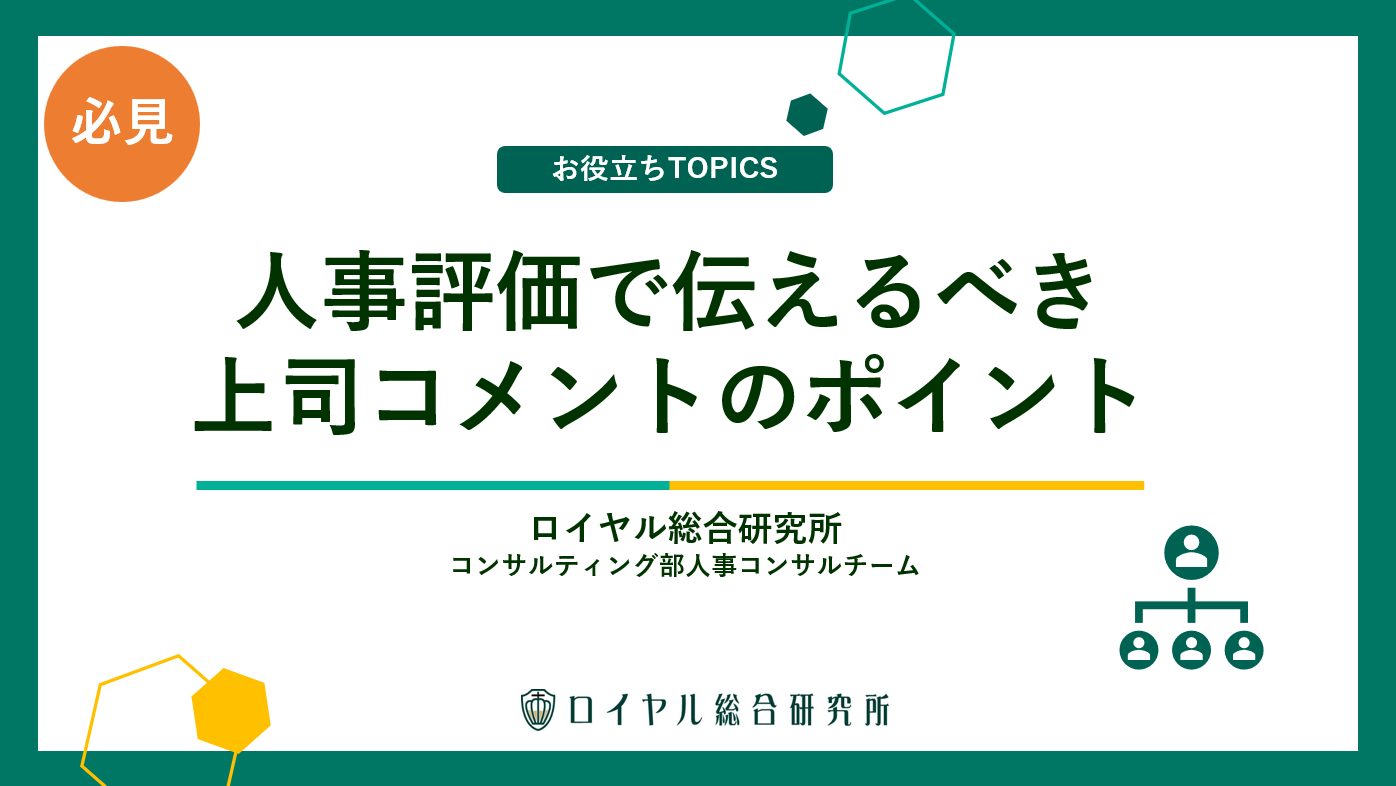
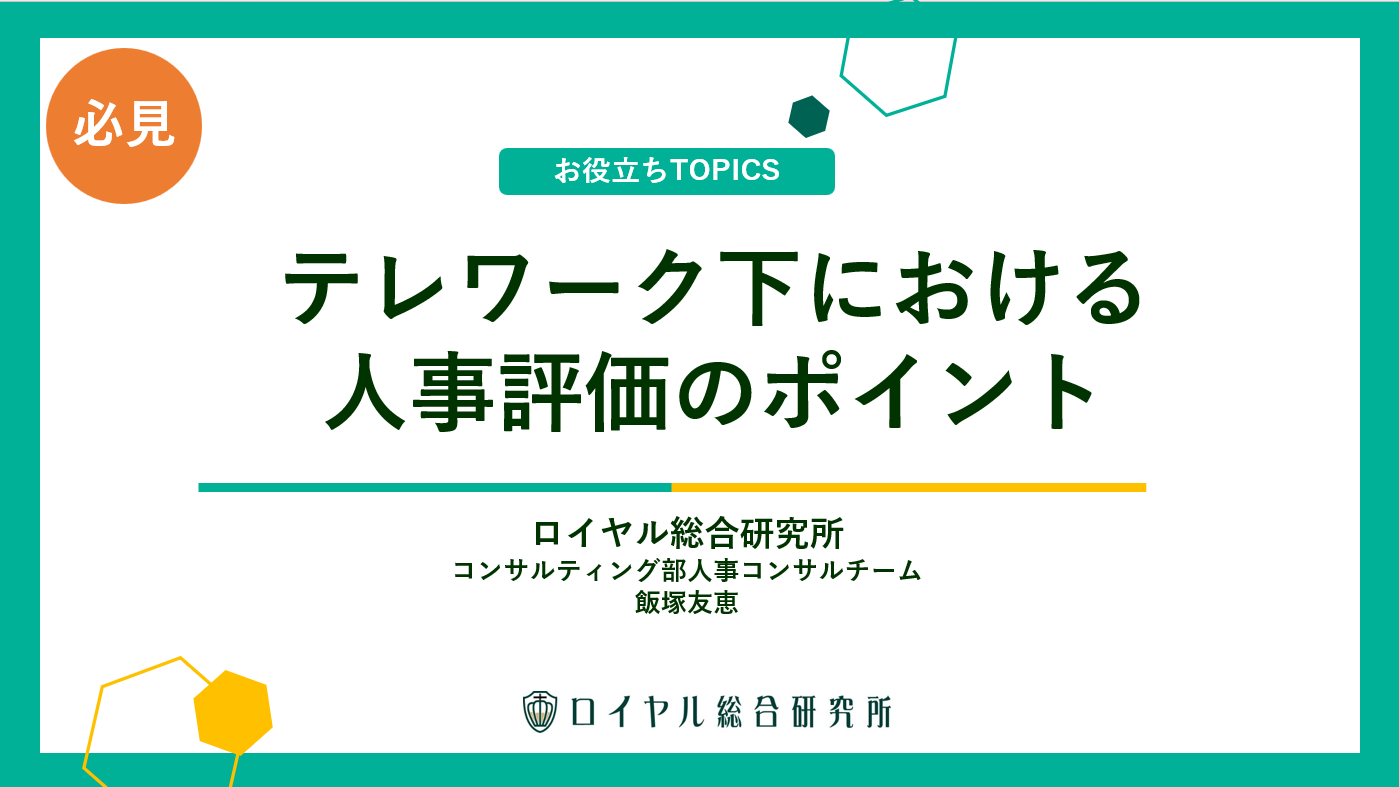
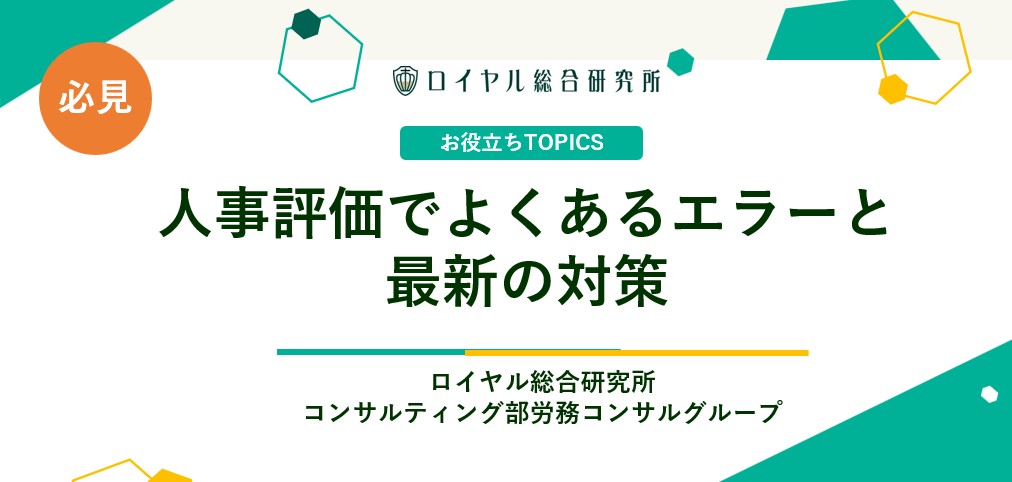
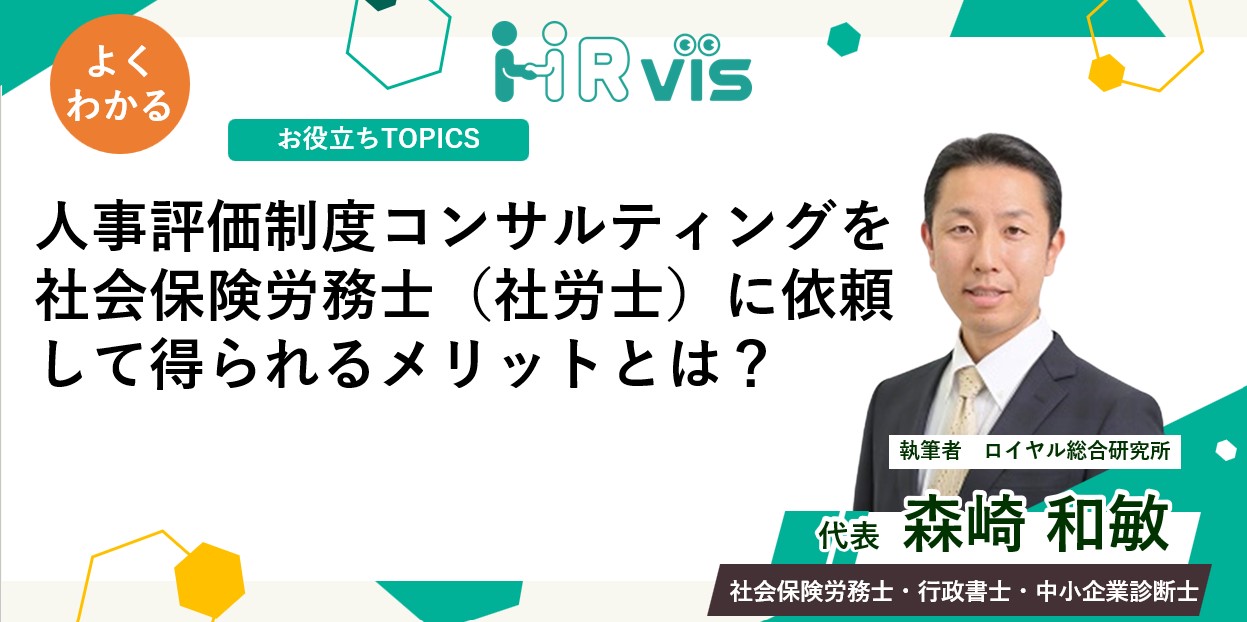
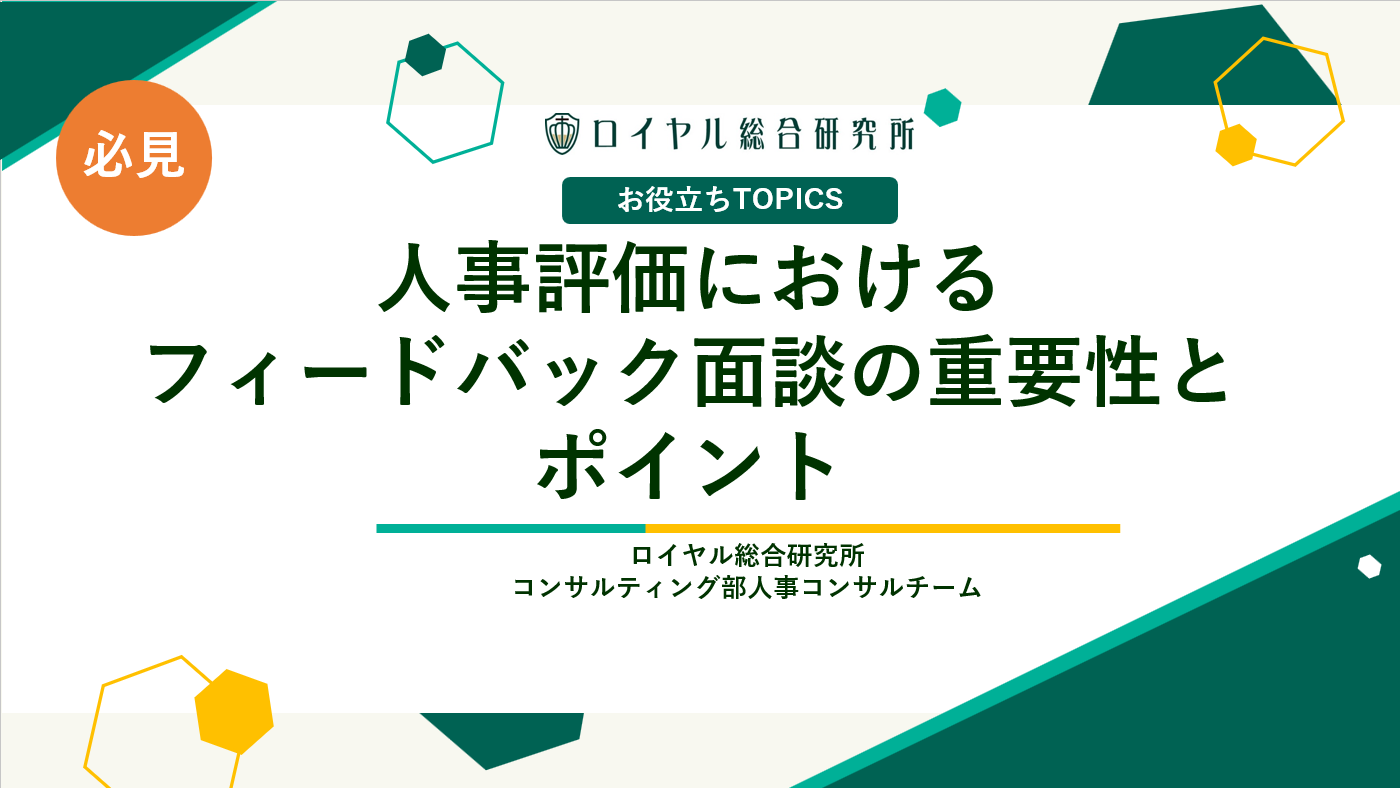






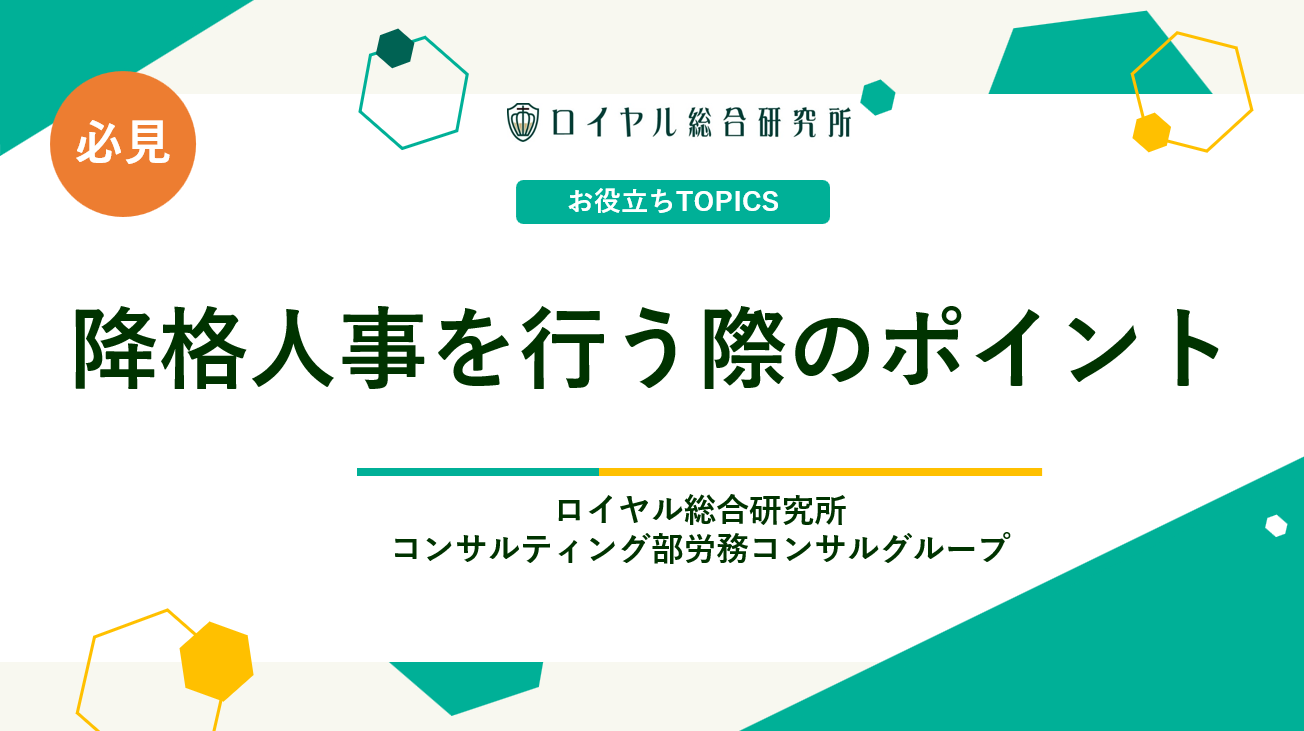
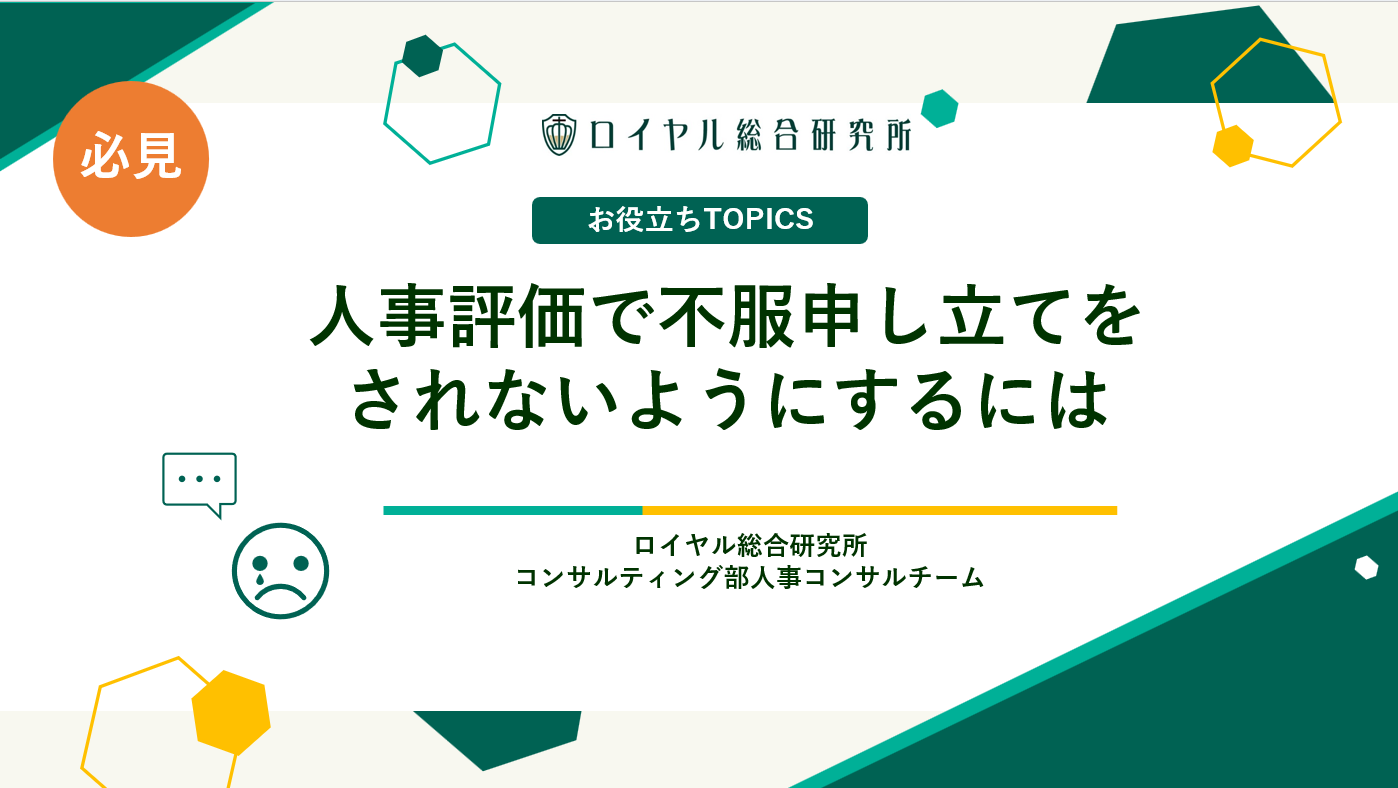
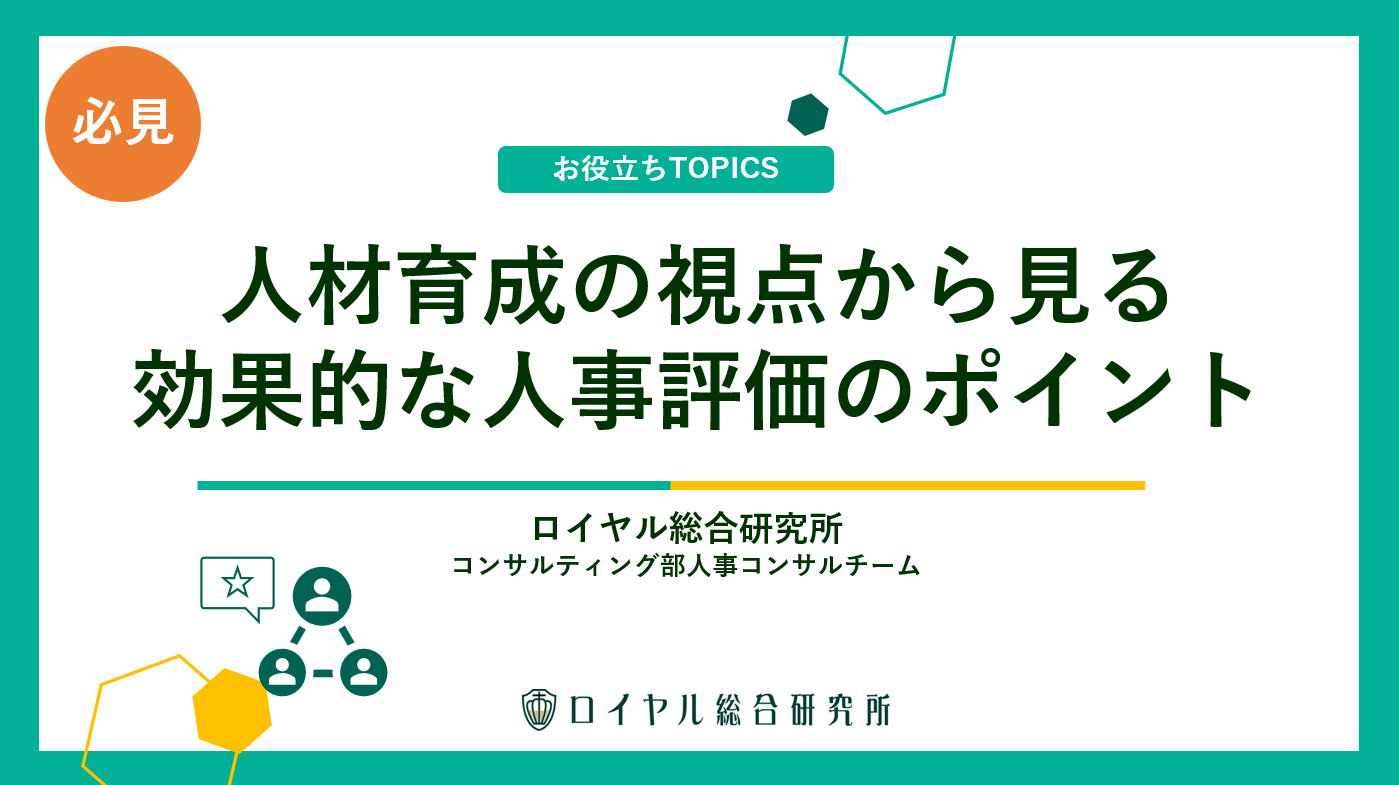
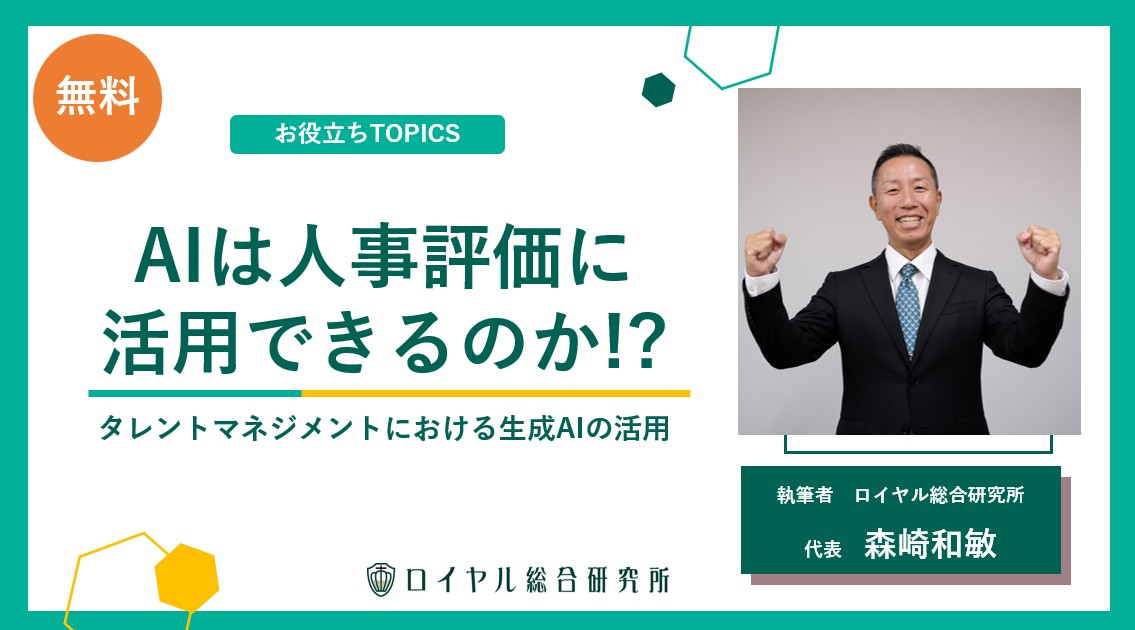

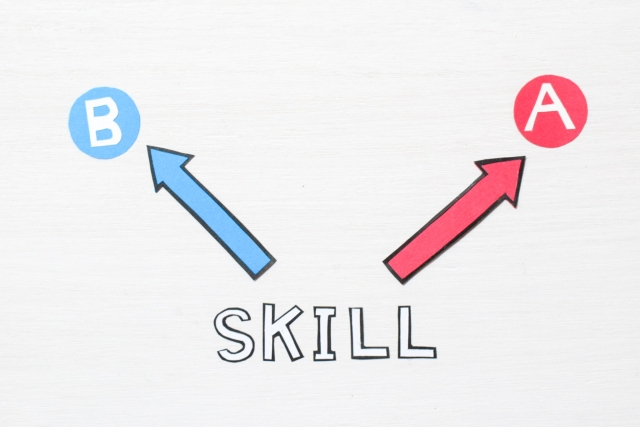


 ページトップに戻る
ページトップに戻る