目次
降格人事の必要性
なぜ降格人事をおこなうのか?
企業における降格人事は、組織の健全な運営と人材の適正配置を実現するための重要な手段です。昇進や昇格と同様に、降格も人事評価の一環であり、社員の能力や成果、行動に応じて適切な職位に配置することが求められます。
たとえば、業務遂行能力が期待水準に達していない場合や、マネジメント職としての役割を果たせていない場合など、現職のままでは本人にも組織にも悪影響が及ぶ可能性があります。こうした状況を改善するために、降格という選択肢が必要になります。
能力不足と降格の関係
降格の多くは「能力不足」に起因します。これは単にスキルが足りないというだけでなく、業務遂行に必要な判断力、責任感、対人スキルなどが求められる水準に達していない場合も含まれます。
このような場合、企業はまず「能力不足であること」を客観的に立証する必要があります。具体的には、以下のような要素が必要です。
– 能力の判定をする基準が存在すること
– 基準が適切に運用されていること
– 基準に照らして「能力不足」と判断される事実があること
– 能力向上のための措置を講じたこと
– 本人に能力向上の意思がないこと
これらを証拠として示すことができなければ、たとえ実際に能力が不足していたとしても、降格や降給の正当性は認められません。
降格には根拠を持った理由を
降格は労働条件の不利益変更に該当するため、必ず契約上の根拠が必要です。根拠となり得るのは以下のとおりです。
– 就業規則の定め(合理的であり、かつ周知されていることが必要)
– 個別の労働契約(合意内容が就業規則を上回る場合)
– 労働協約
また、降格に伴って賃金を減額する場合には、さらに慎重な対応が求められます。
たとえば、役職手当の減額が就業規則に明記されている場合でも、減額幅が大きすぎると無効と判断される可能性があります。たとえば、部長級の役職手当が30万円、課長級が10万円である場合、20万円の減額は過大とされる可能性が高いです。
降格人事の手順
降格を判断する
降格を行う前には、対象社員の業務状況や評価結果を総合的に確認する必要があります。特に、能力不足を理由とする場合には、以下のような資料を準備しておくことが重要です。
– 業務遂行能力の低さや勤務態度の悪さが分かる記録
– 能力向上のための指導や措置を講じた記録
– 改善が見られなかったことを示す記録
– 本人が改善に消極的であることを示す記録
– 降格・降給による不利益の内容を具体的に説明した記録(例:基本給の減額、賞与・退職金への影響など)
これらの資料を揃えたうえで従業員と話し合うことで、従業員が降格に納得できる合理的な根拠とすることができます。
従業員へ通知する
降格の決定後は、本人に対して正式に通知を行います。この際、口頭だけでなく書面での通知も行い、記録を残すことが重要です。通知の形式は、労働契約書の再作成、労働条件通知書、賃金に関する覚書、給与辞令など、いずれの形式でも構いません。
また、降格に伴い賃金が変更される場合には、給与計算システムの設定変更や、社会保険の随時改定手続きが必要になることもあります。たとえば、基本給が減額され、3か月間の報酬平均が2等級以上下がる場合には、標準報酬月額の変更手続きが必要です。
降格の影響
降格後にフォローアップを行う
降格後も、社員が再び成長できるように支援することが重要です。たとえば、定期的な1on1ミーティングを通じて、業務の進捗や心理的な状態を確認し、必要に応じて業務内容の調整やスキルアップの支援を行うことが望まれます。
社員のモチベーションの低下
降格は社員の自尊心やモチベーションに大きな影響を与える可能性があります。
特に、理由が不明確な場合や、納得感がない場合は、離職や職場の士気低下につながることもあります。
そのため、降格後のフォローアップが非常に重要です。たとえば、半年後に賃金を元に戻す機会を与える、改善基準を明示する、能力向上のための支援を行うなどの措置を講じることで、モチベーションの維持と再成長の機会を提供することができます。
パワハラとの関連性
降格が不適切に行われた場合、「パワハラ」として認定されるリスクもあります。特に、業務上の必要性がないにもかかわらず、人格否定や嫌がらせのような形で降格が行われた場合は、法的責任を問われる可能性があります。
そのため、降格の判断には客観的な根拠と合理的な理由が必要であり、手続きも適正に行うことが求められます。
降格人事の適切な伝え方
具体的に話し合う
降格を伝える際には、抽象的な表現ではなく、具体的な事実や行動に基づいて説明することが重要です。たとえば、「マネジメント能力が不足している」といった曖昧な表現ではなく、「部下からのフィードバックで指示が不明確との声が多く、業務の進行に支障が出ている」といった具体的な事例を挙げることで、本人の理解と納得を得やすくなります。
過去の評価や指導内容を記録として詳細に残しておくと、それをもとに具体的な根拠を提示することができ、説明の説得力が高まります。
弁明の機会を与える
降格人事を行う際には、社員に対して「異議申し立ての機会」を設けることが重要です。
これは、評価や処遇に対して社員が自らの意見を述べる権利を保障するものであり、手続きの公正性を担保する上でも不可欠です。
異議申し立ての機会が与えられていない場合、人事評価制度の運用が恣意的であると判断され、降格や降給の合理性が否定されるリスクがあります。
特に、評価結果の開示や説明がなされていない場合には、制度の濫用とみなされる可能性が高まります。
理由を明確に説明する
降格の理由は、本人が納得できるように明確に説明する必要があります。曖昧な説明は不信感を生み、職場の信頼関係を損なう原因になります。
たとえば、「業績が悪いから」ではなく、「3期連続で目標未達であり、改善指導を行ったが成果が見られなかった」といった具体的な説明が求められます。
フォローアップを行う
降格後も、社員が再び成長できるように支援することが重要です。たとえば、定期的な1on1ミーティングを通じて、業務の進捗や心理的な状態を確認し、必要に応じて業務内容の調整やスキルアップの支援を行うことが望まれます。
降格と懲戒処分
懲戒処分とは?
懲戒処分とは、就業規則に違反した社員に対して、企業が制裁として行う処分のことです。
具体的には、戒告、譴責、減給、出勤停止、懲戒解雇などがあり、いずれも「制裁的性格」を持つ処分です。
たとえば、無断欠勤や業務命令違反、会社の信用を著しく損なう行為などが対象となります。
懲戒処分を行うには、就業規則にその根拠が明記されており、かつ社員に周知されていることが必要です。
降格と懲戒処分の違い
降格は、社員の能力や適性に基づく人事上の配置転換であり、懲戒処分とは異なります。懲戒処分が「制裁」であるのに対し、降格は「適正配置」の一環として行われるものであり、目的も性質も異なります。
ただし、同一の事案に対して懲戒処分と降格を重ねて行うことはできません。これは「一事不再理の原則」に基づき、同じ事案に対して二重の処分を行うことは不適切とされているためです。たとえば、非違行為に対して譴責処分を行った後に、同じ理由で降格を行うことは原則として認められません。
社員の権利と企業の責任を守るには
労働契約法に基づく保障
労働契約法第3条第3項では、「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」と定められています。これは、企業が人事異動や降格などの業務命令を出す際に、社員の私生活への配慮を求める趣旨です。たとえば、育児や介護などの事情がある社員に対して、著しい不利益を伴う異動や降格を命じた場合には、業務命令権の濫用とされ、無効と判断される可能性があります。
適切な就業規則の整備
降格や降給を行うには、就業規則においてその根拠が明確に定められている必要があります。たとえば、「降格に伴い賃金を減額することがある」といった抽象的な記載では、契約上の根拠として認められない可能性があります。具体的には、降格の要件、降給の基準、減額幅、適用時期などが明記されていなければなりません。これらが不明確な場合、就業規則を根拠とした降給は無効とされるリスクが高くなります。
法的リスクと対策
不適切な降格や降給は、労働契約法違反や権利濫用とされ、無効と判断される可能性があります。特に、以下のような場合にはリスクが高まります。
– 降格・降給の理由が曖昧で、客観的な評価に基づいていない
– 評価制度の内容や運用に合理性がない
– 降格に伴う賃金減額が過大で、緩和措置が講じられていない
– 降格前に能力改善のための指導が行われていない
これらのリスクを回避するためには、評価制度の透明性を確保し、記録を適切に残すことが重要です。
違法な降格を防ぐために
違法な降格を防ぐには、以下の点に留意する必要があります。
– 降格の理由を客観的な評価に基づいて説明できるようにする
– 降格前に、能力向上のための指導や支援を行い、その記録を残す
– 降格後の処遇(賃金、職務内容など)について、社員に十分な説明を行い、合意を得る
– 合意が自由意思に基づくものであることを担保する(強制や誤認がないようにする)
たとえば、降給について合意書を取り交わしたとしても、社員が不利益の内容を十分に理解していなかった場合や、合意しなければ雇用が継続できないと誤認させるような言動があった場合には、その合意は無効とされる可能性があります。
降格後の職務と責任
業務改善のための指導
降格後の社員に対しては、単に職位を下げるだけでなく、業務改善のための具体的な指導を行うことが求められます。これは、使用者が労働者の能力向上に向けた支援を行う義務を負っているためです。特に、高度な専門職や管理職でない限り、能力不足の状態に至ったことについては、使用者にも一定の責任があるとされます。したがって、降格後も定期的な面談やOJTなどを通じて、業務遂行能力の向上を支援する必要があります。
キャリアの再スタートの機会
降格は社員にとってマイナスの出来事である一方で、再スタートの機会でもあります。企業としては、社員のスキルや適性を再評価し、適切な職務への再配置を行うことで、キャリアの再構築を支援することが重要です。たとえば、スキルマップを活用して、社員の強みや成長の可能性を可視化し、今後の育成方針を明確にすることが有効です。これにより、社員のモチベーションを維持し、組織全体の生産性向上にもつながります。
人事評価にHRvisを活用しませんか?
降格人事を行う上で必要なのは「客観的に評価すること」「具体的な根拠を提示すること」「内容を記録しておくこと」「今後の育成方針を明確にし、再成長の機会を与えること」です。HRvisはこの4つをサポートできる機能が詰まっています!
HRvisの「AI評価支援機能」では、AIが事実をもとに一次評価を作成するので、上司による恣意的な評価を避け、客観的な評価を行うことができます。説明の説得力が増します。「面談記録機能」を活用すれば、過去の評価や指導内容をもとに、人事評価の具体的な根拠を提示することができ、説明の説得力が高まります。さらに「スキルマップ」を活用すると社員自身の能力を見える化できるので、今後の育成方針を明確にし、再成長の機会を提供することができます。
HRvisを導入して、効率的な人事制度を運用しませんか?
ロイヤル総合研究所 コンサルティング部

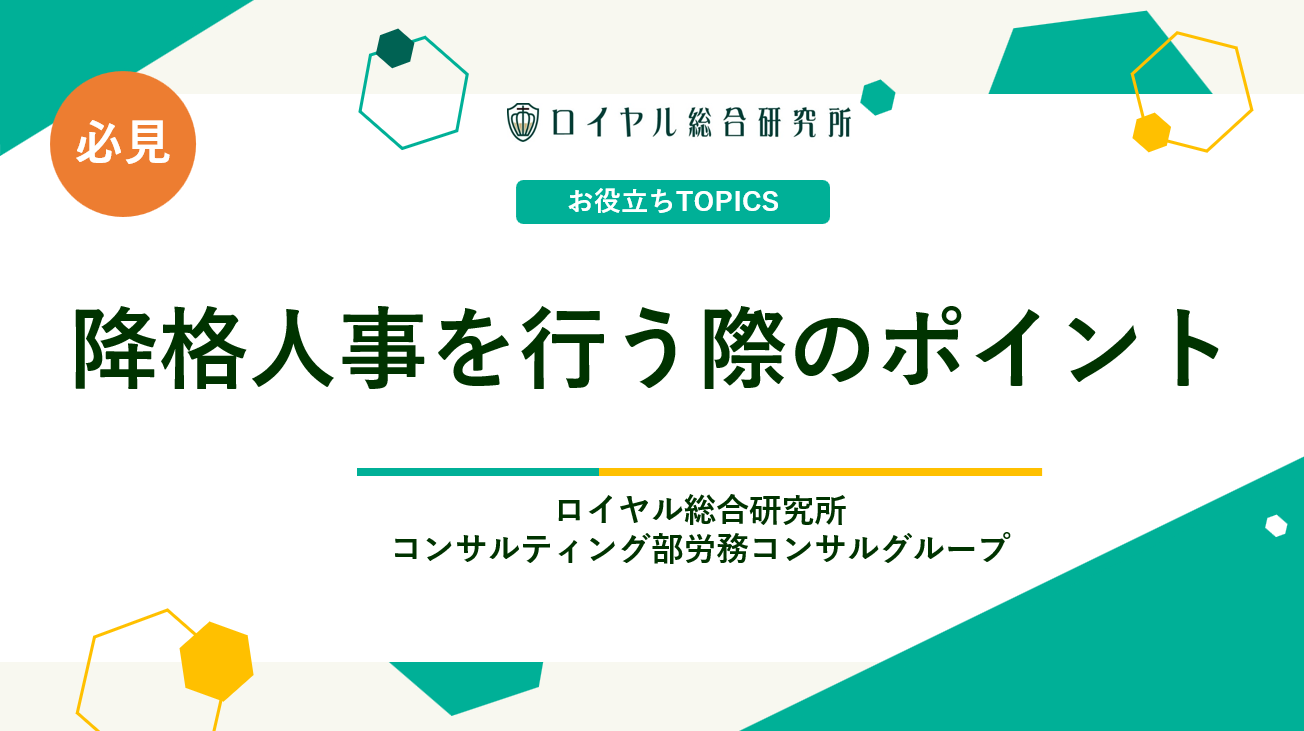
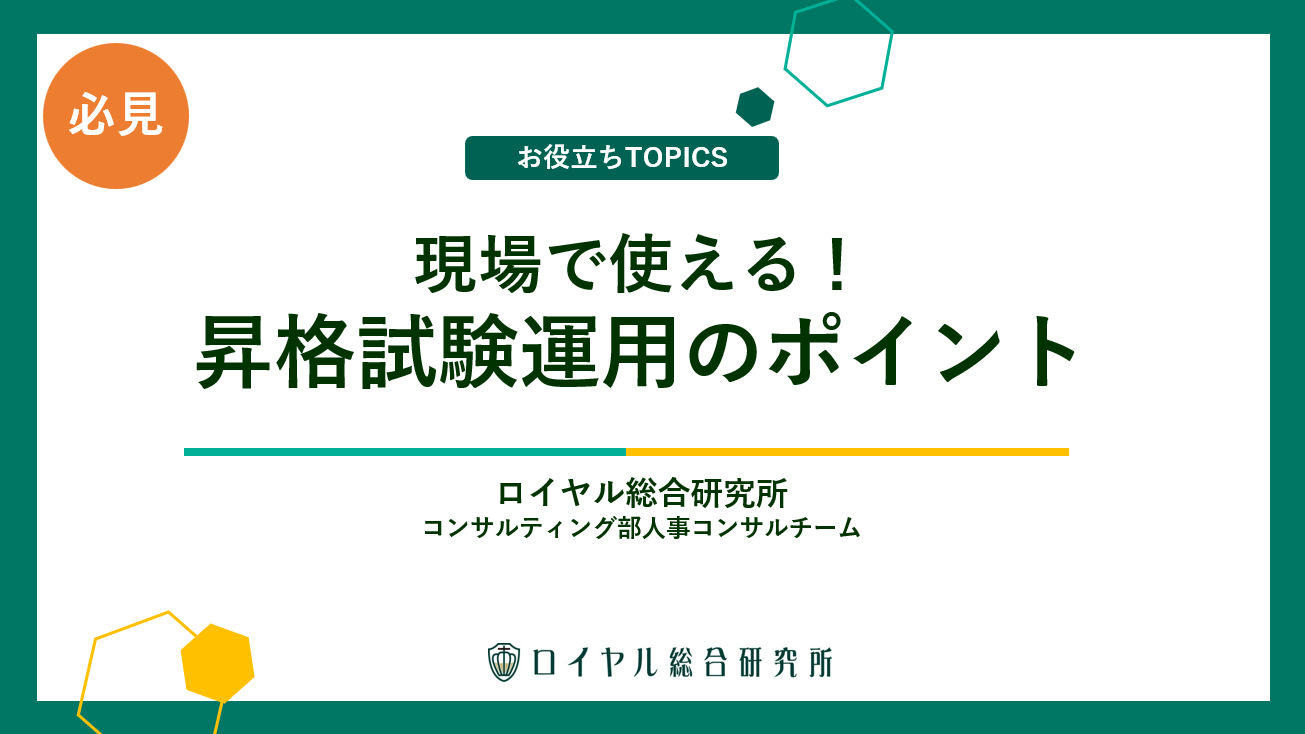
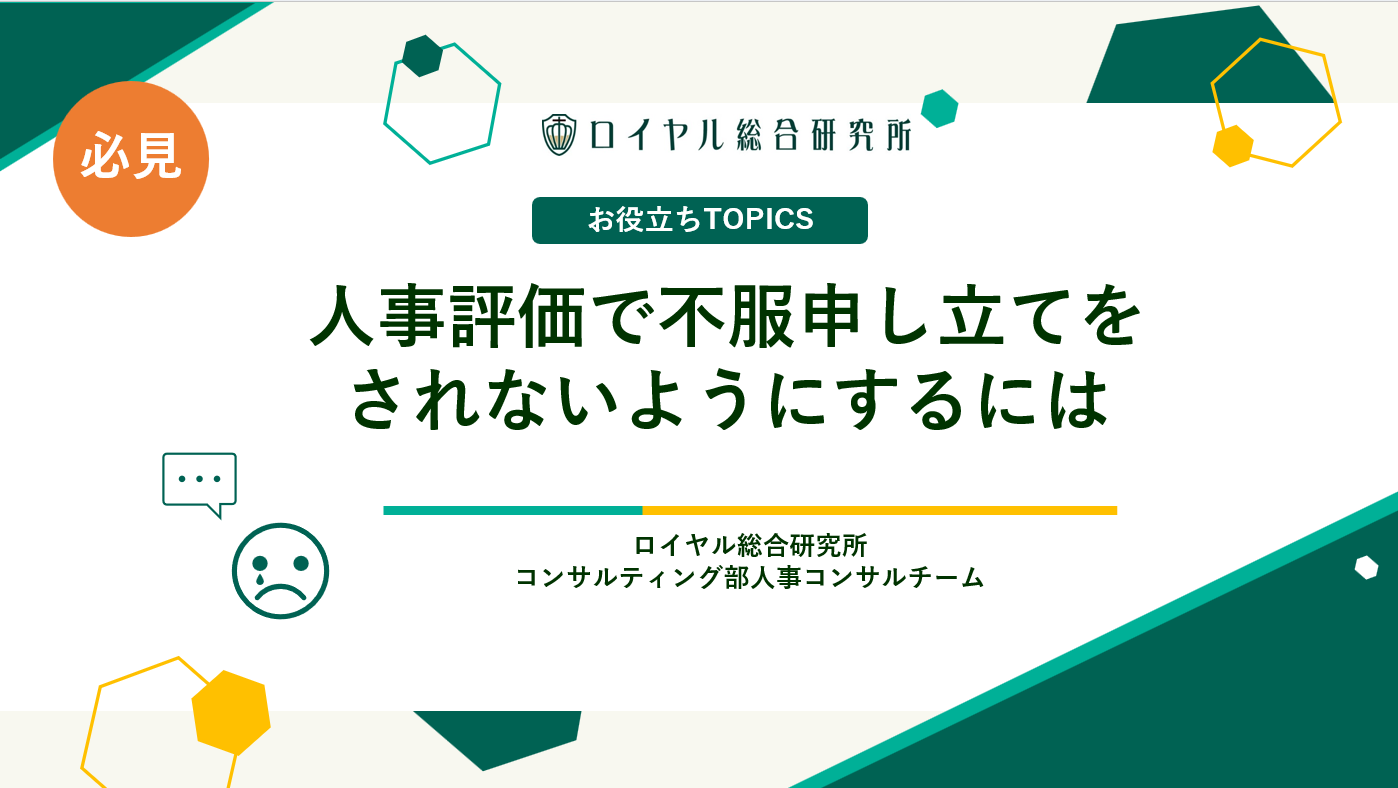
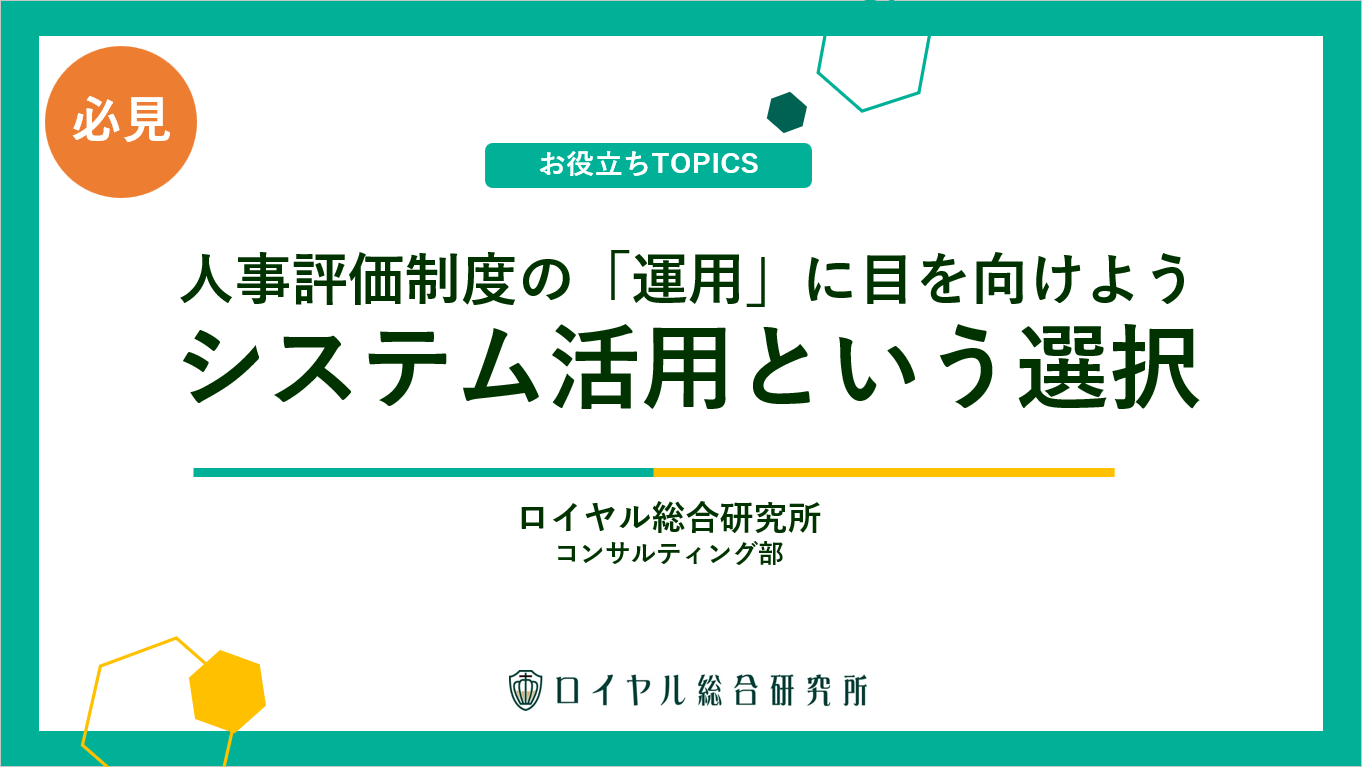
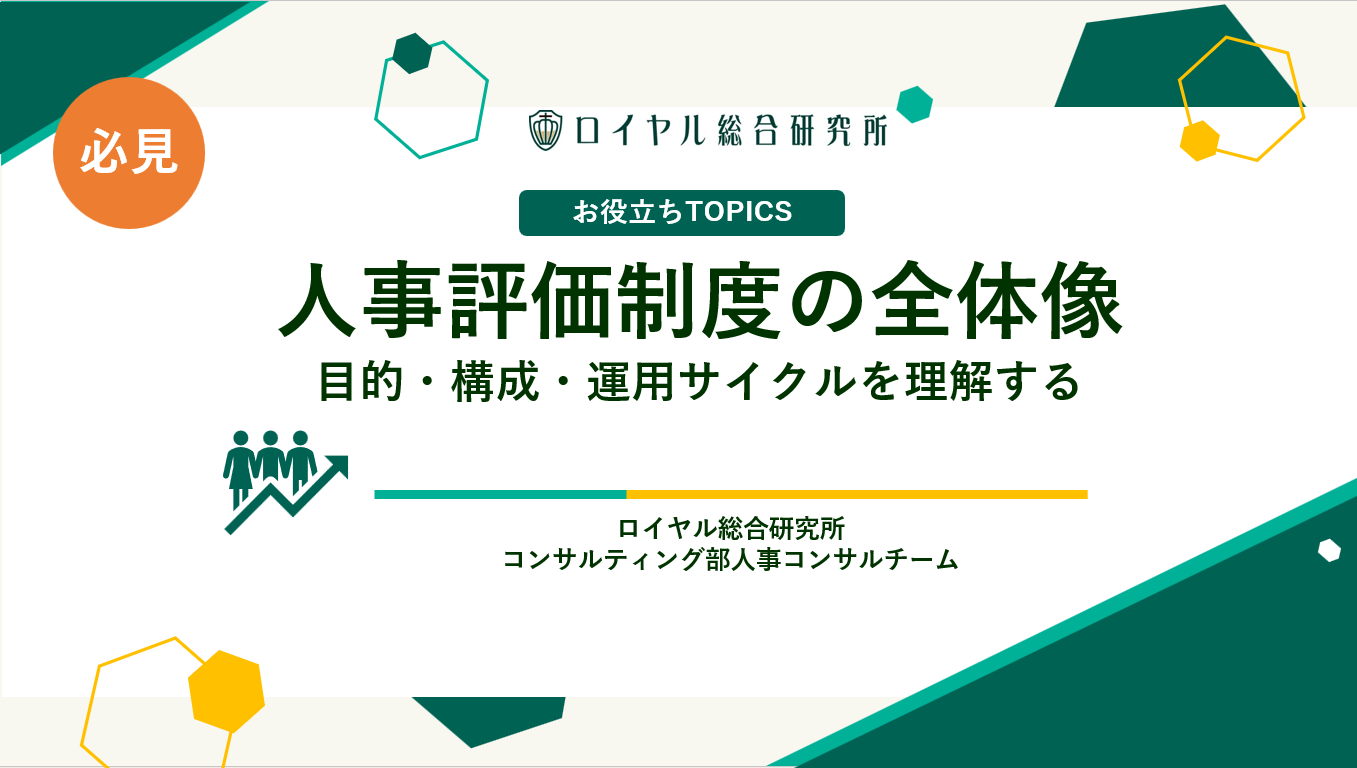
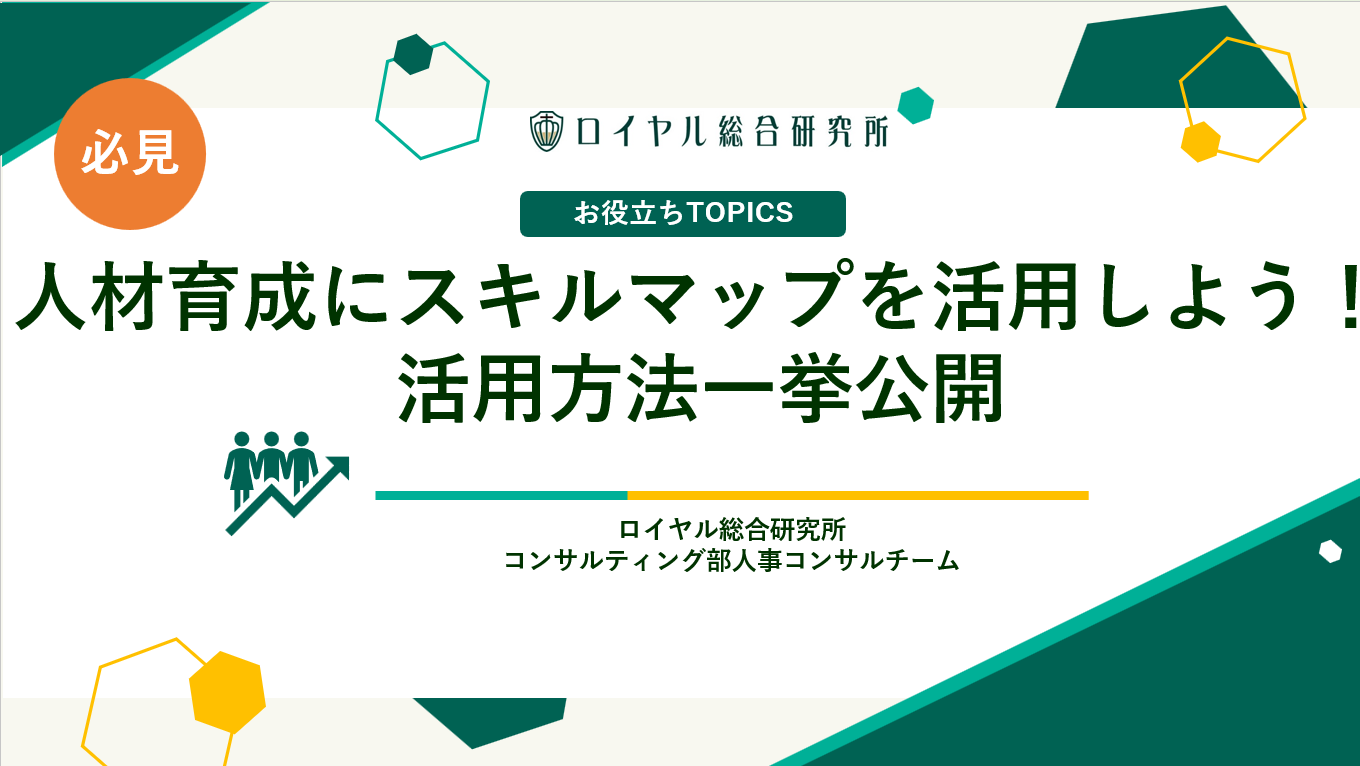
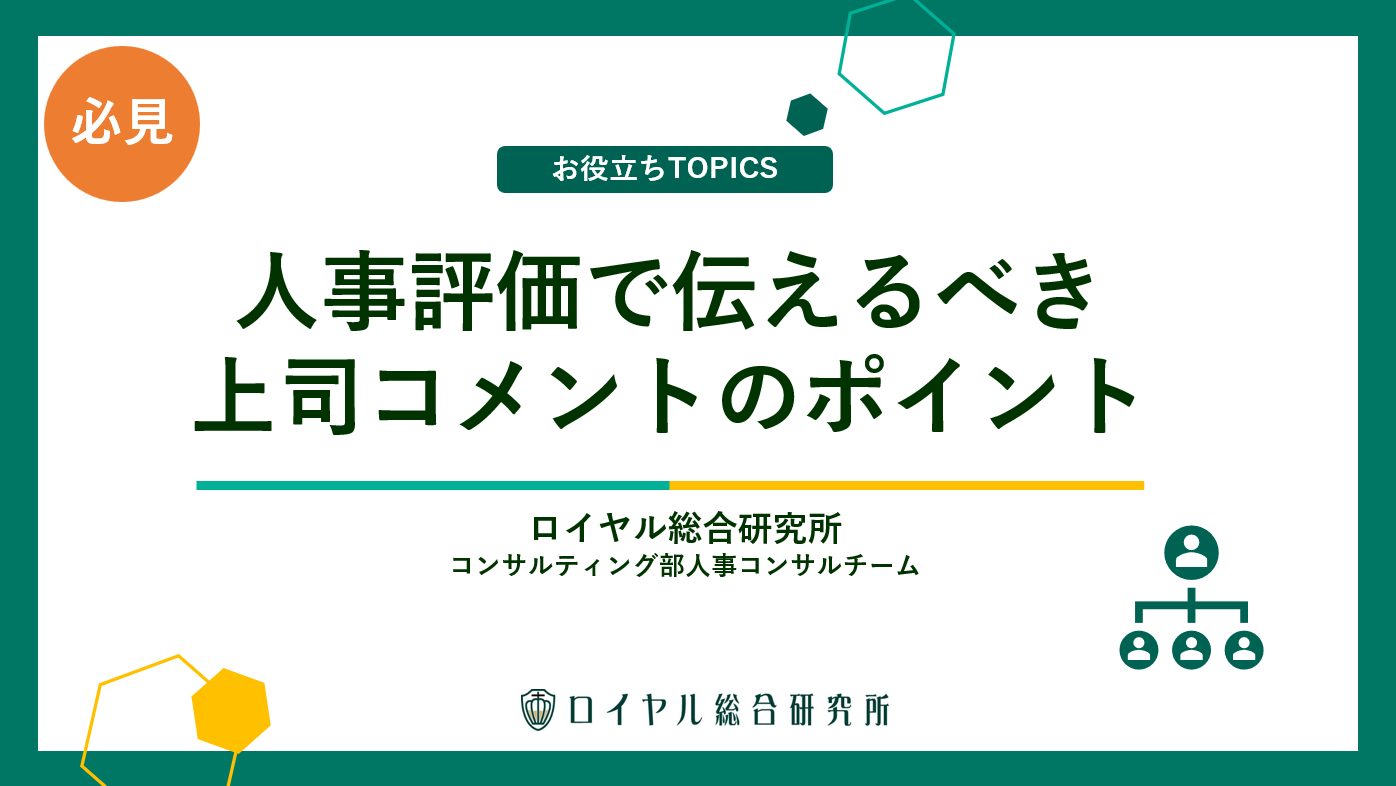
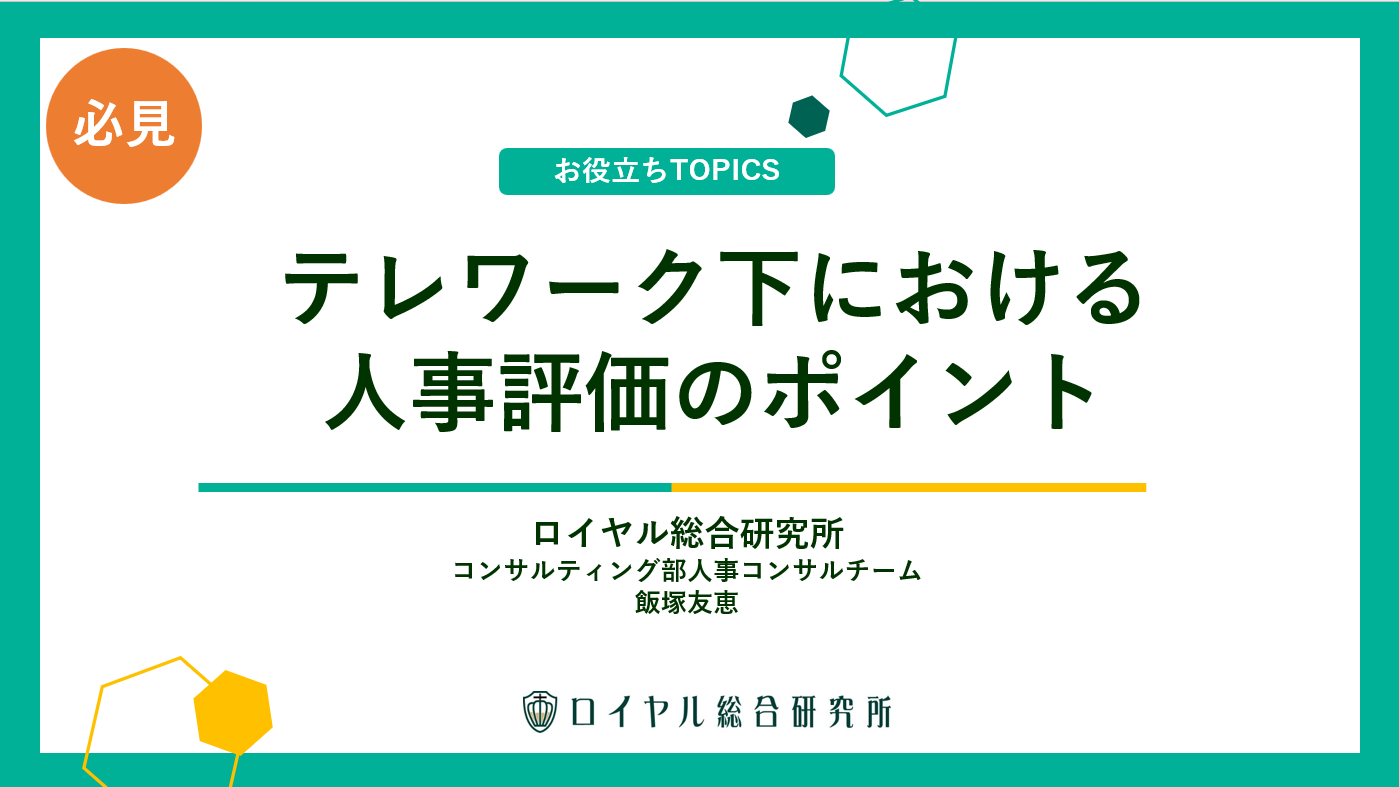
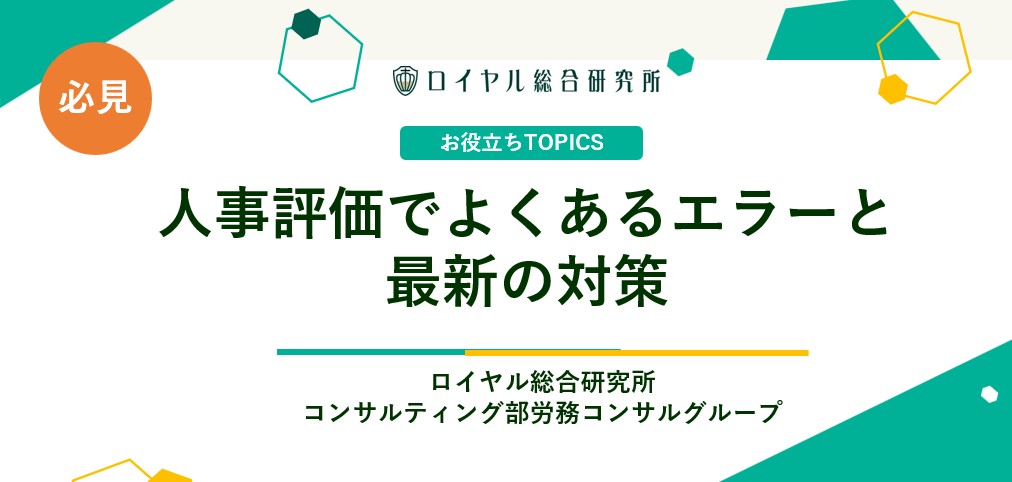
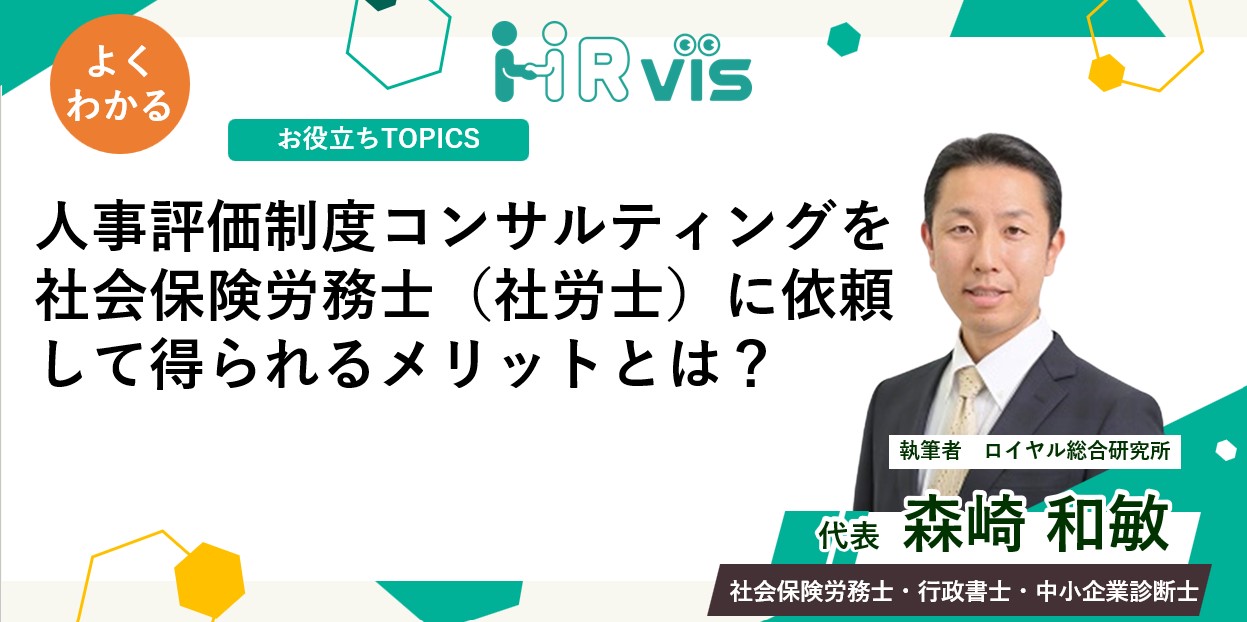
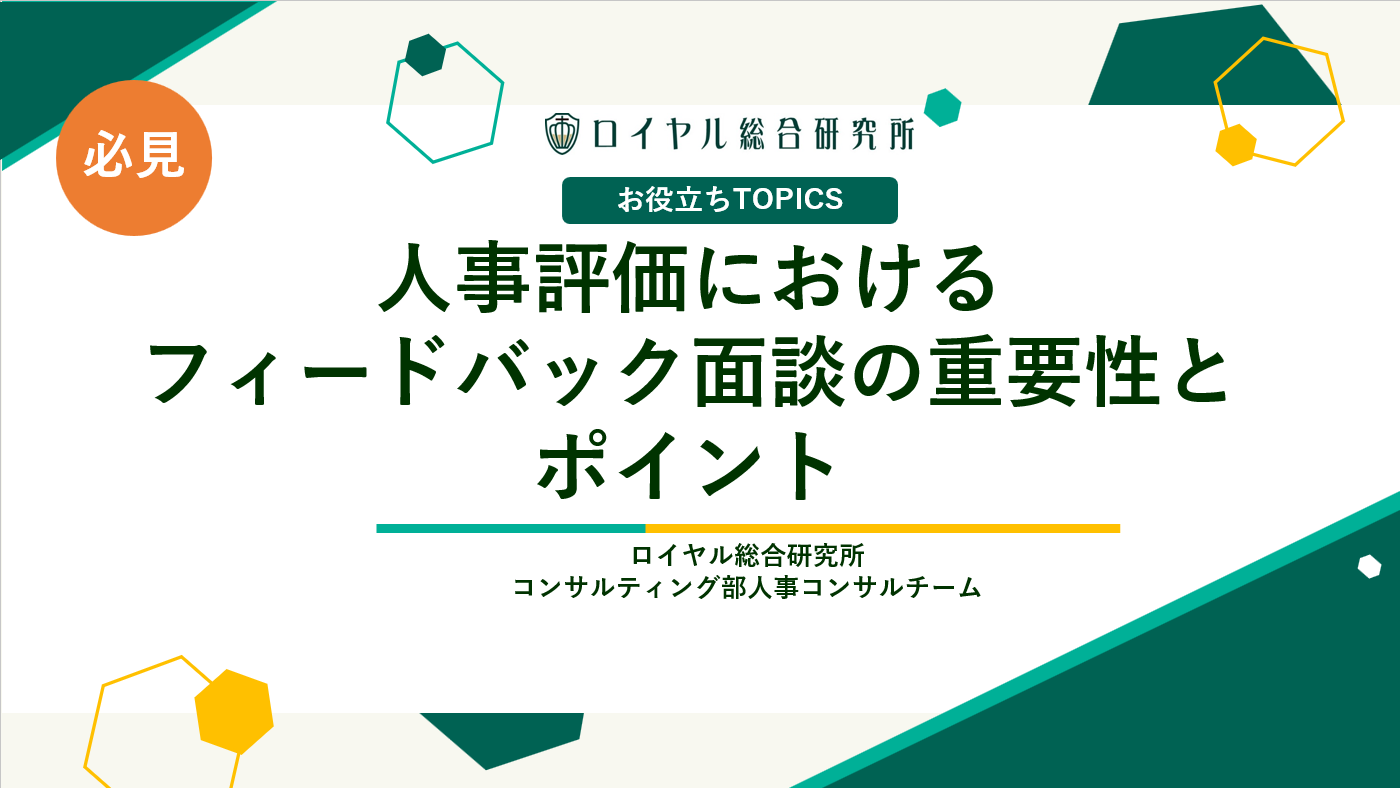



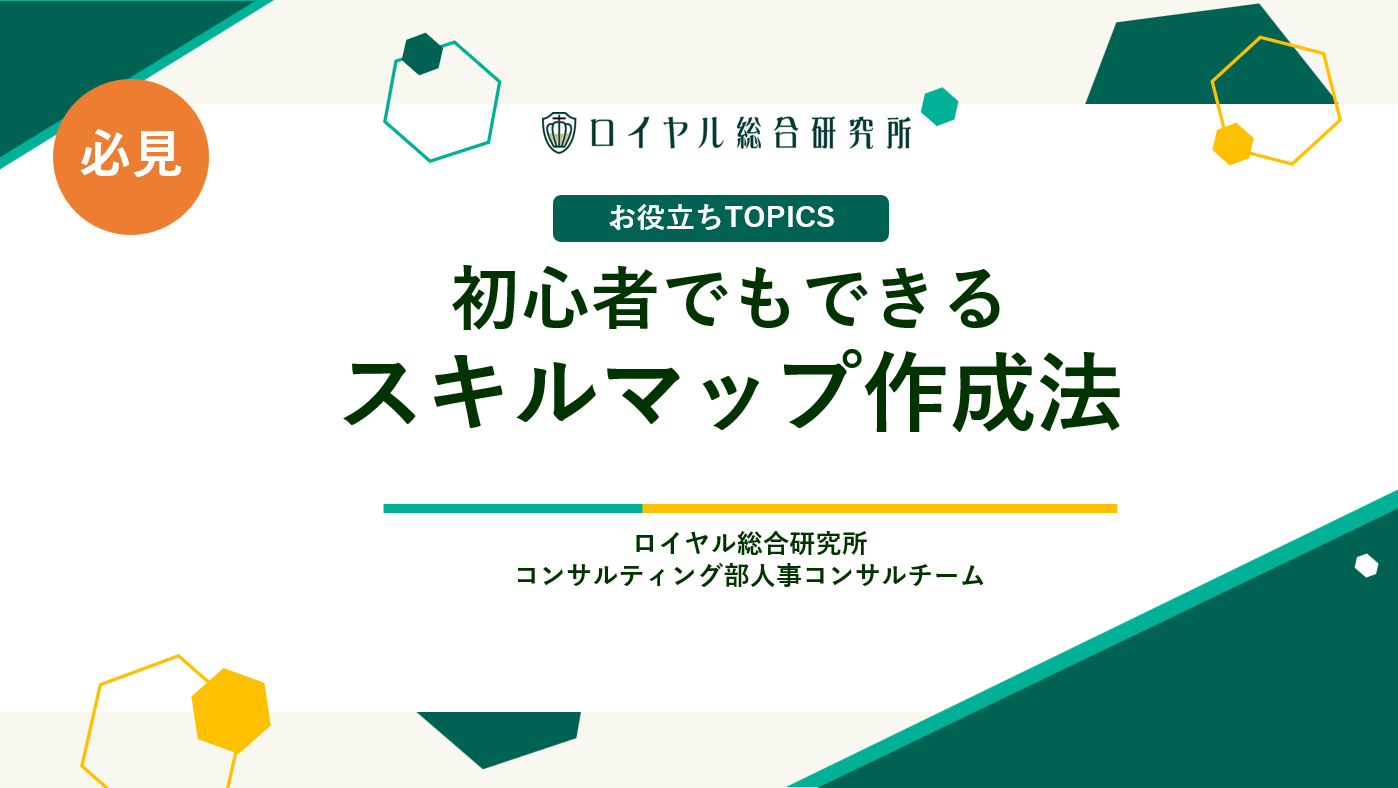
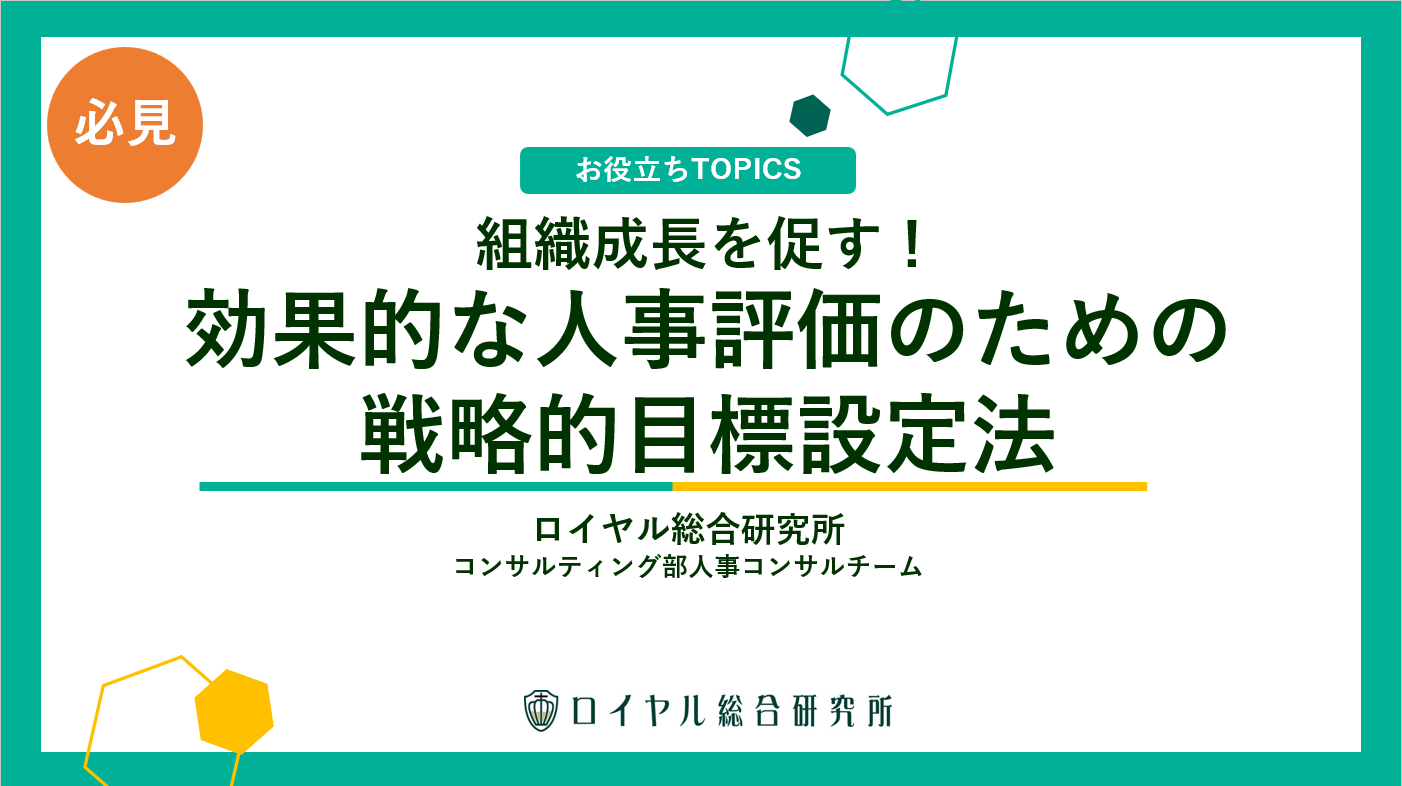
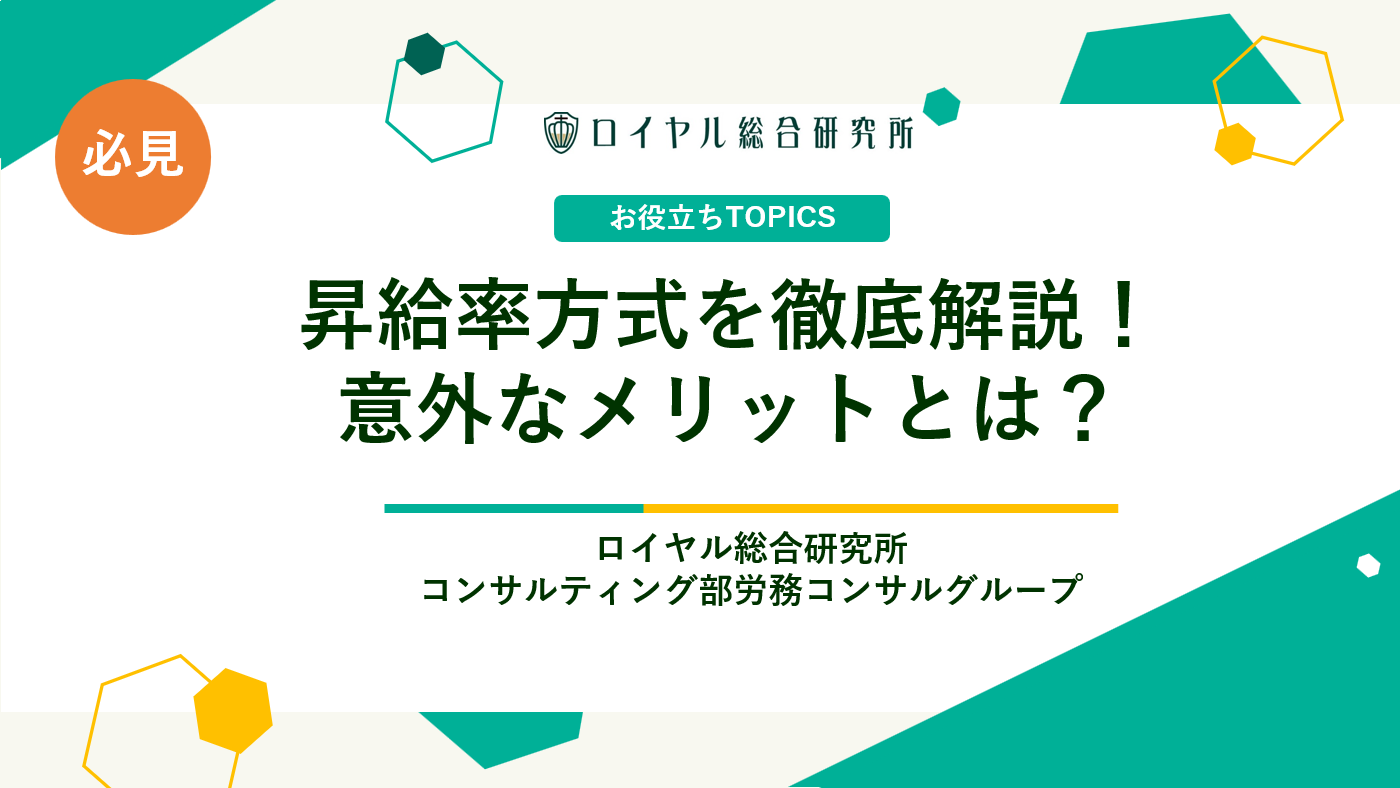


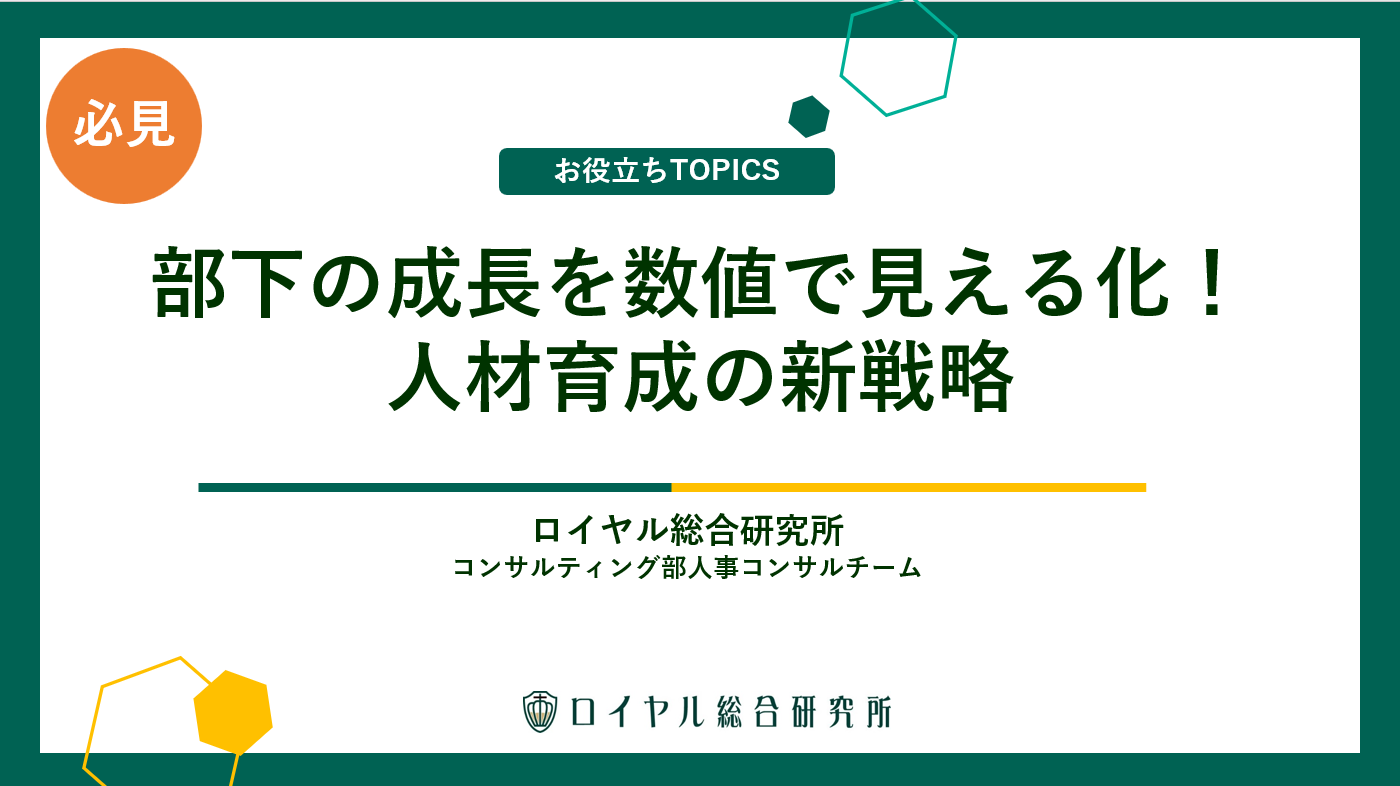
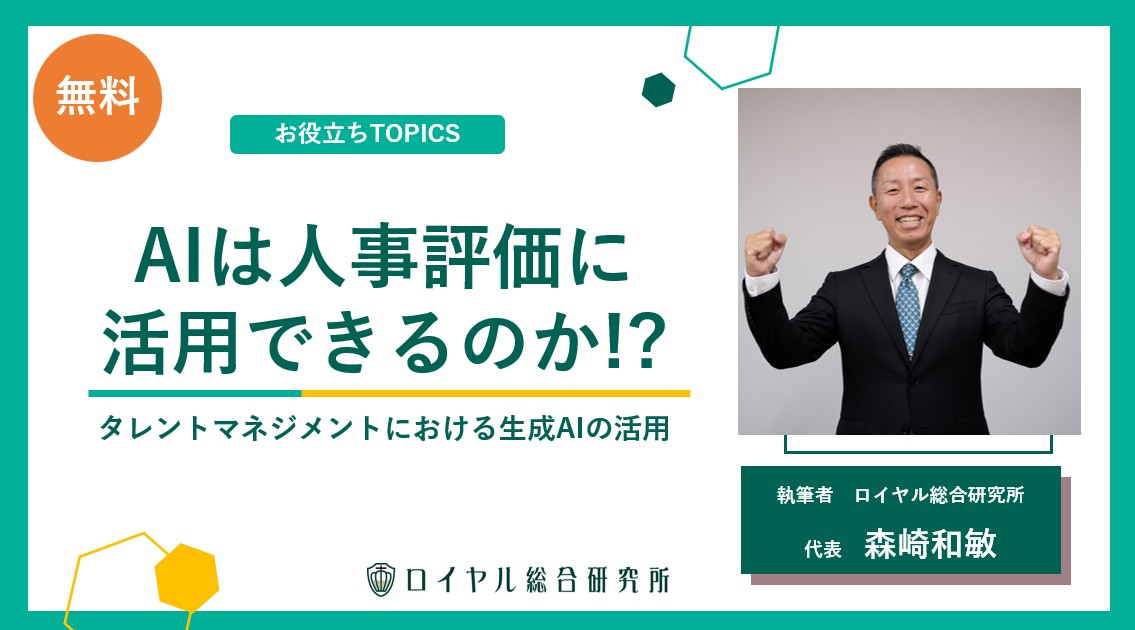

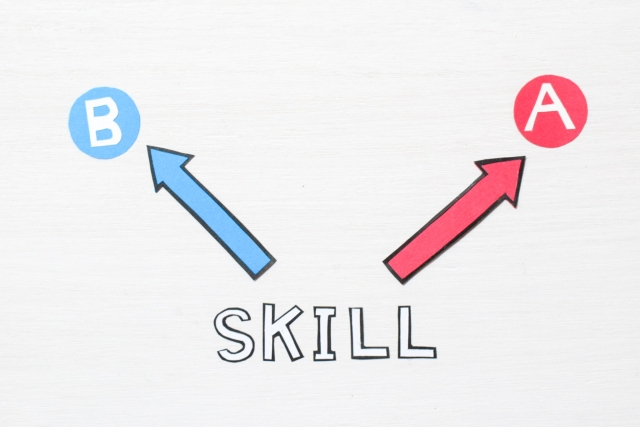


 ページトップに戻る
ページトップに戻る